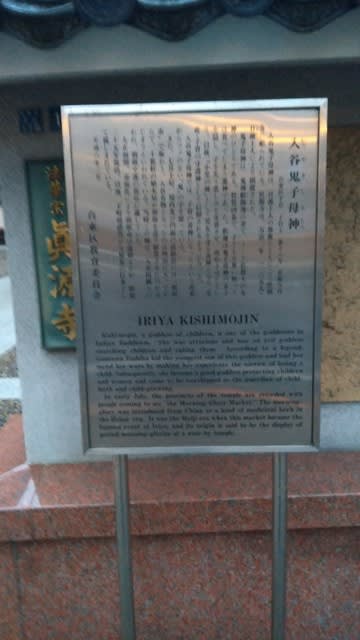山手線で、


構内は作品が目白押し。
ズラリと並ぶ菊の回廊。
こちらは厚物。花弁がふっくらと幾重にも重なる品種です。
一輪挿しは切り花。
背の低い三本仕立てはだるま。
湯島天神は、天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)、菅原道真公が祀られていますが、徳川家康公が江戸城入城から尊び、徳川綱吉公も焼失の折りに復旧資金を寄進した、由緒ある天満宮です。
他にもいろいろな記念碑がありまして、こちらは文具至宝碑。
中国より渡来した紙筆墨硯は、読み書き算盤の寺子屋時代より、明治にかけ高い文化を育てる文具として、大きく貢献をしてきました。
文化の日を文具の日として定めるに当たり、学問の神さま湯島天神の境内に建立されました。
いまや瓦斯灯はほぼ無くなりましたが、都内で屋外の瓦斯灯はここだけになります。ではなぜここなのか?
こちらは泉鏡花の小説「婦系図」で男女の別れの舞台となった場所であり、映画化時の主題歌「湯島の白梅」には、歌詞に青い瓦斯灯が歌われており、それが縁で残されています。境内には泉鏡花の筆塚もあります。
「婦系図」は、明治に起こった舞台演劇、新派の演目となり上演されました。名セリフ、
男「月は晴れても心は暗闇だ。」
女「切れるの別れるのって、そんな事は芸者の時に云うものよ。私にゃ死ねと云って下さい。」
切ないっすね。。
そして、水谷八重子さんにより、新橋演舞場にあった新派の碑は、演舞場改築時にこちらに移されたそうです。
いろんなつながりがあるんですね。
新派は明治期に起こった芝居演劇で、対して歌舞伎は旧派と言われています。
この他、王貞治さんの努力碑もあるそうで、いろいろみて回れますね。
こちらは宝物殿。
江戸神輿をはじめ、広重の『江戸名所百景』や能面など多数展示されています。早朝なのでまだ開いてませんでした。
菊まつりに戻って、趣向を凝らしたいろんなブース。盆庭という総合庭園なのだそうです。
これも力作。
おっと、本殿へのお参りを忘れちゃいけない。こちらへは、これからの子供の受験成就を願い、来たのが本当の目的。湯島天神は学問の神様、菅原道真公を祀る神社だからね。
では、また鑑賞開始。
小菊を断崖から垂れ落ちるように見せる懸崖作り。
大作りは千輪咲きともいいます。
これだけ一斉に咲かせるのは、手間がかかるだろうなー。
菊人形のコーナー。
今年のテーマは西郷どん。桜島をバックに右から西郷どん、妻の糸さん、大久保どん。
菊の盆栽。
参集殿。パーティーや会合を行えます。菊まつりといい、地域生活に溶け込んでいるんですね。
福助という低い活けかた。見た目が福助人形に似ているのでそう呼ばれます。
本殿から社務所間にかかる橋には、中懸崖作りのアーチが。
反対側から。
撫で牛。
道真公の遺言は、「自分の遺骸を牛にのせて人にひかせずに、その牛の行くところにとどめよ」とあり、その牛は、黙々と東に歩いて安楽寺四堂のほとりで動かなくなり、そこを御墓所と定めたといわれています。道真公と牛は切っても切れないものということなのです
こちらの像は、撫でられた部分が白くなっています。自分の悪い部分を撫でればよいみたいですね。
この大作りも見事です。
文京菊会のブース。中央の大懸崖作りが赤いハートになっています。
菊の種類は管物、大掴、江戸菊、一文字菊、巴錦などいろいろあり、細かく見ていくともっと奥が深いみたいですよ
さて、そろそろおいとまして、御徒町に向かいますか。
男坂と呼ばれる急坂を降ります。ちなみに写真の左には緩やかな女坂があります。
坂の下からは、学問のみちと呼ばれる小路を歩きます。受験生や親御さんが思いを胸に、天神さまへお参りに向かう道は、参道といった趣はなく、江戸下町情緒を残す小ざっぱりした閑静さが、心を落ち着かせてくれます。
右には、ほー、パルコができてる。松坂屋と連絡通路でつながってます。
御徒町駅到着。
台東区掲示板の酉の市。これも見てみたいんだが、ちょいと遠い。秋から冬の季節は、花川戸のはきだおれ市等、催しが続くので、スケジュールが合えば行きたいなぁ。
あ、神田明神に寄りたかったけど、時間に余裕がなくなったんで、羽田に向かいます。
(記事:2018年11月 Update:2020年9
月)