 | 日御子 |
| クリエーター情報なし | |
| 講談社 |
福岡ゆかりの作家としては卑弥呼の邪馬台国は九州であると力説したかったに違いない。
志賀島で発見された「金印」を埋める話から始まる。
中国の言葉を通訳する役目の王に仕える使譯一族の数代に渡る歴史絵巻を語る手法で、
側面から邪馬台国が描かれていた。
いつ卑弥呼が出てくるのかもどかしい気持ちで読み進んだ。
日御子がシャーマンでいかに人望厚い女王であったかと言うより、
大国中国と日本の当時の文化対比や風俗、民俗にに興味が惹かれた。
食べ物についても詳しく書かれており、今の醤油の前身だろう調味料などもはじめて知った。
そして忘れてはいけないと思わせる言葉がこの歴史小説のベースにずっと流れていた。
使譯あずみ一族に伝わる三つの教えだ。
.人を裏切らない。
.人を恨まず、戦いを挑まない。
.良い習慣は、人を変える。
そして、途中から加わった日御子に仕えた炎子(えんめ)の教え。
.骨休めは、仕事と仕事の転換にある。
代々教えを一族に伝えるだけでなく、統治者のひみこが守り、
大国である中国への献上品として最も喜ばれたという若人、生口へ
知らない国、帰る国はなく骨を埋める国での処世術として教えられた。
どれも日常生活に置いても国と国に於いても、こうであれば争いはおこらないだろうし
自分自身も国も安泰であろうと思われる。
個々の心の平安、争いより和平。
骨休めの項も良い習慣の項も
しかし、俗人である私自身がまずもって守れそうもない教えであるのも事実。
怠けるから生活の場に乱れが生じ重なり…
大掃除の、断捨離などと発奮しなければいけない羽目になる気もする。
時に触れ肝に銘ずる。
相手が裏切ったり戦いを挑んできたらどうするか?
それについても書かれていた。
裏切り、戦いの連鎖は誰かが断つことで解決を導くと。
教えを守るには強い意志の裏付けが必要と言うことだろう。
隣国の挑発に乗りそうなきな臭い今の時勢に、祈る気持ちで書き記しておく。
死の間際に父が息子に残す言葉にも作者の生死観が窺える。
人の一生は長いようで短い。
明日があると思ってもないのが命だ。
たとえ明日、命が消えても悔いが残らないような今日を送っていれば間違いない。
著者はウキぺディアによると
2008年急性骨髄性白血病に罹っていることが発覚。
半年間の入院生活を余儀なくされたが、現在は復帰している。
1947年1月22日(66歳)
歴史にはまったく詳しくないが、紙がない時代、鉄がない時代
中国から日本にいろんな技術が流れ込んだ創世記があって、
物溢れる現在が築き挙げられたのかと
うっかりコピーから即シュレッダーのような無駄の多い、物に感謝薄れる今の足元も考えさせられた。
医者をしながらこれだけの史実調べから始まる大作を何作も発表する著者って怪物くん?
『骨休めは、仕事と仕事の転換にある』
なるほど実践しておられる

本日の歩数5,211歩
(ウォーキングも寒いと言っておさぼりのワタシ…ついついこたつで小説のラストまで目がランラン^^;)
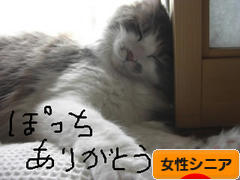 にほんブログ村
にほんブログ村 


来られたお印にふたつクリックしていただくとうれしいです=^_^=









