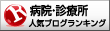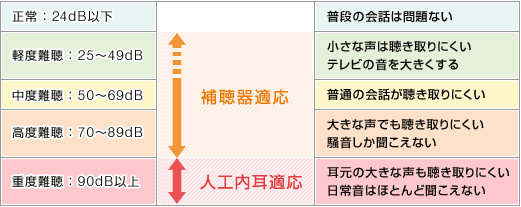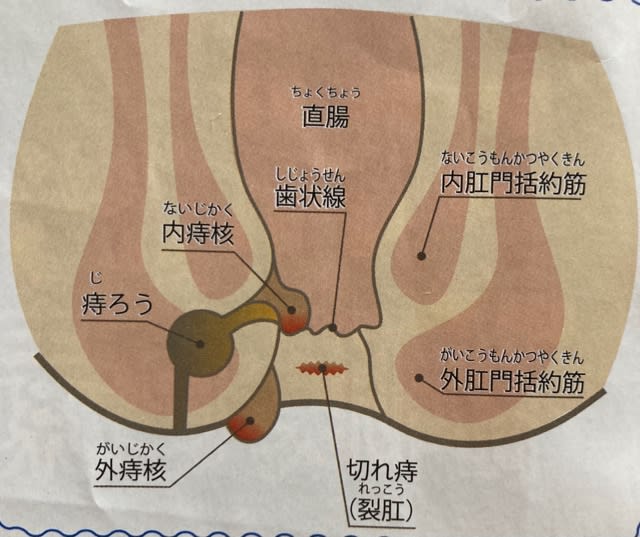当院でも新型コロナウイルスの3回目ワクチン接種を行っています。
接種開始当初は 予約が取りにくい状況があり、クリニックに直接電話問い合わせがあったり、窓口で相談があったり
一時的にとても忙しく対応していました。(事務のスタッフの人々が)
今、現在に関しては加東市内のどこのクリニックにおいても予約に空きがある状況です。
今週はかなり余裕があり、枠が埋まらないため、接種開始当初と反対の意味で枠の調節などをしています。
現在、接種に関しては2回目接種から 6か月以上経過していれば3回目の接種が可能です。
4月からの予約枠もオープンになっていますので、必要な方は予約をお願いします。
10月中に2回目接種を終えた方の予約開始は3月22日の朝9時からになっています。
ワクチンの種類を変えて交差接種をした方が抗体価はやや高値となるというデータがありました。
外来の患者さんであえて、ワクチン種類を変更して接種をされていた方が数名いらっしゃいましたが、いずれも少し1回目2回目に比べて副反応が強い(主に発熱・倦怠感)があるようでした。
また、1回目2回目で全く反応がなかった方が、3回目で強く反応したり(こちらは発熱)
お互いに副反応の出方に関しては全く予測できないな と思いながら、接種をしています。
可能であれば、翌日はゆっくり自宅で休める環境で接種した方が安心かな という印象です。
今の状況では3月中か4月以降かでワクチン種類も選ぶことが可能です。
3月ファイザー 4月モデルナ 予定です。