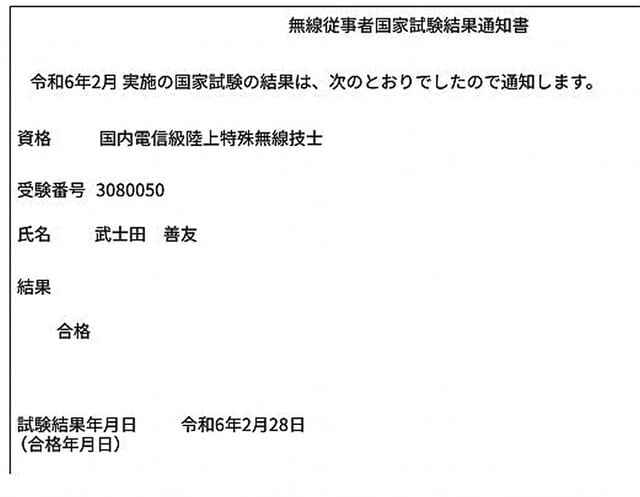今回、100日戦争を経験した後の変化は・・
とにかく毎日、1:3の符号を聴き続けた反動として「癖符号」が聞き取りづらくなってしまいました(笑) まあ、すぐに元に戻ると思いますが・・そして自分の耳に1:3の符号が染みついたせいか、長音が少しでも長いと直ぐに気が付くようになりました。私がエレキーで、いつも使う1:3.5は全く別物という感覚になりました。ですから癖バグの1:10みたいな符号は・・(笑)
モールスを最初から覚える方とは違う苦しみもあります。アマチュア無線では暗記で送受信をしていますが、例え全部が取れなくとも前後のつながりや話題の推移でQSOを続けることが可能です。また、話題も天気や気温から始まってコロナや孫の話題、そしてリグやアンテナ・電鍵等の話題などで自分の守備範囲??にある話題なのです。そしてQSOに難しい表現などは極力使いませんのであまり苦労することなく出来る訳です。
しかし試験の文章は何が出るかわかりません。練習文も宇宙船内部の空気循環や排泄物処理の話やエジソンが何かを発明してどんな評価を受けたとか、博物学がどうのこうの等・・全く興味のない文章が送られてきますので推定受信が出来ません。受験では必ず一文字単位で受信する事というのが鉄則なのですが、これがなかなか出来ないわけです。これにはホント苦労しました。
更に、電報ですから住所や氏名も打電されるのですが、これが曲者です・・何しろ無尽蔵に作り出すことが出来ますので、私が独身時代に住んでいたアパートの「フレグランス・〇✖」とか漫画の「むじな荘」なんていう変わったアパート名や京都などに多く見られる馴染みのない地名が出ないことを祈りました(笑) 振興会の公式CDには一発目に「公務員宿舎~」なんて出てきますので無いとは言えません。
氏名も三郎が「サブロウ」だったり「三ロウ」だったり、名前の前に「一等航海士」なんて付く場合もありますので気が抜けません。
最後の1か月はヤケクソもあったのですが、聞こえた通りに書き取る様にしましたので(実際には遅れ受信ですが)、電文が終わった時点で内容が解らないことが多くありました。しかしこれが結果としては正攻法なのだそうです。
多くの合格者の方が「試験文を覚えていない」というのは、こういう理由なんだと解ったわけです。
総通受験者の方は和文に加えて欧文もありますので、全くの1からですと3~5年は掛かるのでしょうね・・現在の水産高校でも専科を含めると5年の履修期間となっているようです。
総通試験では和文の後に間髪入れずに欧文ですから、練習で慣れる必要があるでしょうね。私は以前、JARLの「モールス技能検定」を受けて落ちた経験もあるのですが、やはり和文・欧文と続いており、欧文の試験なのに全てが和文に聞こえてしまったという苦い経験があります(笑)
まあ、ここまで色々と書くと随分、御大層な試験という印象ですが毎日楽しく和文楽チューをしている延長だと思えば良いだけの話です。日頃、和文QSOを楽しんでいる方は、あとホンのチョッとで合格です。
しかし、同じ受信でも暗記受信と筆記受信は、脳味噌の使う部分が違っているような気がします。