 今年も富士神社大祭が始まった。梅雨時の催事とあって天候が心配だが、昨日から今日の昼まで微かに雨が降った程度で祭りは順調に行われている。昨日は山開きの冒頭の「万灯回り」が行われ、最初から最後まで神事に同行させて頂いて、その模様を撮影して来た。
今年も富士神社大祭が始まった。梅雨時の催事とあって天候が心配だが、昨日から今日の昼まで微かに雨が降った程度で祭りは順調に行われている。昨日は山開きの冒頭の「万灯回り」が行われ、最初から最後まで神事に同行させて頂いて、その模様を撮影して来た。
実は5月の初旬に、「こまじいの家」の主(あるじ)秋元さんから電話があった。「勤労福祉センター」(以下勤福)の所長から依頼の電話がありますとのこと。翌日、勤福の所長さんからの電話で、「協働のまちづくり講座」で本駒込周辺の魅力と歴史に関する話をお願い出来ればとのことだった。
昨年の3月に「アカデミー文京」の”文の京18の町物語を聞く”講座の臨時講師を引き受けた時に私が話した内容が「本駒込」で、作成したパワポがあったので、お引き受けしても良いなと思い、直接所長さんにお会いした。パワポの画像の半分くらいをお見せするとそれで結構ですということで、開催日は10月12日(土)と決まった。
パワポの映像は古いものもあり、一部は撮影し直そうと考えて、まずは万灯回りを思い浮かべた。そこで富士講の役職に就いている、町会長に事情を話して、撮影をお願いすると快諾を頂き、昨日の撮影となった。
 6月30日、10時前に富士神社に着くと、屋台の準備を急ぐ人々の活気ある姿が目に入った。そこを抜けると社務所前に万灯が置かれていた。10時少し前、富士講の元締めの発声で講の方々はお神酒を口に、万灯は、禰宜さんを中心にして、富士講の方々15名ほどと神社をスタートした。
6月30日、10時前に富士神社に着くと、屋台の準備を急ぐ人々の活気ある姿が目に入った。そこを抜けると社務所前に万灯が置かれていた。10時少し前、富士講の元締めの発声で講の方々はお神酒を口に、万灯は、禰宜さんを中心にして、富士講の方々15名ほどと神社をスタートした。
 富士神社→稲荷坂→不忍通り→動坂→駒込病院前通り→本郷通り→信号で折り返し→本郷通り→富士神社と、万灯は台車に乗せられて、幾つかの町会を回ってきた。その間約1時間半。
富士神社→稲荷坂→不忍通り→動坂→駒込病院前通り→本郷通り→信号で折り返し→本郷通り→富士神社と、万灯は台車に乗せられて、幾つかの町会を回ってきた。その間約1時間半。

 神社に戻って来てからが大変だった。ここからは台車ではなく一人の力持ちが万灯を担いで本殿への23階段を昇り、更に神社の裏に通じる道を一周し、最後に万灯を鳥居の横のポールに入れた。その後、禰宜さんと富士講の方々は神社にお参りして神事は終わった。
神社に戻って来てからが大変だった。ここからは台車ではなく一人の力持ちが万灯を担いで本殿への23階段を昇り、更に神社の裏に通じる道を一周し、最後に万灯を鳥居の横のポールに入れた。その後、禰宜さんと富士講の方々は神社にお参りして神事は終わった。
万灯とは多くの提灯をかざしたものだったのだろうが、現在、富士神社の万灯回りに灯りは登場しない。しかし、8月28日の鎮火祭まで火は燃え続けることとなる。













 そのサイトの70番目の話題として「日本医師会館・文京グリーンコート:旧理化学研究所跡・東京府巣鴨病院跡」が取り上げられ、
そのサイトの70番目の話題として「日本医師会館・文京グリーンコート:旧理化学研究所跡・東京府巣鴨病院跡」が取り上げられ、 事務室でその旨を告げると、資料室の鍵を渡された。そこからは自分だけの行動だった。資料室には色々なものが展示されていたが、右の「小石川検定」がその間の事情をよく説明していた。そこに書かれていたことを要約する。
事務室でその旨を告げると、資料室の鍵を渡された。そこからは自分だけの行動だった。資料室には色々なものが展示されていたが、右の「小石川検定」がその間の事情をよく説明していた。そこに書かれていたことを要約する。 「
「 小石川高校の創立が1918年と知り、今年が創立100周年。盛大な式典が行われるだろうなと推定している。巣鴨病院は松沢病院へ移転したとあるように、そこには精神科が置かれていた。(写真:府立5中開校数年後の写真。不忍通りはまだない)
小石川高校の創立が1918年と知り、今年が創立100周年。盛大な式典が行われるだろうなと推定している。巣鴨病院は松沢病院へ移転したとあるように、そこには精神科が置かれていた。(写真:府立5中開校数年後の写真。不忍通りはまだない)
 (1)
(1)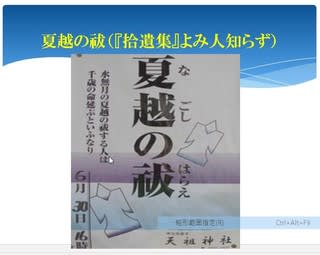
 2)
2)
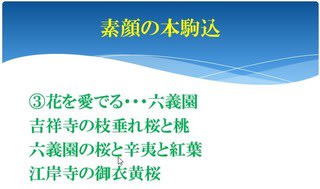 (3)
(3)
 (4)
(4)
 (5)
(5)

 館内には「文京区遺跡一覧表」が掲示されその一つに「駒込神明町貝塚」があった。許可書を提出して写真を撮らせてもらったが、その一覧には地図上の場所とその地域、「遺跡の概要」として「台地・集落跡・住居跡」と書かれているだけで、貝塚の実態はなにも分からなかった。(写真:微かに27と見える地域が駒込神明町貝塚)
館内には「文京区遺跡一覧表」が掲示されその一つに「駒込神明町貝塚」があった。許可書を提出して写真を撮らせてもらったが、その一覧には地図上の場所とその地域、「遺跡の概要」として「台地・集落跡・住居跡」と書かれているだけで、貝塚の実態はなにも分からなかった。(写真:微かに27と見える地域が駒込神明町貝塚) 後日、「文京区図書館」に“神明町貝塚”を項目にして検索すると『駒込神明町貝塚 第3地点』がフィットした。借りてきて早速読んだところ面白い事が幾つか分かってきた。(写真:借りた資料。その上の道路は不忍通り)
後日、「文京区図書館」に“神明町貝塚”を項目にして検索すると『駒込神明町貝塚 第3地点』がフィットした。借りてきて早速読んだところ面白い事が幾つか分かってきた。(写真:借りた資料。その上の道路は不忍通り)