4月27日(金)の天候芳しからず。ただ午後には雨は止むでしょうとの天気予報に期待を込めて、12時45分、西武新宿線新井薬師前から、妙正寺川を遡り始めたのでした。丁度1週間前にUタウンした地点が今回の出発点になりました。 中野区立新井小学校前で新宿線と交差し、新宿線の進行方向左側に出た川は、これより上流では2度と再び新宿線とは交差しません。流れもこの辺りはまだ澄んでいますが、遡るにつれて、水は濁り始め、水量も減り始めます。水源地妙正寺池に近づくにつれ、川底の下に小さい溝が造られ、そこを少量の水が流れるといった状況で、目線は自然と川そのものより、地上に向けられました。(写真:出発地点付近の表示)
中野区立新井小学校前で新宿線と交差し、新宿線の進行方向左側に出た川は、これより上流では2度と再び新宿線とは交差しません。流れもこの辺りはまだ澄んでいますが、遡るにつれて、水は濁り始め、水量も減り始めます。水源地妙正寺池に近づくにつれ、川底の下に小さい溝が造られ、そこを少量の水が流れるといった状況で、目線は自然と川そのものより、地上に向けられました。(写真:出発地点付近の表示)
断片的に、印象的だった5つの事柄を綴ります。 ①沼袋駅付近「平和の森公園」の緑が鮮やかでした。かって中野刑務所跡地だった所に開設された公園で、昭和55年から地下式の下水処理場とともに防災公園として順次整備がすすめられ、現在芝生広場など第二期工事まで完了開園している、と「中野区公式ホームページ」に書かれています。広大な敷地に各種広場が造られ、弥生時代の復元住居もあるとか。今日はそのサワリを垣間見たに過ぎませんせんが・・・。(写真:平和の森公園のホンノ一部)
①沼袋駅付近「平和の森公園」の緑が鮮やかでした。かって中野刑務所跡地だった所に開設された公園で、昭和55年から地下式の下水処理場とともに防災公園として順次整備がすすめられ、現在芝生広場など第二期工事まで完了開園している、と「中野区公式ホームページ」に書かれています。広大な敷地に各種広場が造られ、弥生時代の復元住居もあるとか。今日はそのサワリを垣間見たに過ぎませんせんが・・・。(写真:平和の森公園のホンノ一部)
②白鷺付近には巨大なマンションが建設途上でした。かってこの近辺にある鷺宮高校に勤務していた私は、妙正寺川をジョギングの格好の練習場所に選び、ランニングを繰り返していましたが、この様な建物を見た記憶がありません。この付近には都営住宅がありましたから、都営住宅の高層化かも知れません。
③川が中野区から杉並区に入ると、川沿いに枝垂れ桜が目立ち始めます。既に葉桜ですが、1週間前だったら見事な桜並木が見られたことでしょう。川の上に掛けられた鯉幟もこの川に彩りを添えます。この辺りまできて雨は小雨となりましたが、普段持ち歩く大型カメラは雨故え避けて持参せず、壊れかかった小型カメラはこの時点で作動せず、写真に撮れなかったことが悔やまれます。 ④妙正寺池は小規模な池でした。神田川源流の井の頭公園とは比較しようもない位の小ささでした。この近辺までもジョギングで来たことはありましたが、その一歩手前で引き返していた私は、この池を見るのは初めて。水は澄んでいず、水源は池の端に微かに見える程度。上流に向うにつれて水流が細くなるのが納得できるほどの湧水の少なさです。ただ下流ほど水が澄ん来る事が謎です。(写真:妙正寺池)
④妙正寺池は小規模な池でした。神田川源流の井の頭公園とは比較しようもない位の小ささでした。この近辺までもジョギングで来たことはありましたが、その一歩手前で引き返していた私は、この池を見るのは初めて。水は澄んでいず、水源は池の端に微かに見える程度。上流に向うにつれて水流が細くなるのが納得できるほどの湧水の少なさです。ただ下流ほど水が澄ん来る事が謎です。(写真:妙正寺池)
(写真:ツツジ右下が湧水地点か?) ⑤源流付近に「杉並区立科学館」があり、小柴昌俊博士とニュートリノ天文学が展示されいて、入館無料。関心を、地上から暫し天体に移しました。(写真:杉並区科学館入口)
⑤源流付近に「杉並区立科学館」があり、小柴昌俊博士とニュートリノ天文学が展示されいて、入館無料。関心を、地上から暫し天体に移しました。(写真:杉並区科学館入口) 雨中を歩いた今回の散策でも、歩いたからこそ知る幾つかがありました。散策終点から更に荻窪まで歩き「極楽屋」という銭湯に浸り、帰宅の途に就いたのでした。(写真:銭湯極楽屋入口)
雨中を歩いた今回の散策でも、歩いたからこそ知る幾つかがありました。散策終点から更に荻窪まで歩き「極楽屋」という銭湯に浸り、帰宅の途に就いたのでした。(写真:銭湯極楽屋入口)
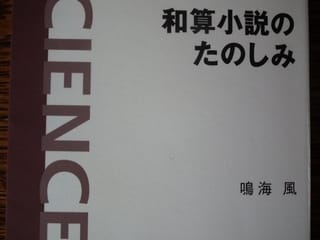 岩波書店が「岩波科学ライブラリー」を創刊したのは今から19年前の1993年のことだったそうで、昨年の11月には150冊を刊行するまでに至っています。
岩波書店が「岩波科学ライブラリー」を創刊したのは今から19年前の1993年のことだったそうで、昨年の11月には150冊を刊行するまでに至っています。
恥ずかしながら私はこのシリーズの存在を知りまんでしたが、その中の1冊「受験算数」を購入た際に、偶然その存在を知り、そのラインナップを眺めると、
例えば
「チンパンジーは何故エイズにならないか」・「はみだし幾何学」・「量子力学を見る」・「月下美人はなぜ夜咲くのか」・「愛は脳を活性化する」・「江戸の数学文化」など興味をソソラレル題名が並びます。要するに数学・天体・物理・植物・医学などの自然科学を中心とした、120ページ程度の読み物シリーズなのです。そこで、これはと思う数学関係を3冊読んでみました。「受験算数」以外には「オイラー、リーマン、ラマヌジャン」と「和算小説のたのしみ」です。
「和算小説のたのしみ」の著者鳴海風の話は一度聞いたことがありました。確か「美しき魔方陣」出版を記念して、池袋「ジュンク堂」の喫茶室で開かれた小さな集いでした。そのとき、パソコンを持ち込みパソコンソフト「パワー・ポイント」を使ってのヴィジュアルで丁寧な説明が印象に残りました。和算家、すなわち江戸時代の数学家を主人公にした小説を数編創作していることもその時に知りました。
江戸時代に独自の発達を遂げた日本の数学「和算」。いまこれを題材にした歴史・時代小説がブームです。和算の持つ数学的な専門性とパズル的遊戯性が共存し、和算家たちの意外な活躍が、一味違う楽しみを教えてくれるからでしょう。「天地明察」(著:冲方丁)もその範疇の一冊。
「和算・・・」では29冊もの和算小説が紹介されていますが、その中で鳴海風の一押しが小野寺公二著「算額武士道」と遠藤寛子著「算法少女」です。「算法少女」は読んだ事がありました。更に続けて同じ遠藤著「きりしたん算用記」を絶賛していました。何故日本に和算が生まれたのか。和算のルーツは謎に包まれた部分ですが、鳴海は初期の和算家に対して宣教師がもたらした西洋数学の影響を大と考え、「きりしたん算用記」にそれに触れる部分がある事に驚きかつ称賛したのです。
鳴海自身「円周率を計算した男」で第16回「歴史文学章」を受賞しています。「和算」、敬して遠ざかっていた世界ですが、「算学武士道」や「円周率を計算した男」を読んでみたくなる様な「和算小説の楽しみ」でした。
2月某日、六本木ヒルズ「TOHOシネマズ」で無修正版「ドラゴン・タトゥーの女」を観て来ました。
原作はスウェーデン作家スティーグ・ラーソンによる推理小説『ミレニアム』。第Ⅰ部「ドラゴン・タトゥーの女」、第Ⅱ部「火と戯れる女」、第Ⅲ部「眠れる女と狂卓の騎士」と続く三部作で、地元スウェーデンで290万部、全世界で800万部を売り上げたと言う超ベストセラー(現在はそれ以上に売り上げが伸びていることでしょう)。著者ラーソンは発売の大成功を見ることなく、2004年に心筋梗塞で急死するなど大きな話題となっていました。
この映画はハリウッド作品ですが、ほぼ同名の作品がスウェーデンでも制作されていて、私はそれをテレビを通じて鑑賞していましたが、4回に分けて半年に1回くらいの割合の放映だったので、作品のインパクトは弱く、印象も散漫になっていました。原作は非常に面白いミステリーでしたから、その良さをじっくり味わいたいと思っていたところ、再度の映画化で、それも180分以上の超大作と知り、期待を込めて映画鑑賞に出掛けたのでした。期待を裏切らない出来栄えに仕上がっていました。 粗筋はこうです。
粗筋はこうです。
『本物語の主人公にして雑誌「ミレニアム」の発行責任者のミカエル・ブルムクヴィストは名誉棄損の有罪判決を下され「ミレニアム」から離れることを決めます。その頃、大企業グループの前会長ヘンリック・ヴァンゲルはミカエルの身元調査を開始し、彼の調査能力を調べ上げていました。調査を担当したのは、背中にドラゴンのタトゥを入れた、少年と見紛うような小柄な女性。もう一人の主人公リスベット・サランデル。
ミカエルの調査能力を信じた大企業の元会長は、36年前に一族が住む島から忽然と姿を消した兄の孫娘ハリエット・ヴァンゲルの捜索を依頼します。失踪当日、島と本島を結ぶ唯一の連絡網の陸橋は交通事故の為閉鎖されていたため、島は密室に相当する状況でした。
依頼を受けて捜査を開始するミカエルは命を狙われる危機に遭遇します。情報処理能力の高いサランデラを助手に依頼し、真相究明に努める二人の前に、連続殺人事件が姿を表し始め、真犯人に辿りつくと同時に、ハリエット失踪の真相も明らかになります』(写真右上:早川書房版「ミレニアム」)
と書いてくると、この作品の持つスリルとサスペンスがまるで浮かびあがりませんが、久し振りに興奮しながら読んだミステリーでした。
その作品の映画化。複雑多岐にわたる人間関係の物語を映画は巧みに処理し、見応えにある作品に仕上がっていました。180分があっと言う間に過ぎ去りました。スウェーデン版は第Ⅱ部・第Ⅲ部とも9月に日本上陸の様です。
我が富士前町会に隣接する神明西町会内の組織で、主としてお祭りを担当する組織は「宮元」と名乗っています。その宮元は毎年「天祖神社」境内を利用して宮元祭りを開催しています。この宮元祭り、今回で第8回を迎えるそうですが、天祖神社の直ぐそばに住んでいる私たちは、第3回から毎年、その祭りに出掛けています。 数年前に遡りますが、向丘高校の卒業生で3年生の時に数学を教えた事のあるT君とその妻さんが、宮元の一員として嬉々として活躍している姿に出会いビックリしました。その縁もあり、私は有志として宮元の会員の仲間入りをさせてもらい、Tシャツも頂きました。第4回・第5回の宮元祭りでは、「芋煮」の調理・販売の手伝いをさせて貰いましたが、今年は本部の仕事を依頼され、主として食券販売の手伝いをしました。(写真:朝8時。準備段階の神社境内)
数年前に遡りますが、向丘高校の卒業生で3年生の時に数学を教えた事のあるT君とその妻さんが、宮元の一員として嬉々として活躍している姿に出会いビックリしました。その縁もあり、私は有志として宮元の会員の仲間入りをさせてもらい、Tシャツも頂きました。第4回・第5回の宮元祭りでは、「芋煮」の調理・販売の手伝いをさせて貰いましたが、今年は本部の仕事を依頼され、主として食券販売の手伝いをしました。(写真:朝8時。準備段階の神社境内)
 4月22日(日)に行われた宮元祭りの内容ですが、参詣道沿いに、大鍋での芋煮・カレーライス・焼きそば・綿あめ・フランクフルトなどの模擬店には人の列が出来ます。消防団の消火訓練・フレーベル合唱団の合唱などのイベントも実施され、金魚すくいや輪投げなどのお店には子供達が殺到します。更には安くて良いものが手に入るバザーが大人気です。文京ケーブルテレビからの取材もありました。(写真:取材を受ける実行委員長)
4月22日(日)に行われた宮元祭りの内容ですが、参詣道沿いに、大鍋での芋煮・カレーライス・焼きそば・綿あめ・フランクフルトなどの模擬店には人の列が出来ます。消防団の消火訓練・フレーベル合唱団の合唱などのイベントも実施され、金魚すくいや輪投げなどのお店には子供達が殺到します。更には安くて良いものが手に入るバザーが大人気です。文京ケーブルテレビからの取材もありました。(写真:取材を受ける実行委員長)
(写真:大鍋の芋煮)
(写真:バザー) お食事処も設営され、多くの人々がここで食事を摂っていました。若手が中心に活躍する宮元祭りは、地元の人々からこの日の来るのを待たれるほどの人気です。やや肌寒い一日でしたが、雨に降られることも無く、一昨年と同じくらい人出で賑わっていました。(写真:食事処)
お食事処も設営され、多くの人々がここで食事を摂っていました。若手が中心に活躍する宮元祭りは、地元の人々からこの日の来るのを待たれるほどの人気です。やや肌寒い一日でしたが、雨に降られることも無く、一昨年と同じくらい人出で賑わっていました。(写真:食事処)
後片付け終了後の打ち上げに私も参加しました。力仕事で一緒に汗を流し、お酒を酌み交わすと仲間の一員に加われた様な気になりました。
妙正寺川は杉並区妙正寺公園内の妙正寺池を源流として、以前は新宿区下落合で神田川に合流していましたが、現在は下落合から暗渠となり、豊島区高田橋付近で神田川に合流しています。神田川の支流の一つ(他の一つは善福寺川)で全長9.7Kmの比較的短い河川です。
1月25日のブログに「高井戸から神田川を下る」と題した記事で、高井戸から高田橋を経由し仲之橋まで歩んだと書きました。次回の川巡りは神田川を更に隅田川まで下る予定でしたが、計画を変更し、後楽橋から高田橋を経由して妙正寺川を遡りました。
4月20日(金)、福寿会健脚3人組で、東京ドームボウリングセンターでボウリングを楽しみ、昼食後散策開始。まずは水道橋駅付近の後楽橋から神田川を遡ります。江戸川橋から先の上流は、春は桜が川に覆い被さるように咲き、右側(川左岸)関口台地からは多くの急坂が神田川方面に下ります。椿山荘「冠木(かぶらぎ)門」からは椿山荘庭園へ昇れます。今回は芭蕉庵に立ち寄りました。池をめぐらせ、こじんまりした庭園風の庵(いおり)跡地に「古る池や・・・」の句碑がありました。 高田橋で神田川を離れ、新目白通り左側を通りを進みます。右側に比べ歩道の幅が広く、樹木などが多数植えられ、明らかに反対側と造りが違います。不思議がっていましたが、KUさんが「この下が妙正寺川の暗渠だ」と気が付きました。3人は6個の眼。一人散歩時より多くに事に気が付きます。(写真:高田橋付近の流れ。右端が妙正寺川の暗渠開始部分)
高田橋で神田川を離れ、新目白通り左側を通りを進みます。右側に比べ歩道の幅が広く、樹木などが多数植えられ、明らかに反対側と造りが違います。不思議がっていましたが、KUさんが「この下が妙正寺川の暗渠だ」と気が付きました。3人は6個の眼。一人散歩時より多くに事に気が付きます。(写真:高田橋付近の流れ。右端が妙正寺川の暗渠開始部分) 西武新宿線下落合駅付近で暗渠は終了し、妙正寺川は姿を表し、源流まで暗渠なしで流れます。今回ここから、西武新宿線「新井薬師駅」まで歩きました。(写真:妙正寺川は所々西武新新宿線と並行しています)
西武新宿線下落合駅付近で暗渠は終了し、妙正寺川は姿を表し、源流まで暗渠なしで流れます。今回ここから、西武新宿線「新井薬師駅」まで歩きました。(写真:妙正寺川は所々西武新新宿線と並行しています)
その中でも印象的だっ2ヶ所を紹介します。 ①「哲学堂公園」内の一葉桜。
①「哲学堂公園」内の一葉桜。
東洋大学の創始者井上円了が「四聖堂」を建設したのがこの公園のはじまりで、四聖堂は当初哲学堂と呼ばれていたそうです。それがそのまま公園の名前になった、相当広い公園の様です。今回は川沿いのみを歩きましたからその全容は分かりませんが、そこに「一葉桜」が見事な白い花を咲かせていました。白色の八重桜といった趣でした。
(写真:哲学堂公園内に咲く一葉桜)
②妙正寺公園調整池
妙正寺川を隔てて哲学堂公園の反対側に妙正寺川公園があり、この公園は妙正寺川第一調整池とも命名され、その下に第二調整池があります。右岸側の岸の高さを左岸側より低くして造っておくことにより、洪水時などに大量の水を調節池側に導くシステムです。神田川・妙正寺川いずれも洪水対策として、川のバイパスや調節池が多く造られている事を知ります。
今回は4時を回ったところで散策を切り上げ、更なる上流へは近々に新井薬師駅から妙正寺池を目指します。









