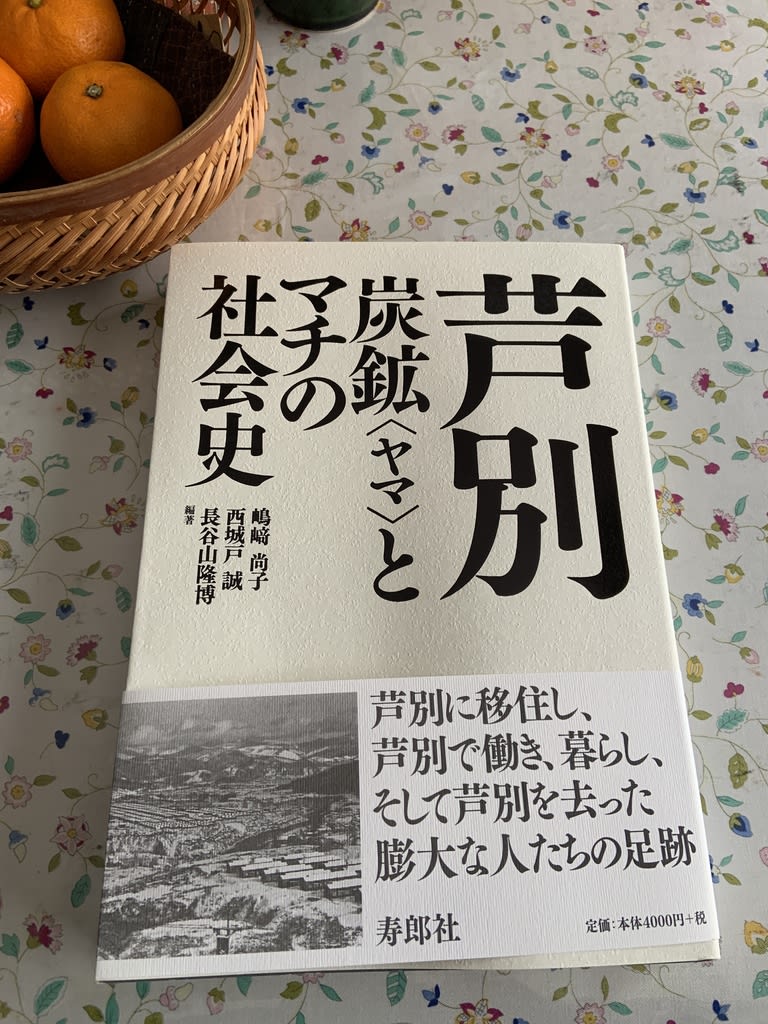メディアは石破首相の正論、一般論を回りくどく話す独特の言い回しを〝翻訳〟して報道し、首相が即座に発言の意図を説明することが繰り返されている。
「大連立」も「予算案否決」も「衆院解散」も少数与党であればあり得るわけで、メディアは当たり前のことで少し騒ぎ過ぎではないかと思う。
だからどうだというのだろうか。
むしろ定まらぬ政治姿勢を問うて欲しい。
1月20日にアメリカのトランプ政権がスタートする。
米中新冷戦、北朝鮮とロシアの軍事同盟、韓国の政情不安。
周辺国との安全保障上のリスクは格段に高まっている。
トランプの顔色を覗い、これまでのような隷属外交を続ければ日本は益々、国益を棄損するだろう。
〝トランプリスク〟に日本は内政、外交、防衛でどのような処方箋を用意しているのか、もっと知りたいことこそ報道して欲しい。
取材が手抜きなのか、マンパワー不足なのか、〝斜陽〟の新聞業界の衰退が心配になる。
石破首相が政治の師と仰ぐ田中角栄にあやかって、ライフワークの〝地方創生〟について、「令和版列島改造」ということも言い始めた。
しかし、これもさっぱり具体的な内容が伝わってこない。
看板政策の防災庁の設置と連動させてのことだろうけれど、省庁機能の地方移転は昔から言われてきて、確か文化庁の一部を京都に移したくらいしか記憶に無い。
かなり難しい問題なわけで何か算段はあるのだろうか。
中央省庁の職員が住居を東京と地方に持って、往来しながら勤務するという構想は唐突というか、奇想天外というか現実味はまるで無い。
このままでは「令和版列島改造」も〝花火〟で終わるのではないか。
作家の高村薫氏ではないが、「石破発言」は、この先の政治のかじ取りを託すにはあまりに軽い。そしてメディアの突っ込みも弱い。
石破首相は施政方針演説の冒頭で石橋湛山を引いたが、政治の師と仰ぐ田中角栄は湛山の親中国路線の強い影響を受けて日中国交回復という大事業を成し遂げた。
中国に行く直前、湛山宅を訪問し、病床の湛山は車椅子で玄関まで出迎え、「周恩来首相によろしく」と伝えたという。
湛山は日米同盟を基本としながらも一定の距離感を持って、GHQに唯一楯突いた政治家だったという。
石破首相が石橋湛山と田中角栄に政治家のあるべき姿を見ていると言うのならば「ひとりでも行く」という単騎の志と地べたに這いつくばって弱い人々の願いを救い上げる泥臭さい政治手法があってこそのものではないか。
石破首相にその気概は感じない。
今年はアメリカを震源とする世界情勢の大地殻変動が起きることは明らかで、その中で国益をどう守るのか、石破首相は政治の師に見習って肝の据わったところを見せて欲しいものだ。