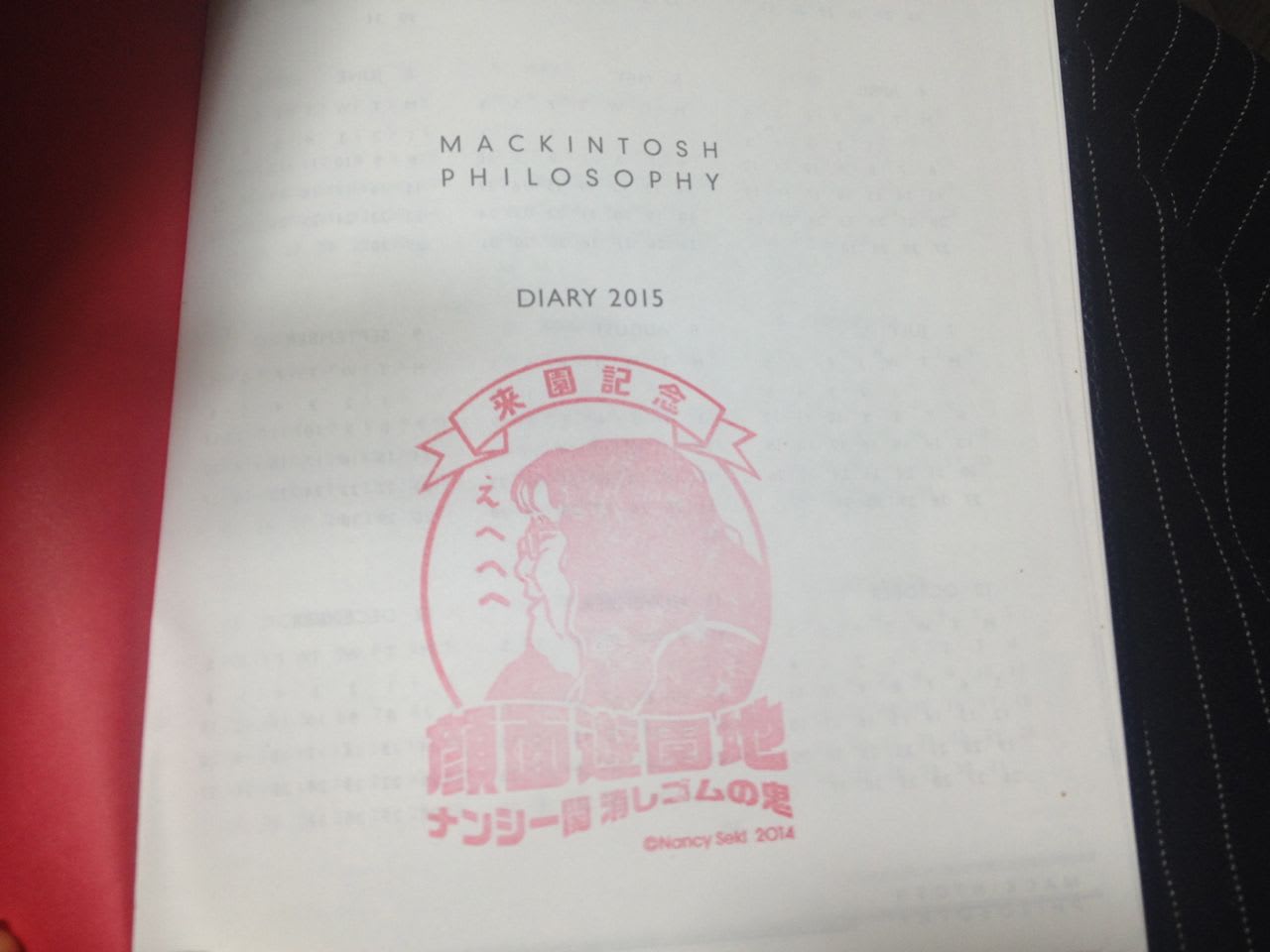これから書くことは、原発の事故処理に対して、誰しもが感じている当たり前なことだろうけれども、その「感じている」ということをもって、ことさらに原発事故のその後について口にする人が少なくなった気がするので、あえて書こうと思う。あまりにも当たり前過ぎて退屈だったら申し訳ありません。ちょっと長くなってしまったけど、よろしかったら読んで下さい。
しばらく前の新聞に福島第一原発への地下水流入を防ぐための凍土遮蔽壁の本格工事が始まるという記事が載っていて、昨日、その工事が余り上手くいってないことが報じられた。そもそも、この工事にはさまざまな懸念材料が提示されていたが、実際にそれが露呈して来ている。2010年に報道関係の仕事を辞めてからは、細かくこうした情報を追うことをしていない。これだけ大きな事故でありながら、これが日本の歴史上においても特記すべき大事と認識していながら、こうした事故後の状況については漠然としか把握していなかったのが正直な所だ。しかし、この凍土壁に関する記事を久しぶりに見出しだけでなくちゃんと読んでみたら、涙が出そうになった。あまりの八方ふさがりに呆然とした。
私は「事故前から原発はやめるべきだと思っている」という言葉を免罪符にしていたな、と思った。「脱原発」と「事故処理」は同じ土俵で考えてはいけないことも頭ではわかっている。しかし実際には「原発はやめるしかない」と思っていることを理由に、事故の現状をちゃんと把握することを怠り、無意識に目を塞いでいた。脱原発を考える人はすべて事故のその後の状況をちゃんと追っかけてるというわけではないのである。私みたいな人も多いと思う。
そして久々に、この凍土壁の記事を読んでみて、そして、あまりの八方ふさがりに呆然となり、その呆然こそが今の現実なのだということを思い知らされた。
以前から凍土遮蔽壁に対して提示されていた懸念は現実になりかけている。そうした懸念は当然である。しかし、他によい方法があるのか?批判は簡単だが、解決策を見つけることは大変だ。いや、まじめに検討すればいづれ見つかるかもしれない。しかし、それにどのくらいの時間がかかるのだろう。また、このまま放置していたとしたら、いつごろどんなことが起こる可能性があるのか…?議論している間に地下水が入り込んでしまうことはないのか…など、二次被害への想像が頭をもたげる。時間との闘いに背中がジリジリするような感覚に陥る。作業員には被爆の危険がつきまとい、また、そんな作業員の作業にも、人間でやるがゆえのヒューマンエラーは当然つきまとう。絶対大丈夫なんてことはない。そのとき、自分の住む東京は大丈夫なのか? いや日本は大丈夫なのか?
原発処理作業は現代の戦場であることは多くの人が指摘している。相手が他国の戦闘員やテロリストではなく、事故った原発というだけ。そんな戦場で被爆の恐怖と向き合いながら汗まみれで作業を行う人たちのことを考えると、また背中がジリジリする。追い立てられるように続く処理作業はやめるわけにはいかない。少しでも気を抜けば、日本は本当に大変なことになる可能性がある。私たち多くの国民の平安は、彼ら作業員の緊張した肩にかかっている。そんなプレッシャーに満ちた仕事で、絶対ミスをするなとは酷な話。しかし、本当にミスがあっては困るのだ。はやく作業員たちを楽にしてあげて欲しい。しかし、戦争なら降伏することもできるが、原発はそれさえも許してはくれないのだ。作業員の緊張は、世代を超えて、作業が続く限り永遠に続く。
こんなことに誰がしたのだ。こんなものを誰が作ったのだ。なぜ今の世の中はこんなジレンマのようなエネルギーに支えられているのだ…。今、自分が電灯の下でこの文章を書いていることさえじれったい。なのに、なぜ政府や財界は原発再稼働を意図し、さらに海外に輸出までしようとするのか。
そこまでの緊張と苦労を人々に強いている原発をさらに増やしてまで彼らが守ろうとしているのは何なのか? それは決して日本経済などではないと私は思う。彼らはそう主張するかもしれないが、そんな方法は前記したようなジレンマだらけのこじれた世の中を延命するだけの、それも焼け石に水でしかない。
彼らは再生可能エネルギーはなかなかモノにはならないという。開発にはコストがかかりすぎると言う。しかし、ITの世界で2000年以前にはgoogleがここまでの存在になるなど多くの人が予想せず、facebookもtwitterも存在していなかったのである。なのになぜ、古い原発というエネルギーにしがみつき、これだけ巨大な恐怖を増やさねばならないのか…。私にとってはこのことこそが、現時点での世界最大のミステリーだ。東京五輪のための国立競技場たった一つに当初3000億円もの税金を投入しようとしていたのである。そうした予算を日本のエネルギーシステム転換のために使えないものなのか…。
原発の事故処理に関しては、緊張の糸を切らさないように、もちろん議論の糸も切らさないように、地道にやっていくしかないのだろう。絶対に投げやりになってはいけない。今回の凍土壁問題で見えて来た問題の数々に対しても、投げやりにならず真面目に答えていかねばならない。時間との闘いなのであれば、そこは天秤にかけるしか無い。こちらのほうがベターと判断出来る範囲で議論を尽くすしか無い。それは背中がガチガチになるような大変なことだろうし、私は静かな部屋でこうしてパソコンに向かっているだけだから、言えることかもしれない。けれど、黙っていては、何も変わらない。
もうひとつ言うと、解決策に対してはお金にいとめはつけてはいけない。もちろん解決策の選択は慎重に行わねばならないが、お金惜しさに、挑戦出来ないということがあってもいけない。
新聞報道では、凍土壁の失敗で300億円以上が無駄になる…といっていたが、原発処理という、地球環境にさえ影響しかねない、失敗を許されない作業には、1兆円かけたとてそれは無駄とはいわない。試行錯誤で税金が無駄になったところで、それが真摯な試行錯誤の上の無駄であれば、しょうがないはずだ。
いまだに、原発反対派の中にも、税金の無駄とか金勘定で政策の適否を語る人がいるが、もはやこの原発事故の問題はお金で語れるような問題ではないことを日本国民はもっときちんと認識すべきだ。もし、放射能の封じ込めに失敗したとしたら、日本は世界中の国から白い目で見られるはずだから。
荒唐無稽な人知を超えた状況に出会うと、人は思考停止に陥り、無意識に目を背ける。現在の日本の状況がまさにそれだ。多くの弱い人々は真正面から原発事故の現状を見ることができない。
より問題が根深くない方角を探して、最も大きな問題からは目を背けながら、目の前の大問題に蓋をしてきたのがこの3年間だ。
荒唐無稽な状況に舞い上がって現実を見失い、神頼みとか神風とかいって失敗したのが第二次世界大戦だということをもう忘れたのだろうか。自分の目の前にあるものをきちんと見つめ、見誤らないようにして、一つ一つ、自分の把握出来ることから処理して行くほか、私たち人間になすすべはない。無理なものは無理と認識することも必要なこと。
結局、現実に対処できるのは「真面目に、地道に、真剣に」ということしかないということを原発事故という現実によって教えられた。
妄想が悩みを深めるように、脳内でうごめく印象論や感情論、立場論に引きずられると、現実との矛盾がどんどん積み上がり、ふくれあがっていく。そうしないためにも、目の前で起こっている具体的な事象に具体的に対応していける真面目さが必要だ。未来への一筋の光を見るためには、目の前の現実を見るしかない。
なのになのに、目の前には、「シュウダンテキジエイケン」の問題やら「TPP」やら、「東京オリンピック」など、よく分からない問題が山積みになっている。原発事故という大問題だけでも手いっぱいなのに…。
本当に涙目になりそうだ。
このところ漠然と感じる絶望感は、人間はこれら全てをうまく解決するほど万能ではないことからくる虚脱…。
もう破滅への道を落ちて行きたいという誘惑が背後から忍び寄っているのが分かる。けれど、その誘惑に負けた時、その向こうに待っているのは、多分、薬物依存のあとの状況にも似た深い後悔だろうとも思う。破滅への誘惑というのはそういうものではないか…。しかし、その後悔の大きさは体験した人にしか分からない。だから今、多くの人がその絶望感(絶望だと意識していないだろうが)の虜になりそうになっている。
そして、そんな誘惑が現政権を支持する多くの人の無意識の領域を占めているのだと思う。