「グローバリズムは終わった」
この言葉、FACEBOOKとかツイッターでつぶやいてみました。
ネットで配信してるラジオデイズの平川克美、内田樹両氏の
「はなし半分」10月号がめちゃ めちゃ面白かったんですが、
そこで、「遠い目をして『グローバリ ズムって終わったねっ』て
言ってると感染力凄いんだよね」と言っ てたので、
とりあえず、パソコンに向かって遠い目をしてつぶやいてみました。
その番組では「もう鎖国かな」とも言ってて、
私も出島プロジェク トって名のってることだし、
かっこつきの「鎖国」ってどういう形 があり得るか
考えてみようかなとも思ったりしました。
交流しながら 鎖国する方法。
例えば、隈研吾の言う、建 築における「柔らかいスクリーン」、
格子とか障子みたいな 、仕切ってんだけど、つながってるみたいな方法が
ないだろうかと思ったりしてます。
日本のあり方ってそういうインターフェイスのあいまいさにある気もします。
たとえば貿易。海外のもの買うにしても、日本のモノ売るときも、
関税高くてもどうしても欲しい人だけ
売ったり買ったりすればいいんじゃないんですかねえ・・。
そんなに言うなら売っちゃるわ、というやつです。
輸入輸出が減った分は国内需要で。
そのかわり、旅行に来てくれはるのは大歓迎。
もちろんこの発言は、ふつうの経済理論とか無視してます。
ただ、内田氏も言ってますが、経済学って、人間の消費行動の中の
数値に表れない非合理的な部分は織り込んでないので、
ある意味、かなり不完全なんじゃないでしょうか。
それに、スタバだのマックだのが無くなったら、
多分一時期は混乱するんでしょうけど、
そこに地元のカフェとかが入っても、今の日本なら、
かなりオシャレで快適な空間を提供できると思うんですけどね。
大資本じゃないいろんなお店の顔が見れて楽しそうです。
まあ、多国籍企業がロビー活動をして、そんな日本をぶっつぶせ、
戦争しかけチャレなんてことになるっていうなら、
ちょっとまた方法を考えねばなりませんが…。
内田氏は、大政奉還、廃県置藩とも言ってましたが、
江戸の仕組みに学ぶところはありそうです。
私も以前、半分本気半分遊びで「水戸黄門計画」water door yellow gate plan
略してwater gate (嘘)というノートを作っていたことがあります。
水戸黄門って、毎回、その土地の代表的な産業をになう庄屋とか大店が出て来て、
そこでの贈収賄がテーマになります。
つまり、各藩の伝統工芸とか産業とかを見て回ってんですよね黄門様って。
水戸黄門って、そんな各地の産業紹介番組ともいえるなあと常々思っていたわけです。
そこで、わたしも水戸黄門よろしくとりあえず、格安深夜バスを駆使して
各地の手仕事や産業を見に行こうかと思ったのが水戸黄門計画でした。
とにかく地方自治体が中央政府にぶら下がらないでやっていける方法を
見つけねばとの思いです。
一時期は、地方交付税のひも付きをなくし、一括交付にすることで
ある程度、中央集権政府からのぶら下がり体質は解消できるかとも思いましたが、
ショック療法としての廃県置藩もいいかもですね。
グローバリズムの時代も終わろうとしています(キリッ。
「鎖国」が象徴する新しい時代の、新しいインターフェイスとはどんなものか
私にもまだわかっていません。「出島プロジェクト」の出島はまさしく、
そのインターフェイスのつもりで名付けたのですが、
それがどういう機能を果たすものかは、
実のところ自分でもまだよくわかっていないのです。
「出島」としたのは直感です。
ここらへんで本気出して、現代の「出島」とは何かを考えねばなりません。
こんな話をお酒でも飲みながらしたいもんです。
ラジオデイズ たぶん月刊 内田樹・平川克美「はなし半分」10月号
http://www.radiodays.jp/item/show/200808
facebookにも短いバージョン投稿したんですが、ブログでもだめ押ししときます。
にしても、facebookに書くときって話口調にするせいか、
ちょっと「ヒロシです」みたいになってしまいますね。
やはり、メディアによる違いて文章にもでるんだなあ・・・。
あと、なぜかフォントサイズが小さいところがあります。なぜだろ?直らない。












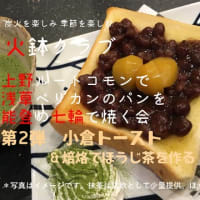



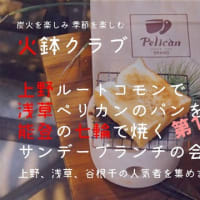



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます