夕方、昨年末浅草にできた日本中の物産を集めた商業施設に立ち寄った。今夜は雪が予想されたからか、まったく混雑しておらず、余裕を持って見てまわれた。
東京五輪にむけた観光立国ブームとか、地域振興とか、クールジャパンとか、そんなこんなで、ここ数年の間にこうした商業施設がいくつも誕生したが、五輪までまだ4年を残して、こうした施設も曲がり角に来ていると感じる…。そんな私は間違ってんだろうか??
上記で「地域振興」という言葉を使ったが、こうした商業施設が地域振興に寄与することはあるのか…。以前は私もこうした方法はありかと思っていたのだが、結局、売れるのはそのテナントに入っている店だけであり、その店はすでに地方で成功していて、極端なことを言えば、これ以上宣伝せずともやっていける店ばかりである。舶来ものと老舗ばかりを集めたテパ地下となんら変わらない。地方物産という言葉に付加価値があり、消費者に訴求するから、新たな商業施設の一形態として採用されているにすぎないと思う。
それに、全国からちょびちょび集めたこうしたセレクトショップは、いまや不動の人気を誇る北海道物産展のような爆発力とインパクトに欠ける。イベントとして短期決戦という緊張感も無い。
さらに、観光地という一見の客の多い立地では、それぞれの商品も漠然とした印象しか残せないのではないだろうか。
さらに根源的なことを言えば、食べ物は地産地消がいいと言いながら、都会までパッケージングして(時には添加物を付加して)、送料かけて運んで来ているという矛盾…。あまりのテナント料の高さに、それって誰が潤ってんだ…とも思う。聞けば、店舗によっては100万円単位のテナント料になるらしい。それが商品価格に乗せられていると思うとクラクラする。もちろん、デパートやスーパーとて同じことだが、それも含めて、流通というものが生んだ矛盾について考えさせられる。
地方のものがその地方でちゃんと消費されれば、地方の経済もそれなりに廻るはずで、地域振興など必要ない。そうならないのは、地方に進出した大企業の商品が地方の需要を奪ったからだ。全国展開する大手スーパーマーケットに並ぶ野菜は、地元産のものも無くはないが、多くは、よその大規模生産地からトラックで運ばれて来たものだ。
大企業が作るバラエティと利便性に富んだ加工食品の魅力に抗えなかったのも事実だ。今ごろになって、地方の小さな菓子メーカーの素朴なお菓子に注目したりしているが、もはやここまで大量生産大量消費の仕組みが盤石になっては焼け石に水の感もある。
地方の人々が地元のものを買わなくなったせいで、都会で売らないとやっていけなくなっているのが今だ。そして、都会の商業ビルのテナントに入り、今度は高いテナント料をとられている。もちろん、都会で宣伝出来たことで成功する店もあるだろう。けれど、それが地元にトリクルダウンをおこすほどの大成功に繋がることはほとんどない(と思う)。結局は選ばれしものだけが潤う。
地方再生の一番の近道は、地方の人達が地元の良いものを自分たちで買うことだ。しかし、中央にいろんな形で吸い上げられ、収入の減った地方の人々には、地元で伝統的な手法で作られる手間のかかった商品は高嶺の花となっている。
でも、地方の年寄りって、年金溜め込んでたりするんだよね。そういうお年寄りに言いたい。みなさんが率先して地元の現役世代の作る生産物を買うべきです。年寄りよ大志を抱け。墓には持って行けないお金。最後に地元のために使ってはいかがでしょう。
地方の小さな商店街がシャッター商店街となり、車の運転ができないお年寄りが買物難民になっているとも聞きます。やはりここは地元密着の個人商店が集まった、歩いて行けて、御用聞きにも来てくれる地元商店街の新たな形が模索されるべきなんじゃないでしょうかね。
とはいえ、東京で地方のいろんな食べ物や工芸品を手に取れるのは嬉しいことでもある。テナントのお店の方が潤うなら、これもこれでいいと思う。言いたいのは、くれぐれもそれがその地方全体の再生につながるとか考えない方がいいということで、そこに補助金とか出さないほうがいいんじゃないかってことだ。みなさんはどう思います?












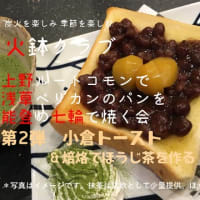



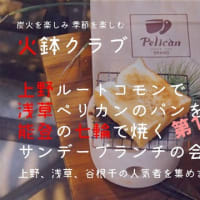



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます