前回の最後に、「ビデオニュースで、ジャーナリストの高野孟氏が語った『政治とカネの問題の本質』を聞くに至って、菅直人との会談で『小沢一郎が求めたポストは何か』を問う事もある意味、意味があるのではないかと思えてきた」と書いた。
これはどういう意味か。
簡単に言うと、小沢一郎にはある意味、「政治とカネ」の問題があるのかもしれないなあと思ったということだ。
しかし、それはマスメディアやそれを信じる人たちが言う西松建設からのカネがおかしいとか、狭義の「政治とカネ」の問題ではない。検察審査会に持ち込まれた政治資金収支報告書に関する「政治とカネ」の問題については、裁判をしたところで有罪になる事はほぼないだろうし、これ以上問うような事ではないと思う。
高野氏がビデオニュースで「政治とカネの問題の本質」として語ったのは、個別具体的な政治とカネの問題ではなく、政治文化としてのカネの問題だ。問題視されたのは、お金の入り口の問題というより、出口、つまり使い道の問題だ。もちろん私腹を肥やすという類いのものではない。
高野氏は、小沢の“剛腕”と言われるものの実態は、自らの資金や、幹事長職を獲って牛耳った政党助成金を、組織対策費として使い、物事を動かす政治手法のことだという。平たく言えば、カネを使って、仲間=数を集める手法だ。「政治闘争とは結局はカネと人事だ」と考え実行するような政治文化。それこそが、小沢氏の“剛腕”の正体だというのだ。
菅直人が公開討論会で
「小沢さんの政治のあり方というのは、どちらかといえば、資金的な強さ、仲間の数の多さ、そういうお金と数の原理が色濃くあるのは私だけが感じているのではないのではないでしょうか」と語っていたが、まさにそういう政治手法のことだ。
こうした政治文化は、自民党政権時代の古い政治文化と言える。
小沢の場合、違法性があるわけではない。また、私腹を肥やすカネではなく、政治に必要な資金であったりする。
しかし、資金を渡すことで人心までも掌握するという旧時代の手法を、政権交代した今、再び容認するのか?
そういわれると、確かに、容認していいのだろうか・・という気もしてくるのだ。
反小沢の急先鋒とされる仙谷由人は、高野氏によれば、カネを使わずに人脈を広げ、手練手管を弄せる、小沢に対抗できうる唯一の人材だと言う。彼の物事の理解力や基礎学力の高さが人望に繋がっているらしい。
高野氏は、今回の戦いは、菅vs小沢ではなく、実質的には、仙石vs小沢だと語るが、その本質は、権力闘争に関するこうした2つの異なる政治文化のぶつかり合いだと分析する。
政策や理念はどうあれ、カネを使って数を集める旧自民党的体質の政治家は、新しい時代の幕開けにはふさわしくないという考え方も確かにある。
じゃあ、菅&仙石に一票と思いそうになる。
しかし、私は、迷いなくそうすることもできない。
政策についての議論はおいとくとして、
問題とされる小沢の「政治文化」の中にも、こうした「カネの使い方」とはまた違った、捨てがたい何かがあるような気がするからだ。
そういえば、高野氏は「陸山会事件の本質」として、こんなことを言っていた。
『小沢一郎は、巨大な政治資金を集めて、何十人もの秘書を抱え、それを選挙プロフェッショナルとして派遣している。彼らを住まわせるためのマンションも必要だ。彼がそこまでするのは、民主党が坊ちゃん嬢ちゃんばかりだから、オレがプロとしてやってやってるという思いから。
しかし、近代政党なんだったら、選挙のプロを党の中で育てて、党のシステムとしてやっていかないと本当の強い政党にはならない。
しかし、小沢は、おまえらバカで政治を知らないからオレがやってやってんだという考え。違法だとかどうとか関係ない、それが陸山会事件の本質だ。』
高野氏は、「近代政党なら選挙のプロは党のシステムとして育成を」という。
しかし小沢のやり方は、いわゆる「書生」から始めるってことだ。
別の言い方すれば「徒弟制度」。
そして、彼らが苦労して学ぶ政治手法は古くさい。
さらに、こうしたやり方は自分の主人に対する変な忠誠を生み、物事の本質から目をそらさせるという一面があるとも思う。
しかし一方で思うのは、「選挙のプロを党の中で育てて、党のシステムとしてやっていく」という言葉からは、いわゆる「コーチング」みたいな米国的な合理的方法論というか、マニュアル化され身体性を伴わない学習と実践といおうか、悩みなく一足飛びに何かを獲得しようとする「今時の学びの態度」をイメージしてしまうのだ(もちろん高野氏は、こんなやわなシステム化を考えているわけではないと思う。私の勝手なイメージだ)。
私が小沢一郎に感じる捨てがたい部分というのは、多分、職人技につながるような「地道さ」とか「めんどくささ」みたいなものだ。一見、理不尽な師弟関係から習得され経験により研ぎすまされる日本的な「習熟」。
小沢一郎自身が実際にそんなものを目指しているかは知らないが、あのたたずまいにはそう感じさせる何かがある。
一方、高野氏は、こうした「オマエらに言っても分からんから、オレが全部やる」的なやり方や「結局はカネと人事だ」という考え方は小沢独特の「人間不信」と「ニヒリズム」から来ているのではないかという。
確かに、そんな気がする。
「地道さ」と「ニヒリズム」というアンビバレント。
その2つの間を繋いでいるのは、地道な努力しないで上手く世の中を切り抜けようとする狡いヤツや腹をくくっていないヤツに対する不信感なのではないのか。そして、そういうヤツに限って、カネに引っかかるのではないか。
かつて、小沢一郎に真っ向から政策を問うたものはいるのだろうか。
小沢一郎からカネを渡されて、私はいりませんと言ったヤツはいたのだろうか。
本当に小沢一郎が「ニヒリズム」の人なのだとしたら、彼は、そうした現代の風潮や世の中に復讐するつもりでカネを渡したのではないかとさえ思えるのだ。それは買いかぶりすぎか?
小沢一郎は、日本改造計画で日本の将来ビジョンを示すという仕事をした。
そして、現在もそのビジョンは改訂されつづけていると思う。
そんな仕事をする人間が「ニヒリズム」に陥るとしたら、なにが彼をそうさせたのかを問う中に、高度成長以降日本が陥った病とは何かを考える鍵があるような気がする。
なんか凄い話になっちゃったよ・・・。
ところで、この頃様々なところから、小沢を西郷隆盛に、菅を高杉晋作になぞらえる声が聞こえてくる。
しかし、小沢自身が尊敬する人物に挙げるのは大久保利通だ。
明治維新を境に、過去にとどまった西郷と、未来に踏み出した大久保。
多分、彼の中にはこの二人に象徴されるような何かが、アンビバレントに存在しているのだろう。
「小沢さんは古い」という言葉を聞くとき、明治時代の夏目漱石が、文明開化のかけ声のもと、江戸の文化や価値観がどんどん切り捨てられて行く事に不安を抱いたような、そんな気持ちにさせられる。
平成維新と言われる今、私たちは「戦後」からの脱却を企てようとしている。
古いものは捨て、新しいものを選びとらねばならないのは事実だ。もちろん私も、世の中の変革を望んでいる。
しかし、変化の動乱に翻弄されないようにするのに必死で、ちゃんと考える余裕もなく、なんでもかんでも古いものは切り捨てるというのでは、歴史に何も学んでいない事になってしまう。
何が「いらない古いもの」で、何が「必要な古いもの」か、そして何が私たち日本人にとっての「普遍」なのか。普遍なんてあるのかどうかも、まだ私には分からないけれど、ちょっとそんなことを考えてみようと思った今回の代表選なのだ。
内村鑑三の「代表的日本人」でも読んでみようかな~。
というわけで、私の妄想でした。
最後になりましたが、
やはり、菅さんも、小沢さんも、仙石さんも、鳩山さんも、他の皆さんも、喧嘩しないで、本音を言い合って、良いとこ取りしてやってくれるのが、私としては良いんですけどね。分裂したって日本の将来にはなーんもいいことないと思う。だってさ、みんな政策的にはそんな大きく変わらないじゃないですか。目指してる目標は一緒でしょ。争う事がおかしいおかしい。
菅さんがやたら官僚にやられてるイメージになってるけど、民主党全体で見ると、やっぱり自民党の時よりはずっとましになろうとしてんのよ。ちょっと経済がヤバい感じだけど、今はしょうがないとも思う。自民がやったって死ぬまでの苦しい時間を延ばすだけですって。
これはどういう意味か。
簡単に言うと、小沢一郎にはある意味、「政治とカネ」の問題があるのかもしれないなあと思ったということだ。
しかし、それはマスメディアやそれを信じる人たちが言う西松建設からのカネがおかしいとか、狭義の「政治とカネ」の問題ではない。検察審査会に持ち込まれた政治資金収支報告書に関する「政治とカネ」の問題については、裁判をしたところで有罪になる事はほぼないだろうし、これ以上問うような事ではないと思う。
高野氏がビデオニュースで「政治とカネの問題の本質」として語ったのは、個別具体的な政治とカネの問題ではなく、政治文化としてのカネの問題だ。問題視されたのは、お金の入り口の問題というより、出口、つまり使い道の問題だ。もちろん私腹を肥やすという類いのものではない。
高野氏は、小沢の“剛腕”と言われるものの実態は、自らの資金や、幹事長職を獲って牛耳った政党助成金を、組織対策費として使い、物事を動かす政治手法のことだという。平たく言えば、カネを使って、仲間=数を集める手法だ。「政治闘争とは結局はカネと人事だ」と考え実行するような政治文化。それこそが、小沢氏の“剛腕”の正体だというのだ。
菅直人が公開討論会で
「小沢さんの政治のあり方というのは、どちらかといえば、資金的な強さ、仲間の数の多さ、そういうお金と数の原理が色濃くあるのは私だけが感じているのではないのではないでしょうか」と語っていたが、まさにそういう政治手法のことだ。
こうした政治文化は、自民党政権時代の古い政治文化と言える。
小沢の場合、違法性があるわけではない。また、私腹を肥やすカネではなく、政治に必要な資金であったりする。
しかし、資金を渡すことで人心までも掌握するという旧時代の手法を、政権交代した今、再び容認するのか?
そういわれると、確かに、容認していいのだろうか・・という気もしてくるのだ。
反小沢の急先鋒とされる仙谷由人は、高野氏によれば、カネを使わずに人脈を広げ、手練手管を弄せる、小沢に対抗できうる唯一の人材だと言う。彼の物事の理解力や基礎学力の高さが人望に繋がっているらしい。
高野氏は、今回の戦いは、菅vs小沢ではなく、実質的には、仙石vs小沢だと語るが、その本質は、権力闘争に関するこうした2つの異なる政治文化のぶつかり合いだと分析する。
政策や理念はどうあれ、カネを使って数を集める旧自民党的体質の政治家は、新しい時代の幕開けにはふさわしくないという考え方も確かにある。
じゃあ、菅&仙石に一票と思いそうになる。
しかし、私は、迷いなくそうすることもできない。
政策についての議論はおいとくとして、
問題とされる小沢の「政治文化」の中にも、こうした「カネの使い方」とはまた違った、捨てがたい何かがあるような気がするからだ。
そういえば、高野氏は「陸山会事件の本質」として、こんなことを言っていた。
『小沢一郎は、巨大な政治資金を集めて、何十人もの秘書を抱え、それを選挙プロフェッショナルとして派遣している。彼らを住まわせるためのマンションも必要だ。彼がそこまでするのは、民主党が坊ちゃん嬢ちゃんばかりだから、オレがプロとしてやってやってるという思いから。
しかし、近代政党なんだったら、選挙のプロを党の中で育てて、党のシステムとしてやっていかないと本当の強い政党にはならない。
しかし、小沢は、おまえらバカで政治を知らないからオレがやってやってんだという考え。違法だとかどうとか関係ない、それが陸山会事件の本質だ。』
高野氏は、「近代政党なら選挙のプロは党のシステムとして育成を」という。
しかし小沢のやり方は、いわゆる「書生」から始めるってことだ。
別の言い方すれば「徒弟制度」。
そして、彼らが苦労して学ぶ政治手法は古くさい。
さらに、こうしたやり方は自分の主人に対する変な忠誠を生み、物事の本質から目をそらさせるという一面があるとも思う。
しかし一方で思うのは、「選挙のプロを党の中で育てて、党のシステムとしてやっていく」という言葉からは、いわゆる「コーチング」みたいな米国的な合理的方法論というか、マニュアル化され身体性を伴わない学習と実践といおうか、悩みなく一足飛びに何かを獲得しようとする「今時の学びの態度」をイメージしてしまうのだ(もちろん高野氏は、こんなやわなシステム化を考えているわけではないと思う。私の勝手なイメージだ)。
私が小沢一郎に感じる捨てがたい部分というのは、多分、職人技につながるような「地道さ」とか「めんどくささ」みたいなものだ。一見、理不尽な師弟関係から習得され経験により研ぎすまされる日本的な「習熟」。
小沢一郎自身が実際にそんなものを目指しているかは知らないが、あのたたずまいにはそう感じさせる何かがある。
一方、高野氏は、こうした「オマエらに言っても分からんから、オレが全部やる」的なやり方や「結局はカネと人事だ」という考え方は小沢独特の「人間不信」と「ニヒリズム」から来ているのではないかという。
確かに、そんな気がする。
「地道さ」と「ニヒリズム」というアンビバレント。
その2つの間を繋いでいるのは、地道な努力しないで上手く世の中を切り抜けようとする狡いヤツや腹をくくっていないヤツに対する不信感なのではないのか。そして、そういうヤツに限って、カネに引っかかるのではないか。
かつて、小沢一郎に真っ向から政策を問うたものはいるのだろうか。
小沢一郎からカネを渡されて、私はいりませんと言ったヤツはいたのだろうか。
本当に小沢一郎が「ニヒリズム」の人なのだとしたら、彼は、そうした現代の風潮や世の中に復讐するつもりでカネを渡したのではないかとさえ思えるのだ。それは買いかぶりすぎか?
小沢一郎は、日本改造計画で日本の将来ビジョンを示すという仕事をした。
そして、現在もそのビジョンは改訂されつづけていると思う。
そんな仕事をする人間が「ニヒリズム」に陥るとしたら、なにが彼をそうさせたのかを問う中に、高度成長以降日本が陥った病とは何かを考える鍵があるような気がする。
なんか凄い話になっちゃったよ・・・。
ところで、この頃様々なところから、小沢を西郷隆盛に、菅を高杉晋作になぞらえる声が聞こえてくる。
しかし、小沢自身が尊敬する人物に挙げるのは大久保利通だ。
明治維新を境に、過去にとどまった西郷と、未来に踏み出した大久保。
多分、彼の中にはこの二人に象徴されるような何かが、アンビバレントに存在しているのだろう。
「小沢さんは古い」という言葉を聞くとき、明治時代の夏目漱石が、文明開化のかけ声のもと、江戸の文化や価値観がどんどん切り捨てられて行く事に不安を抱いたような、そんな気持ちにさせられる。
平成維新と言われる今、私たちは「戦後」からの脱却を企てようとしている。
古いものは捨て、新しいものを選びとらねばならないのは事実だ。もちろん私も、世の中の変革を望んでいる。
しかし、変化の動乱に翻弄されないようにするのに必死で、ちゃんと考える余裕もなく、なんでもかんでも古いものは切り捨てるというのでは、歴史に何も学んでいない事になってしまう。
何が「いらない古いもの」で、何が「必要な古いもの」か、そして何が私たち日本人にとっての「普遍」なのか。普遍なんてあるのかどうかも、まだ私には分からないけれど、ちょっとそんなことを考えてみようと思った今回の代表選なのだ。
内村鑑三の「代表的日本人」でも読んでみようかな~。
というわけで、私の妄想でした。
最後になりましたが、
やはり、菅さんも、小沢さんも、仙石さんも、鳩山さんも、他の皆さんも、喧嘩しないで、本音を言い合って、良いとこ取りしてやってくれるのが、私としては良いんですけどね。分裂したって日本の将来にはなーんもいいことないと思う。だってさ、みんな政策的にはそんな大きく変わらないじゃないですか。目指してる目標は一緒でしょ。争う事がおかしいおかしい。
菅さんがやたら官僚にやられてるイメージになってるけど、民主党全体で見ると、やっぱり自民党の時よりはずっとましになろうとしてんのよ。ちょっと経済がヤバい感じだけど、今はしょうがないとも思う。自民がやったって死ぬまでの苦しい時間を延ばすだけですって。
 | 代表的日本人 (岩波文庫)内村 鑑三岩波書店このアイテムの詳細を見る |












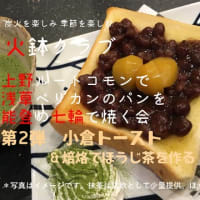



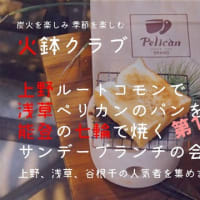



私がそのむかし所属した会社では、学閥、閨閥もなくて良い会社だなと思ってました。東大卒でも高卒でも、人事ではさほど違いがない扱いでした。
でもすぐに気がついたのは、親分子分みたいな関係の目に見えない人閥で人事が動いてるということです。これならいっそ、あいつは東大卒だからとあきらめられる方がまだましかな、とw
たとえ「金閥」でも、誰それにこれだけ金くばったから、それだけ分、言うことを聞かせるって、目に見えたら、まだましかなと思ったりします。
問題は、目に見えない金の動きで政治が動いてしまってるという不気味さにあるかと。