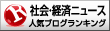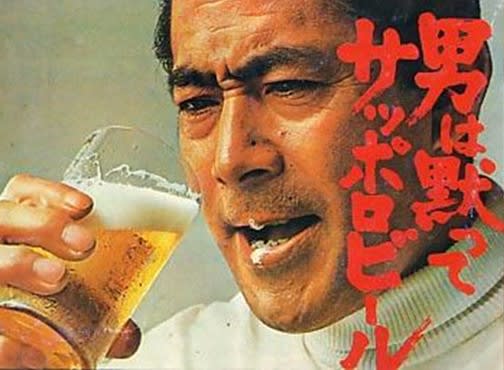ひとりで死ぬということと「お迎え現象」
緩和ケア医・おひとりさま応援医 奥野滋子
2016年09月17日 05時20分
無断転載禁止
どんな人間にも必ず訪れる死。最近は、子や孫や親戚一同に囲まれた「絵に描いたような大往生」が減り、「孤独死」が増える傾向にある。見守っていた家族をひとりきりで死なせてしまい、後悔する人も少なくない。終末期のがん患者に寄り添う緩和ケア医として、これまで2500人以上を 看取 みと ってきた奥野滋子さんは、「ひとりで死ぬことが寂しいとは限らない。人生に満足し安心して旅立つ方も多い」と、人の最期に関する一つの考え方を提示する。
「お母さんが会いに来てくれた」
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
60歳、女性。卵巣がん。
衰弱が進行し、入院していた。腹水で腹部は膨らみ、顔はやつれ、手足がやせ細っていて、自力では動くこともままならない。夫とは死別しており、子供がいないため独居である。母親は彼女が学生だった時に病死している。
ある朝の回診での出来事である。
「先生、昨日の夜、お母さんが会いに来てくれたんです」
「お母さんはそこの椅子(ベッド脇のソファ)に座って、窓の方を見ていて、全然私の方を見てくれないの。寂しかった。もっと近くに来てって言ったけど聞こえないみたいで」
「手を伸ばせば届くような気がするのに、手を差し伸べてくれない。私、お母さんに何か悪いことしたかな」
翌日の回診でも彼女は暗い顔をしながら、「お母さんはまだ私の方を見てくれない」「背中を向けたままずっとそこにいる」と話し、「早くこっちを向いてほしい」と訴えた。
翌々日の朝、彼女は非常にすがすがしい顔をして私たちを待っていた。
「先生、お母さんがやっと私の方を見てくれたの。とてもうれしい。お母さんが私の手をつかんでしっかり握ってくれたの。私、これできっとお母さんのもとに行けるのね。うれしい。先生、みなさん、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。私は大丈夫です」
その日の午後、突然血圧が低下して意識がなくなり、夜に亡くなった。
人間はつねに死に向かって歩んでいる
私は16年間、緩和ケア医として、病院や在宅診療で訪れた患者の自宅などで多くの方々の死に触れてきた。今回は、その経験から思うことをお伝えしたい。死への怖れ、永遠の命への希求、親しい人との死別がもたらす悲嘆は、場所や時代を問わず、人間にとって共通の重要な問題である。日本は今や超高齢社会に突入し、医療の進歩により容易に死ねない時代となった。どこで生きてどこで死ぬのかを、個々人が具体的に真剣に考え、決定せざるを得ない状況にある。
高齢者だから死が近いということでは、もちろんない。実は、人生のどの段階も生と死は表裏一体であり、人間はつねに死に向かって歩んでいるといっても過言ではない。健康な人であっても、事故や事件など不慮の事態によって命を奪われることもあるのだから、まだ若いからと言って人ごとでは済まされないのである。
安心して旅立つ人たち
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
現代は核家族化が進み、未婚や死別による独居家庭も増えている。たくさんの人が最期の迎え方として希望されるのが、テレビドラマのように家族親戚、友人たちに手を握られ、互いに感謝の言葉を伝え、コクッと静かに頭を垂れて旅立つという形だが、現在ではこれは非常に難しい。
独居の方なら、もともとひとりで死ぬという覚悟がある方も少なくないだろう。しかし、たとえ家族が一緒にいてくれる場合でも、24時間体制で付き添ってくれていた妻がトイレに行っている間に夫が息を引き取ることもあるし、隣で寝ていた夫が朝になったら冷たくなっていたということも、元気にしていた赤ちゃんが突然静かになって気が付いたら死んでいたということもある。誰かと一緒に死ぬということは不可能であり、最期は一人で旅立つことになると考えておいた方がよさそうである。
同時に、愛する人の最期に必ず立ち会えるという保証は誰にもできない。したがって、「たった一人で死なせてしまった」と後悔したり、親戚などから責められたりする必要はないのである。
ただ、全く誰とも縁がないとか、自分が生きた証しを残すこともできない「天涯孤独の最期」は、生きているうちの努力である程度回避できる。つまり、誰かと関わり、縁をつなぐ生き方をすること。もちろん単に出会いの数を増やすということではなく、たとえ1人でも2人でも、相手のことを深く考え大切にする気持ちを持って関われば、その人の心の内に自分の存在が記憶されていく。
そうした努力をしようと思ってもなかなか人と交わることが難しいと言う人はやはり、寂しいのかと言うと、そうでもないようだ。私がこれまで看取りをさせていただいたケースから見ると、「亡くなった方との再会」「お迎え」「先祖の存在」によって、安心して旅立つ人が少なくないからである。
もちろん実際に「お迎え」があるかどうかは私にはわからない。しかし「お迎え現象」というご本人が「見た」「聞いた」と感じられたお話はしばしば耳にしている。「お迎え現象」の中には、せん妄などの意識障害や認知力の低下などが影響している場合もあるかもしれないことはあらかじめお伝えしておく。
「共に」
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
70歳、男性。大腸がん
独身。すでに治療は終了し、終末期と考えられた。腹水が大量にたまり腹痛、腹部膨満感、全身倦怠けんたい感があり、ほぼ一日中ベッドで横になっていた。以前は自分の意思表示も明確で医療者にも協力的であったが、亡くなる1か月ほど前から体調が悪いのか言葉を発しなくなった。こちらからの問いにはうなずくか、首を振ることでコミュニケーションはかろうじてとれるが、細かな体調や心の問題を把握できるほどではなかった。主治医や病棟スタッフはうつではないかと考え、抗うつ薬の投与が検討されていた。
ある日、私が彼の病室を訪れた時、机の上に「南無真如一如大般涅槃経」と書かれたメモ帳が置かれているのに気づいた。そこで「信仰をお持ちですか」と問うと、うなずかれた。「今、あなたの仏様はどこにおられますか」と問うと、「共に」と一言だけ答えられた。「心配なことはありますか」と問うと、首を横に振って返事をされた。
数日後、息を引き取った。
元の記事を読む
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160915-OYT8T50018.html?page_no=2#csidxe49a3a6560b88298bcaedaabbe18160
Copyright © The Yomiuri Shimbun
「温泉に行く」
50歳、女性。卵巣がん。
抗がん治療を続けてきたが効果なく、食欲不振、嘔おう気・嘔吐、腹痛、全身倦怠感、腹水などの症状が出て、下肢のリンパ浮腫が増悪し、自宅での生活がままならなくなり入院となった。
独身で、有名ブランド店の店長を任され、仕事一途いちずの生活を送っていたという。生きがいにしていた仕事を他人に預け、着替えや排せつなども看護師に任せなければならず、介助なしに生活を営むことが困難な状況になって、「こんな状態が長く続くのなら死んだ方がまし」「人に迷惑をかけてまで生きるのはいや」と言うようになった。
キーパーソンの姉に話を聞いたところ、父親は認知症のため施設に入所中で、面会に行った娘のこともわからない状況ということだった。母親は乳がんが脳に転移し別の病棟に入院中で、病状は厳しいとのことであった。
ある日、「母親が面会に来た」と言う。しかし、周辺でそのような人物を目撃した人はいなかった。数日後のある日の夕方、「母と温泉に行く話をしていた。今帰ったばかり」と話した。その頃から一人部屋にいて誰かに語りかけている姿が時々見られた。「お母さんを送っていく」と言ってベッドから立ち上がろうとして転倒したこともあった。
まもなくして、別病棟にいた母親が息を引き取ったと、連絡が入った。その後、約1週間で本人も永眠した。
姉は「母と妹は仲が良かったので、一緒に温泉に出かけたのかしら」と語った。
予想外の展開に後悔した娘さんに
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
72歳、男性。膵臓すいぞうがん終末期。
妻とは数年前に死別し、独居であった。主治医に積極的ながん治療はないと言われて、自宅で過ごしたいと退院してきた。週3回程度、片道約1時間をかけて長女が訪ねて来ていたが、彼女は仕事を持っており長居をすることはできず、父親に頼まれた用事を済ませるくらいの時間しかなかった。普段の彼の生活はヘルパー、訪問看護師、訪問診療スタッフ、薬剤師がサポートしていた。
ある日の夕方、トイレで真っ黒の便が大量に出た後、その場に倒れ込んでしまった。いつもと違う様子に、たまたま居合わせた娘は救急車を呼んで病院に担ぎ込んだが、その数時間後に静かに息を引き取った。父親は徐々に衰えて死んでいくのだろうと思っていた娘は、予想外の急激な展開に「もっと一緒にいてあげればよかった」とずっと後悔していたという。
「父の死が受け入れられない」と知り合いの僧侶に相談したところ、「お父さんは先祖の列に入られたのですよ。いなくなってしまったわけではなくて、これからはずっと他のご先祖さんたちと一緒にあなた方を守ってくれるのですよ」と言われ、安堵あんどしたという。
死から目を逸らさず今日一日を精いっぱい生きる
ここに挙げた方々にとって、「お迎え」に訪れる死者たちは必ずしも恐怖の対象ではなかった。出現のしかたや会話も自然で、恐怖や不安も感じていないように見える場合には、その人のもとに一緒に行きたいという希求と一種の安堵感のようなものが本人には生まれているのかもしれない。もしそうであるならば、「お迎え現象」は死の恐怖を乗り越える助けになり得るのかもしれない。
生理的な生には限りがあり、死は必至で不死の願いは叶かなえられない。死が避けられないとすると、生の意味を拡大解釈して死の苦悩を和らげようとする考えが出てくる。つまり死後生を願い、先祖となって家族、イエを守っていく存在となることも生の意味の拡大解釈の一つの形ではないだろうか。死の時でも先祖は見守ってくれているので、ひとりぼっちの寂しい最期はないと信じることもできるのかもしれない。
ありきたりの話になるかもしれないが、私たちはいつ最期を迎えるかはわからない。その時が迫ってから「孤独のうちに死にたくない」、「誰かに看取ってほしい」とジタバタする前に、死から目を逸そらさず、今のうちから時間を共有できる相手を見つけて共に今日一日を精いっぱい生きる方が、この人生に満足し安心して旅立てるような気がする。
プロフィル
奥野 滋子( おくの・しげこ )
1960年、富山県生まれ。緩和ケア医。特定医療法人社団若林会湘南中央病院在宅診療部長。順天堂大学医学部客員准教授。麻酔・ペインクリニック医から緩和ケア医に転向。ホスピス、緩和ケア病棟、大学病院緩和ケアチームで全人的医療を実践し、約2500人の看取りを経験。患者からの「死んだらどうなるの」という問いをきっかけに宗教学、死生学を学ぶ必要性を感じ、東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科修士課程を修了。「ひとりで死ぬのだって大丈夫」(朝日新聞出版)、「お迎えされて人は逝く」(ポプラ社)など著書多数。
元の記事を読む
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160915-OYT8T50018.html?page_no=3#csidxcbf5369301cb375932e624b178b8d58
Copyright © The Yomiuri Shimbun
緩和ケア医・おひとりさま応援医 奥野滋子
2016年09月17日 05時20分
無断転載禁止
どんな人間にも必ず訪れる死。最近は、子や孫や親戚一同に囲まれた「絵に描いたような大往生」が減り、「孤独死」が増える傾向にある。見守っていた家族をひとりきりで死なせてしまい、後悔する人も少なくない。終末期のがん患者に寄り添う緩和ケア医として、これまで2500人以上を 看取 みと ってきた奥野滋子さんは、「ひとりで死ぬことが寂しいとは限らない。人生に満足し安心して旅立つ方も多い」と、人の最期に関する一つの考え方を提示する。
「お母さんが会いに来てくれた」
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
60歳、女性。卵巣がん。
衰弱が進行し、入院していた。腹水で腹部は膨らみ、顔はやつれ、手足がやせ細っていて、自力では動くこともままならない。夫とは死別しており、子供がいないため独居である。母親は彼女が学生だった時に病死している。
ある朝の回診での出来事である。
「先生、昨日の夜、お母さんが会いに来てくれたんです」
「お母さんはそこの椅子(ベッド脇のソファ)に座って、窓の方を見ていて、全然私の方を見てくれないの。寂しかった。もっと近くに来てって言ったけど聞こえないみたいで」
「手を伸ばせば届くような気がするのに、手を差し伸べてくれない。私、お母さんに何か悪いことしたかな」
翌日の回診でも彼女は暗い顔をしながら、「お母さんはまだ私の方を見てくれない」「背中を向けたままずっとそこにいる」と話し、「早くこっちを向いてほしい」と訴えた。
翌々日の朝、彼女は非常にすがすがしい顔をして私たちを待っていた。
「先生、お母さんがやっと私の方を見てくれたの。とてもうれしい。お母さんが私の手をつかんでしっかり握ってくれたの。私、これできっとお母さんのもとに行けるのね。うれしい。先生、みなさん、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。私は大丈夫です」
その日の午後、突然血圧が低下して意識がなくなり、夜に亡くなった。
人間はつねに死に向かって歩んでいる
私は16年間、緩和ケア医として、病院や在宅診療で訪れた患者の自宅などで多くの方々の死に触れてきた。今回は、その経験から思うことをお伝えしたい。死への怖れ、永遠の命への希求、親しい人との死別がもたらす悲嘆は、場所や時代を問わず、人間にとって共通の重要な問題である。日本は今や超高齢社会に突入し、医療の進歩により容易に死ねない時代となった。どこで生きてどこで死ぬのかを、個々人が具体的に真剣に考え、決定せざるを得ない状況にある。
高齢者だから死が近いということでは、もちろんない。実は、人生のどの段階も生と死は表裏一体であり、人間はつねに死に向かって歩んでいるといっても過言ではない。健康な人であっても、事故や事件など不慮の事態によって命を奪われることもあるのだから、まだ若いからと言って人ごとでは済まされないのである。
安心して旅立つ人たち
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
現代は核家族化が進み、未婚や死別による独居家庭も増えている。たくさんの人が最期の迎え方として希望されるのが、テレビドラマのように家族親戚、友人たちに手を握られ、互いに感謝の言葉を伝え、コクッと静かに頭を垂れて旅立つという形だが、現在ではこれは非常に難しい。
独居の方なら、もともとひとりで死ぬという覚悟がある方も少なくないだろう。しかし、たとえ家族が一緒にいてくれる場合でも、24時間体制で付き添ってくれていた妻がトイレに行っている間に夫が息を引き取ることもあるし、隣で寝ていた夫が朝になったら冷たくなっていたということも、元気にしていた赤ちゃんが突然静かになって気が付いたら死んでいたということもある。誰かと一緒に死ぬということは不可能であり、最期は一人で旅立つことになると考えておいた方がよさそうである。
同時に、愛する人の最期に必ず立ち会えるという保証は誰にもできない。したがって、「たった一人で死なせてしまった」と後悔したり、親戚などから責められたりする必要はないのである。
ただ、全く誰とも縁がないとか、自分が生きた証しを残すこともできない「天涯孤独の最期」は、生きているうちの努力である程度回避できる。つまり、誰かと関わり、縁をつなぐ生き方をすること。もちろん単に出会いの数を増やすということではなく、たとえ1人でも2人でも、相手のことを深く考え大切にする気持ちを持って関われば、その人の心の内に自分の存在が記憶されていく。
そうした努力をしようと思ってもなかなか人と交わることが難しいと言う人はやはり、寂しいのかと言うと、そうでもないようだ。私がこれまで看取りをさせていただいたケースから見ると、「亡くなった方との再会」「お迎え」「先祖の存在」によって、安心して旅立つ人が少なくないからである。
もちろん実際に「お迎え」があるかどうかは私にはわからない。しかし「お迎え現象」というご本人が「見た」「聞いた」と感じられたお話はしばしば耳にしている。「お迎え現象」の中には、せん妄などの意識障害や認知力の低下などが影響している場合もあるかもしれないことはあらかじめお伝えしておく。
「共に」
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
70歳、男性。大腸がん
独身。すでに治療は終了し、終末期と考えられた。腹水が大量にたまり腹痛、腹部膨満感、全身倦怠けんたい感があり、ほぼ一日中ベッドで横になっていた。以前は自分の意思表示も明確で医療者にも協力的であったが、亡くなる1か月ほど前から体調が悪いのか言葉を発しなくなった。こちらからの問いにはうなずくか、首を振ることでコミュニケーションはかろうじてとれるが、細かな体調や心の問題を把握できるほどではなかった。主治医や病棟スタッフはうつではないかと考え、抗うつ薬の投与が検討されていた。
ある日、私が彼の病室を訪れた時、机の上に「南無真如一如大般涅槃経」と書かれたメモ帳が置かれているのに気づいた。そこで「信仰をお持ちですか」と問うと、うなずかれた。「今、あなたの仏様はどこにおられますか」と問うと、「共に」と一言だけ答えられた。「心配なことはありますか」と問うと、首を横に振って返事をされた。
数日後、息を引き取った。
元の記事を読む
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160915-OYT8T50018.html?page_no=2#csidxe49a3a6560b88298bcaedaabbe18160
Copyright © The Yomiuri Shimbun
「温泉に行く」
50歳、女性。卵巣がん。
抗がん治療を続けてきたが効果なく、食欲不振、嘔おう気・嘔吐、腹痛、全身倦怠感、腹水などの症状が出て、下肢のリンパ浮腫が増悪し、自宅での生活がままならなくなり入院となった。
独身で、有名ブランド店の店長を任され、仕事一途いちずの生活を送っていたという。生きがいにしていた仕事を他人に預け、着替えや排せつなども看護師に任せなければならず、介助なしに生活を営むことが困難な状況になって、「こんな状態が長く続くのなら死んだ方がまし」「人に迷惑をかけてまで生きるのはいや」と言うようになった。
キーパーソンの姉に話を聞いたところ、父親は認知症のため施設に入所中で、面会に行った娘のこともわからない状況ということだった。母親は乳がんが脳に転移し別の病棟に入院中で、病状は厳しいとのことであった。
ある日、「母親が面会に来た」と言う。しかし、周辺でそのような人物を目撃した人はいなかった。数日後のある日の夕方、「母と温泉に行く話をしていた。今帰ったばかり」と話した。その頃から一人部屋にいて誰かに語りかけている姿が時々見られた。「お母さんを送っていく」と言ってベッドから立ち上がろうとして転倒したこともあった。
まもなくして、別病棟にいた母親が息を引き取ったと、連絡が入った。その後、約1週間で本人も永眠した。
姉は「母と妹は仲が良かったので、一緒に温泉に出かけたのかしら」と語った。
予想外の展開に後悔した娘さんに
(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
72歳、男性。膵臓すいぞうがん終末期。
妻とは数年前に死別し、独居であった。主治医に積極的ながん治療はないと言われて、自宅で過ごしたいと退院してきた。週3回程度、片道約1時間をかけて長女が訪ねて来ていたが、彼女は仕事を持っており長居をすることはできず、父親に頼まれた用事を済ませるくらいの時間しかなかった。普段の彼の生活はヘルパー、訪問看護師、訪問診療スタッフ、薬剤師がサポートしていた。
ある日の夕方、トイレで真っ黒の便が大量に出た後、その場に倒れ込んでしまった。いつもと違う様子に、たまたま居合わせた娘は救急車を呼んで病院に担ぎ込んだが、その数時間後に静かに息を引き取った。父親は徐々に衰えて死んでいくのだろうと思っていた娘は、予想外の急激な展開に「もっと一緒にいてあげればよかった」とずっと後悔していたという。
「父の死が受け入れられない」と知り合いの僧侶に相談したところ、「お父さんは先祖の列に入られたのですよ。いなくなってしまったわけではなくて、これからはずっと他のご先祖さんたちと一緒にあなた方を守ってくれるのですよ」と言われ、安堵あんどしたという。
死から目を逸らさず今日一日を精いっぱい生きる
ここに挙げた方々にとって、「お迎え」に訪れる死者たちは必ずしも恐怖の対象ではなかった。出現のしかたや会話も自然で、恐怖や不安も感じていないように見える場合には、その人のもとに一緒に行きたいという希求と一種の安堵感のようなものが本人には生まれているのかもしれない。もしそうであるならば、「お迎え現象」は死の恐怖を乗り越える助けになり得るのかもしれない。
生理的な生には限りがあり、死は必至で不死の願いは叶かなえられない。死が避けられないとすると、生の意味を拡大解釈して死の苦悩を和らげようとする考えが出てくる。つまり死後生を願い、先祖となって家族、イエを守っていく存在となることも生の意味の拡大解釈の一つの形ではないだろうか。死の時でも先祖は見守ってくれているので、ひとりぼっちの寂しい最期はないと信じることもできるのかもしれない。
ありきたりの話になるかもしれないが、私たちはいつ最期を迎えるかはわからない。その時が迫ってから「孤独のうちに死にたくない」、「誰かに看取ってほしい」とジタバタする前に、死から目を逸そらさず、今のうちから時間を共有できる相手を見つけて共に今日一日を精いっぱい生きる方が、この人生に満足し安心して旅立てるような気がする。
プロフィル
奥野 滋子( おくの・しげこ )
1960年、富山県生まれ。緩和ケア医。特定医療法人社団若林会湘南中央病院在宅診療部長。順天堂大学医学部客員准教授。麻酔・ペインクリニック医から緩和ケア医に転向。ホスピス、緩和ケア病棟、大学病院緩和ケアチームで全人的医療を実践し、約2500人の看取りを経験。患者からの「死んだらどうなるの」という問いをきっかけに宗教学、死生学を学ぶ必要性を感じ、東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科修士課程を修了。「ひとりで死ぬのだって大丈夫」(朝日新聞出版)、「お迎えされて人は逝く」(ポプラ社)など著書多数。
元の記事を読む
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160915-OYT8T50018.html?page_no=3#csidxcbf5369301cb375932e624b178b8d58
Copyright © The Yomiuri Shimbun