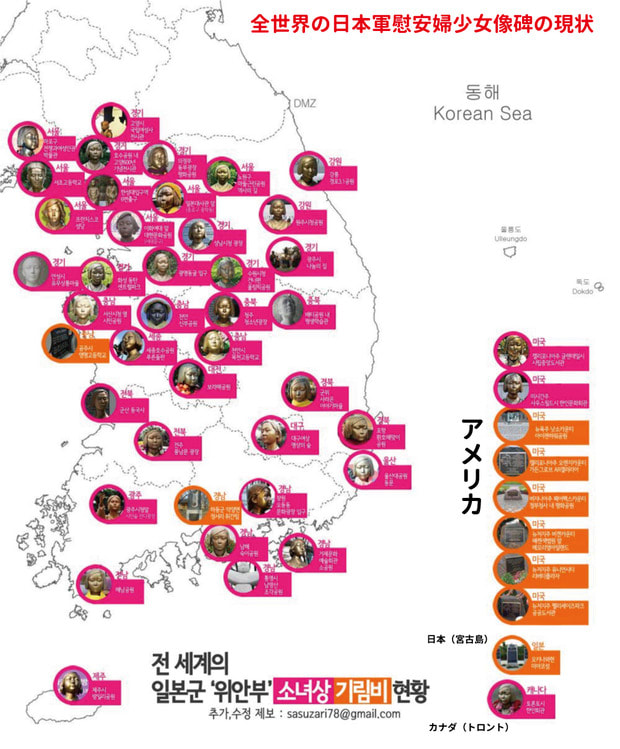【コインランドリービジネスの現実】予想売上より30万の赤字が数か月。実際に経営してみてわかった成功のカギ。
6/29(木) 7:10配信 マネーの達人
【コインランドリービジネスの現実】予想売上より30万の赤字が数か月。実際に経営してみてわかった成功のカギ。
コインランドリービジネスが注目を集めています。
コインランドリービジネス
毎月60万円ほどの売上げが見込めると言われるコインランドリービジネス。カフェやコンビニなどと比べると、その売上高はほんのわずか。
ところが、そんなコインランドリービジネスが、サラリーマンや定年退職者から熱い視線を集めています。その理由と実情に迫ってみましょう。
どうしてコインランドリー?
何がコインランドリービジネスをそこまで魅力的に見せているのか?
それは装置産業であるということではないでしょうか。人間ではなく機械が働いてくれるため、人件費もほとんど必要ありません。
人を雇用することには一定のリスクが伴います。そのリスクを負わずして始められるのが、多くの人にとって魅力なのです。実際、私がコインランドリーを始める際も、その部分を大きく評価しました。
売上げと利益
では、肝心な売上げと利益についてはどうでしょう。コインランドリーの平均的な売上げは、1か月に付き60万円ほどと言われています。
とはいえ、売上高はお店の規模によってさまざまです。
どのようなお店であれば、60万円という売上げを実現できるのかというと、次のとおりです。
・ 店舗面積30坪
・ 洗濯機6台
・ 乾燥機10台
次に、経費について考えてみましょう。コインランドリーの経費には次のようなものあります。
・ 家賃(テナントを借りる場合)
・ 洗剤、水道光熱費
・ 機材のリース代
■家賃
上述規模のテナントを借りる場合の家賃は20万円程度です。
■光熱費、リース代など
・ 洗剤や水道光熱費は24万円
・ リース代は20万円
といったところでしょうか。合計64万円の経費は売上げを上回ってしまいます。
つまり、毎月4万円の赤字になってしまうのです。
【コインランドリービジネスの現実】予想売上より30万の赤字が数か月。実際に経営してみてわかった成功のカギ。
遊休地があれば家賃は不要だが
■遊休地や空き店舗を所有している人にとってはどうでしょう?
その場合、20万円の家賃は不要となり収支は逆転。毎月16万円の黒字になります。
機材を購入した場合はリース代も不要となり、毎月の利益は36万円に。
■機材のリース代は7年後から利益となる
機材をリースで調達したとしても、7年ほどで償却期間が終了します。その後のリース料金はタダ同然なので、7年経過後には16万円の利益が上げられるということになります。
開業から7年間は貯金をするというイメージを持ってもらえると分かりやすいかもしれません。
このように、「そこそこ」そして「継続的に」収益を生むビジネスとして、コインランドリーの経営が注目を集めているのです。
シミュレーションを鵜呑みにして出店してしまうと…
出店を検討するほとんどのオーナーは、売り上げについてシミュレーションしてみることでしょう。
さまざまな要因を考慮する必要があるため、自分ではなかなか正確なシミュレーションをすることができません。
そこで頼りになるのが、メーカーやコインランドリーの運営会社が提供するシミュレーションです。
■シミュレーションと現実の違い
しかし、100%信用してしまうと後々取り返しがつかなくなってしまうことも…
私が出店を検討していたときのシミュレーション結果によると、毎月の予想売上高は56万円ほど。しかし、実際の売上げは10万円台。その数字が数か月間続きました。
自分でも30万円から40万円の売上げを予想していたので、正直その数字には戸惑いました。
なんとか売上げを伸ばすべく、集客に効果的な方法やどうしたらお客さんに喜んでもらえるかなど、毎日必死に考えたものです。
【コインランドリービジネスの現実】予想売上より30万の赤字が数か月。実際に経営してみてわかった成功のカギ。
徹底したリサーチが重要
最悪のケースも珍しくない
私のお店は、ご紹介した平均的な規模のお店の半分程度です。つまり、ダメージもその半分程度に抑えられるため、そこから徐々に回復することができました。
しかし、大きな規模のお店ではそうはいかないでしょう。多額の投資をした挙句に撤退を余儀なくされる最悪のケースに陥ってしまうことも珍しくありません。
■徹底したリサーチが重要
コインランドリービジネスが成功するか否か、カギを握るのは立地です。
商圏(半径2km以内)の人口や世帯構成、住居のタイプなどはインターネットで調べられます。
駐車場の有無や車の止めやすさ、視認性の良さなども大きな要素です。
「これならやれる!」と確信できるまで、自分自身でリサーチすることも大切だと思います。(執筆者:内田 陽一)