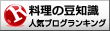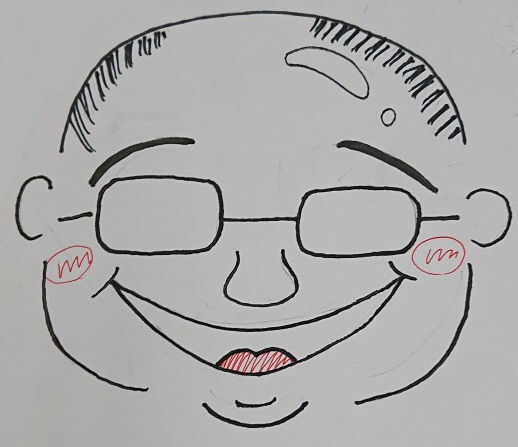【10月18日は何の日】
1866年 シーボルト、亡くなる
1870年 鈴木大拙、生まれる
【前の答】チンゲン菜
Q1,ボクの生産量1位はどこでしょう?
a,愛知 b,静岡 c,埼玉 d,茨城
→d,茨城28%、静岡18%、愛知7%、埼玉6%です。
Q2,ボクの葉軸が白いものを何というでしょう?
→白菜と書いて「パクチョイ」。
ハクサイと紛らわしいので
「広東白菜」や「小白菜」と書いたり、
「白梗菜」と記して区別することもあります。
Q3,一年を等して栽培されますが、夏場に種をまくと何日くらいで収穫ができるでしょうか?
a,20日 b,30日 c,40日 d,50日
→b,
Q4,一年を等して栽培されますが、冬場に種をまくと何日くらいで収穫ができるでしょうか?
a,40日 b,50日 c,60日 d,70日
→c,
【脳トレの答】ミンチ
【今日の話】
十五夜の月、見ましたか?
私は雲が多い中、しばらく佇んで
雲の切れ間から皓々と光る満月を見ることができました。
待ちながら、かぐや姫ってこんな情景かな?
なんて思いながら、雲を見つめていました。
今のところ、微妙な天気予報です。
見られるといいなぁ。
さて、十三夜は旧暦の9月13日~14日の夜をいいます。
今年は旧暦の9月13日の10月18日月曜日が十三夜です。
十三夜は新月から数えて13日目なので、
満月になる少し手前の月です。
日本人は完璧なものも好むのですが、
その一歩手前を味わう感性を持ち合わせているような気がします。
ですから、十五夜が中国から伝わった風習であるのに対して、
十三夜は日本で始まった風習なんです。
秋の収穫に感謝しながら、美しい月を愛でるのです。
昔は月の満ち欠けなどを基準とする旧暦(太陰暦)を使っていたため、
人々の生活と月は密接につながっていました。
十三夜のお月見の始まりについては諸説ありますが、
平安時代に醍醐天皇が月見の宴を催し詩歌を楽しんだのが
十三夜の月見の始まりではないかというのが有力な説です。
また、平安時代後期の書物に名月の宴についての記述があり、
宇多天皇が「今夜の名月は並ぶものがないほど優れている」という和歌を詠んだと記されていて、
風習として親しまれていたことがわかります。
お月見に欠かせないのがお供えですね。
月の見える場所にお供えしましょう。
お盆などで代用してもいいと思います。
すすき、月見団子、栗や豆など。
収穫に感謝する行事なので、収穫できた物をお供えしてみましょう。
そうそう、『十三夜』という短編小説がありますが、
お月見とは関係がありません。
なぜそんなタイトルにしたのか、
読んで考えるのも十三夜にふさわしいかもしれません。
Q1,十五夜は中秋の名月と言いますが、十三夜は何というでしょうか?
a,晩秋の名月 b,片見月 c,清い月 d,後の月
Q2,十六夜は旧暦16日の月のことです。では、旧暦17日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q3,旧暦18日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q4,旧暦19日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q5,旧暦20日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q6,『十三夜』の作者は誰でしょう?
a,樋口一葉 b,森鴎外 c,志賀直哉 d,島崎藤村
Q7,喜劇『十二夜』の作者は誰でしょう?
a,シェークスピア b,モリエール c,井原西鶴 d,式亭三馬
【今日のひと言】大きなことは一晩ではできない、継続しかない
【今日の脳トレ】

【今週の一枚】

1866年 シーボルト、亡くなる
1870年 鈴木大拙、生まれる
【前の答】チンゲン菜
Q1,ボクの生産量1位はどこでしょう?
a,愛知 b,静岡 c,埼玉 d,茨城
→d,茨城28%、静岡18%、愛知7%、埼玉6%です。
Q2,ボクの葉軸が白いものを何というでしょう?
→白菜と書いて「パクチョイ」。
ハクサイと紛らわしいので
「広東白菜」や「小白菜」と書いたり、
「白梗菜」と記して区別することもあります。
Q3,一年を等して栽培されますが、夏場に種をまくと何日くらいで収穫ができるでしょうか?
a,20日 b,30日 c,40日 d,50日
→b,
Q4,一年を等して栽培されますが、冬場に種をまくと何日くらいで収穫ができるでしょうか?
a,40日 b,50日 c,60日 d,70日
→c,
【脳トレの答】ミンチ
【今日の話】
十五夜の月、見ましたか?
私は雲が多い中、しばらく佇んで
雲の切れ間から皓々と光る満月を見ることができました。
待ちながら、かぐや姫ってこんな情景かな?
なんて思いながら、雲を見つめていました。
今のところ、微妙な天気予報です。
見られるといいなぁ。
さて、十三夜は旧暦の9月13日~14日の夜をいいます。
今年は旧暦の9月13日の10月18日月曜日が十三夜です。
十三夜は新月から数えて13日目なので、
満月になる少し手前の月です。
日本人は完璧なものも好むのですが、
その一歩手前を味わう感性を持ち合わせているような気がします。
ですから、十五夜が中国から伝わった風習であるのに対して、
十三夜は日本で始まった風習なんです。
秋の収穫に感謝しながら、美しい月を愛でるのです。
昔は月の満ち欠けなどを基準とする旧暦(太陰暦)を使っていたため、
人々の生活と月は密接につながっていました。
十三夜のお月見の始まりについては諸説ありますが、
平安時代に醍醐天皇が月見の宴を催し詩歌を楽しんだのが
十三夜の月見の始まりではないかというのが有力な説です。
また、平安時代後期の書物に名月の宴についての記述があり、
宇多天皇が「今夜の名月は並ぶものがないほど優れている」という和歌を詠んだと記されていて、
風習として親しまれていたことがわかります。
お月見に欠かせないのがお供えですね。
月の見える場所にお供えしましょう。
お盆などで代用してもいいと思います。
すすき、月見団子、栗や豆など。
収穫に感謝する行事なので、収穫できた物をお供えしてみましょう。
そうそう、『十三夜』という短編小説がありますが、
お月見とは関係がありません。
なぜそんなタイトルにしたのか、
読んで考えるのも十三夜にふさわしいかもしれません。
Q1,十五夜は中秋の名月と言いますが、十三夜は何というでしょうか?
a,晩秋の名月 b,片見月 c,清い月 d,後の月
Q2,十六夜は旧暦16日の月のことです。では、旧暦17日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q3,旧暦18日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q4,旧暦19日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q5,旧暦20日の月を何というでしょうか?
a,居待月 b,更待月 c,立待月 d,寝待月
Q6,『十三夜』の作者は誰でしょう?
a,樋口一葉 b,森鴎外 c,志賀直哉 d,島崎藤村
Q7,喜劇『十二夜』の作者は誰でしょう?
a,シェークスピア b,モリエール c,井原西鶴 d,式亭三馬
【今日のひと言】大きなことは一晩ではできない、継続しかない
【今日の脳トレ】

【今週の一枚】