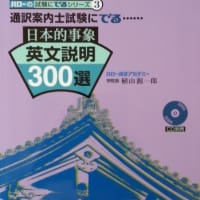2019年度<合格体験記>(1)(スペイン語)
●スペイン語(メルマガ読者、セミナー参加者、動画利用者、教材利用者)
① 受験の動機
20~40代にかけて留学と仕事で海外3か国に20年弱滞在していましたが、人々との触れ合いを通じ国際民間交流の楽しさと難しさを身をもって実感しました。また、その間に日本の良さを改めてよく理解できました。
これまでは自分が外に出る立場でしたが、今後は日本に来る人たちを受け入れる側として海外からの旅行者に日本の良さを伝えられればという思いで、通訳案内士に興味を持ちました。
② 第1次試験対策
昨年4月から勉強を開始。朝夕の通勤時間と昼休みに知識をインプットし、週末は過去問対応などアウトプットの時間を長めに取りました。
50台半ばで記憶力も落ちており、そのうえ体調も思わしくない時期だったので、結果的に4か月の短期集中型で1次試験に合格できたのは幸いでした。
5科目の時間配分は全体を10として、スペイン語3、地理3、歴史3、一般常識0.7、通訳実務0.3程度でした。
スケジュールは、4-6月はスペイン語・地理・歴史に集中、7月に一般常識を開始、8月に通訳実務を追加しました。7-8月にもスペイン語、地理、歴史の復習を継続しました。
このような短期間で何とか回せたのは、スペイン語以外の4科目でのインプット情報源をハローの教材に絞り、他に手を広げなかったおかげだと思います。
<スペイン語>(90点)合格 → 公式回答がありませんので点数はあくまでも自己感覚です
市販の過去問集も購入し30年分やりましたが、著作権の関係で長文は削除が多く、実質は半分くらいしかできていませんが、間違えたところは何度も見直しました。
学生時代に勉強した文法の記憶と駐在時代の実使用経験がありましたが、直近10年はほとんど使っていなかったため、久しぶりにスペイン語の音声と感覚に慣れることを目的にニュースや番組を聴いていました。
お勧めはNHK World Radio Japanのアプリです。10分強の短い番組が多いので移動などのすきま時間でも聴きやすいうえ、日本観光や文化に関するトピックが中心で通訳案内士試験との相性もいいと思います。
英仏独伊西葡露中韓を含む多くの言語でほぼ毎日内容が更新され、すべて無料なのもありがたいです。
<日本地理>(87点) 合格
まずは「マラソンセミナーの音声」を2回通して聴きました。
もともと地理が好きなのと、先生のとぼけた語り口にもハマり音声の長さは苦になりませんでした。
できるだけ「都道府県別地図帳」も合わせて参照しました。市販の「旅に出たくなる地図帳」もビジュアルイメージを補うために眺めていました。
過去問は5年分解きました。
試験直前は「切腹資料」に2回目を通しました。7月の「植山先生ライブセミナー地理」も一度参加しました。
第1次邦文試験対策<特訓1800題>も使おうと思いましたが、時間が足りず断念しました。
<第1次筆記試験【問題】>→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.geo.pdf
<直前対策セミナー>(日本地理資料)→ http://www.hello.ac/2019.7.6.pdf
<マラソンセミナー>(日本地理)(12講義24時間)→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667
<都道府県別地図帳> → http://hello.ac/map.prefectures.pdf
<旅に出たくなる地図帳>
<日本歴史>(71点) 合格
まず山川の「詳説日本史B」を読んで全体の流れを確認したあと、日本地理と同様に「マラソンセミナー」音声版を2回通しで聞きました。
過去問を5年分解きながら、最後に「切腹資料」でおさらいをしました。
「植山先生ライブセミナー歴史」は残念ながら出席できませんでした。
NHKの「知恵泉」と「歴史秘話ヒストリア」は資料で学んだことをビジュアルでイメージする助けになりますし、歴史上の人物により興味を持つことができました。
幸いぎりぎりの点数で合格できましたが、より確実に合格するには特訓1800題をやっておけばよかったと思いました。
<第1次筆記試験【問題】>→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.his.pdf
<直前対策セミナー>(日本歴史資料)→ http://www.hello.ac/2019.6.30.pdf
<マラソンセミナー>(日本歴史)(12講義24時間)→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/aa9caa987007e8ef9f390a0a88c6e667
<日本史の時代区分と各文化の特徴> → http://hello.ac/timeline.pdf
地理と歴史の学習に共通してお勧めしたいことは、文字情報のみに頼らずできるだけビジュアルイメージと共に記憶することです。
写真問題が出る出ないにかかわらず、記憶作業を少しでも楽しく、そして定着させるために自分にはビジュアルが重要でした。
<一般常識>(46点) 合格
通訳案内士に挑戦する前年「日経TEST」というビジネスマン向けの政治/経済/産業/文化知識検定の勉強をしていました。
通訳案内士の勉強開始前に一般常識の過去問を見たところ、日経TESTの知識がかなり流用できそうでしたので、遅めですが7月から対策を開始。過去問を解いた後は「切腹資料」でおさらいをしました。
通訳案内実務の勉強を兼ねて「観光白書」は試験直前に目を通しました。
<第1次筆記試験【問題】>→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.gen.pdf
<直前対策セミナー>(一般常識資料) → http://www.hello.ac/2019.7.21.pdf
<平成31年度観光白書(要旨)→ https://www.mlit.go.jp/common/001294574.pdf
<通訳案内の実務>(38点) 合格
難易度が上がるという植山先生の教えを守り、手を抜いたつもりはなかったのですが、想定以上に法令問題が多くかつ細かく出題されたために、期待していた点は取れませんでした。
8月になって「切腹資料」を集中的に勉強し、「観光庁研修テキスト」も1度だけ通読しました。
<第1次筆記試験【問題】>→ https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<最重要事項のまとめ> → http://www.hello.ac/matome.jitumu.pdf
<直前対策セミナー>(通訳案内の実務資料) → http://www.hello.ac/2019.8.5.pdf
<観光庁研修テキスト> → http://hello.ac/jitumu.122.pdf
③ 第2次試験対策
「日本的事象英文説明300選」を購入し、英文をスペイン語に訳そうとしました。
見てもらえる人がいないので、Google翻訳にかなりお世話になりました。Google翻訳の日本語→スペイン語の翻訳精度は怪しいですが、英語→スペイン語は相当精度が高いと思います。
1次試験後しばらくは翌年用の英語対策をしていたため、スペイン語2次対策の開始が10月下旬と遅くなってしまい、すぐに時間が足りないことに気づきました。
結局300題すべての翻訳はあきらめ、鉄板128題の翻訳に切り替えました。
翻訳作業と並行して、自分でスペイン語を読み上げた音声データをスマホに入れて通勤電車で聴いていました。自声を聞くのが気恥ずかしいのは最初だけでしたが、決して他人には聞かせませんでした(笑)。
音声録音現場に家族が入ってきたりすると照れてしまい、自分の笑い声が入った音声データもありました。
私の場合、試験直前に勉強したテーマ「風鈴」がプレゼンのお題に出たのでとてもラッキーでした。
私の反省を踏まえ、今後の受験者さんには300題すべてをできる限り余裕をもってやりきっておくことをお勧めします。
「備えあっても憂いあり」は、かつて貴乃花が一日消防署長を務めた際の名言ですが、「備えなければ憂い増え」となりますので。
「日本的事象英文説明300選」<鉄板厳選128題> → http://www.hello.ac/teppan128.pdf
④ ハローのセミナー、メルマガ、動画、教材などで役に立ったこと
1次試験対策として、勉強初期には地理と歴史のマラソンセミナー音声教材とテキストを何度も利用させていただきました。
そして試験が近づいたときは「切腹資料」が復習にとても役立ちました。8月以降は多くの資料を見返さず、切腹資料に何度も目を通していました。
2次対策では何といっても「日本的事象英文説明300選」と「鉄板128題」です。これがなければ何を勉強したらいいのか絞りようがなかったと思います。
植山先生の各種動画もモチベーションを維持するためにとても役立ちました。
頻繁に届くメールマガジンは、孤独な受験者にとって「先生が気にかけてくれている」という心の支えになっていたと思います。
植山先生のライブセミナーも時間が許す限り参加をお勧めします。
私は1度しか行けませんでしたが、植山先生に直接お会いできたことで「教材への親しみ」が沸いたり、ブログの背景写真を見るたびに「自分も合格してパーティーに出たい」という意欲を掻き立ててくれたりしました。
受験者はたいてい孤独なことが多いと思います。読みたい本を我慢して通勤中に勉強したり、会社で一人ランチをあわてて済ませ残り時間を神社や公園でこっそり勉強していると、時々切なくなることがありました。植山先生からのメルマガでの励ましや手作り資料の温かみは、「孤独な勉強の精神的な支え」になっていたと思います。
⑤ 今後の抱負
まずはハローの合格記念パーティに出て、植山先生や同期合格者の皆さんと喜びを分かち合いたいです。
合格したといっても直ぐにガイドができる実力があるとは思えませんし、会社が未だ副業を認めていませんので、しばらくはボランティアの実務経験を得る機会を積極的に探したいと思います。
今年は「英語・通訳案内士」にもチャレンジする予定で、既にTOEICで1次試験免除を得ています。
2次対策は昨年の反省を踏まえ「日本的事象英文説明300選」をしっかりマスターしたいと思います。
また、副業解禁までの準備期間中に「旅行業務取扱管理者資格」も取得しておきたいと思います。
2年以内にこれらの準備を整え、英語とスペイン語を駆使して、お客の募集、旅程企画・管理、ガイドをすべて自前でやるのが目標です。
魅力的なブログや動画サイトの作り方も勉強が必要ですね。
植山先生、本当にありがとうございました。
また、皆様のご健闘をお祈りいたします。
以上