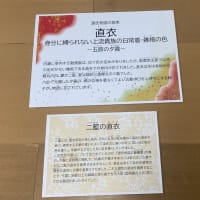いづれの宮にかおはしけむ。白河院にまろもろともにおはして かく書きて家守(いへもり)に取らせておはしぬ。 「われが名は 花盗人と 立てば立て ただ一枝は 折りて帰らむ」 日ごろ見て、折りて、左衛門督の返し 「山里の 主(ぬし)に知られで 折る人は 花をも名をも 惜しまざりけり」 とある文を付けたる花のいとおもしろきを、まるが口ずさびにうち言いし 「折る人の それなるからに あぢきなく 見し山里の 花の香ぞする」 左衛門督の返事、また、宮せさせたまふ 「知られぬぞ かひなかりける 飽かざりし 花に代へつる 身をば惜しまず」 又、左衛門督 「人知れぬ 心のうちを 知りぬれば 花のあたりに 春は過ぐさむ」 一日、御文つけたりし花を見て、まるなむき言いしと人の語りければ、 かくのたまひし 「知るらめや その山里の 花の香は なべての袖に うつりやはする」 返し 「知られじと そこらの霞の 隔てしに 尋ねて花の 色は見てしを」 又、左衛門督、陸奥守(みちのくかみ)の下りしころ、 それにうちそへたることとぞ見し 「今さらに 霞の閉づる 白河の 関をしひては 尋ねべしやは」 まろ、返し 「行く春の とめまほしきに 白河の 関も越ゆる 身ともなるかな 」 (王朝女流歌人抄より。和歌表示に「」を私が勝手につけました)
コメントで電池切れさんがご指摘された和泉式部集冒頭文歌群、
長いのですが、清水好子氏王朝女流歌人抄にも載っていて面白いので
載せておきます。
長いのですが、清水好子氏王朝女流歌人抄にも載っていて面白いので
載せておきます。
清水好子氏の解釈。以下抜粋。
白河院とは藤原公任(きんとう)の鴨河東岸白河の地にある別荘。 その辺りは一帯桜の名所だった。 (公任は紫式部に若紫はここにいらっしゃいますか?と尋ねた人ですね) 道長の下ながら家柄はこちらの方が上で藤氏の本流。 歴代后妃を出す名門。当代一の和漢の教養人として著名で、道長もこの人を味方につけるようにしていた。 師宮はその公任の別荘に和泉を伴った。実際は公任の留守に寄った。 「花盗人だといううわさが立つなら立ってもよい。 あまりにこの花が見事なのでせめて一枝だけでも折ってやろう」 しかし一枝は唐詩以来美女を意味、 このごろの和泉との世評に、立てば立てと、胸をはる意気込みが感じられる。 公任は何日かして宮のお手紙を見て あらためて桜を一枝折りそれに返歌をつける。 「山里の主ー私に内緒で、花を折る方は、 美しい花をもご名誉をもものともされないのですね」 この桜の一枝があまりに見事だったので、 側の和泉式部が思わず心に浮かぶまま口づさんだ歌 「折る人が、ほのかならぬあの方ー公任さまですから、 もうむやみにこの間、宮さまと見た山里の花と同じ美しさですこと」 折る人が公任だから、この間と同じように美しいと公任を褒めたたえた歌。 公任への宮の返歌は 「あなたに私の気持ちがわかってもらえないのは残念だ。 しかし、いつまでも見飽きぬ美しい花のためには、わが身の名誉は惜しまないのです」 裏にはやはり和泉を手折ったことに寄せる気持ちがあると見たい。 公任もこれにこたえて 「誰にも分からぬ宮様のお心のうちはよく存知あげておりますから、 私もまたこの春は花のあたりで過ごしましょう」 と、下の句は桜を賞美する風雅の体で結んだ。 ところが先日の公任の返歌をつけた桜を見て、 和泉がこう詠みましたと聞かされた公任は次のようなお歌をお詠みになった。 「ご承知かな。あの私が差し上げた桜は、誰の袖にでも匂いを移したりしないのですよーあなたのように浮気ではないのですよ」 和泉はさりげなく 「知られまいといちめんに霞をこめて隔てていらした花だすけれど、 私は捜し求めて香りどころか美しい花の色も見て参りましたのよ」 宮さまとご一緒でしたからという気持ちがあろうか。 そこで公任が突っつく 「霞が立ちこめて、人の行き来を止めている白河の山荘、その名も白河の関と同じ。強いて立ち入ってもいいのでしょうか」 おりしも、前夫道貞が陸奥に下向する、その地の歌枕に掛けて、夫のことはどうだ"白河の関を尋ねる"などと言っては誤解されますよ、と触れてみる 返歌は 「行く春が惜しく、引きとめたい思いでつい白河のお邸に参ったのです」 一、二句、夫との別離を悲しむ心情が率直に歌われている。 この「いづれの宮にかおはしけむ・・・」の冒頭詞ではじまる歌群は よほど有名だったらしく、 「公任集」にもほぼこの順序で載っている。最後の和泉の歌はなし。 (ちなみに、この歌の前に赤染衛門が大江一門として心配した歌も載せておきます) 道貞去りてのち、師宮に参りぬと聞きて、 「うつらはで しばし信田(しのだ)の 森を見よ かへりもぞする 葛の裏風」 返し 「秋風は すごく吹くとも 葛の葉の うらみ顔には 見えじとぞ思ふ」 赤染「心変わりして師宮のところへ行ったりしないで、 しばらくあの人の様子を見ていてごらんなさい。 ひょっとしたらご亭主はあなたのところへもどってくるかもしれないから」 「信田の森」は和泉の国の歌枕。和泉守である道貞を暗に指す。 葛の裏葉は、葛の葉」は風に吹かれるとひらひらと裏返り、白い葉裏が目立つので「かへりもぞする」と続け、「返り」に「帰る」が掛けられる 和泉「たとえ秋風が淋しく吹いても、あの人に飽きられても、 私は恨めしいそぶりはすまいと心に決めているのです」
和泉式部と師宮との仲に、世間がかなり騒いでいる様子が伺えます。
もっとも、紫式部は身持ちがいけないと批評していましたが、
すらすらと口から詠んでいく才能という歌の感じも
当たっているように思います。
すらすらと口から詠んでいく才能という歌の感じも
当たっているように思います。
ところで、これからの梅雨の季節頃を描いた源氏物語「ははきぎ」の巻では、
いわゆる「雨の夜の品定め」という場面があります。
浮気な女という話。
いわゆる「雨の夜の品定め」という場面があります。
浮気な女という話。
平安時代は通い婚です。
理想の妻にはなりませんが、
女も相手が来なかったら、結構自由のように思ったりもします。
理想の妻にはなりませんが、
女も相手が来なかったら、結構自由のように思ったりもします。
しかし、蜻蛉日記のように、
夫が来なくなったのを嘆く日記もあるので、不思議です。
夫が来なくなったのを嘆く日記もあるので、不思議です。
身分の高い人との結婚は
女性の方がひたすらに待つ時代だったのでしょうか。
女性の方がひたすらに待つ時代だったのでしょうか。
時代は和泉式部より前ですが「伊勢」もすごい人だったです。
紫式部が書いた「朧月夜」と「紫の上」の違いなども考えてしまいますが、
今も昔も女性の個人差だったのかもしれませんね。
今も昔も女性の個人差だったのかもしれませんね。