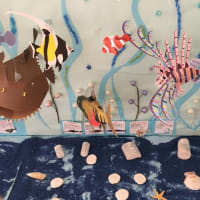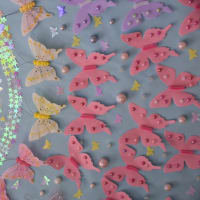今日、日本新薬のMRさんが、日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会記録集というパンフレットを持ってきてくれました。私の参加しなかった今春の学会での、好酸球性副鼻腔炎に関する発表の要約です。詳しい内容については、もう一つのブログ”好酸球性副鼻腔炎”の方に書きましたので、ここでは、個人的なことをひとつ追加です。
パンフレットの内容をざっと見ていて、”好酸球性副鼻腔炎モデルマウスにおけるデキサメタゾンペシル酸エステルの作用”という題の発表があったのですが、その参考文献”Development of a murine model of chronic rhinosinusitis.” の共著者の最後のひとりBolger WEという名前に眼が止まりました。
Bolgerと言う名前に、心当たりがあったのです。私がスウェーデンにいる頃、ビルという若いアメリカ人が、同じ施設にやってきました。初めは私が指導して、数ヶ月間、一緒に副鼻腔炎の研究を行ったのですが、お互いに若く、小さい子供を連れての海外留学で、なおさら親近感が持てました。でも帰国してからは、アメリカの学会で一度会っただけで、その後20年近く、音信もありませんでした。それでも大学にいる頃は、英語の学術雑誌もたくさん読んでいましたので、副鼻腔炎の画像診断などの論文の著者に、彼の名前を見つけることがありましたが、開業してからは、それもなくなっていました。
そのビルの名字が、Bolgerです。世界で副鼻腔炎を専門にしている先生は、耳鼻咽喉科の他の分野に比べて多くありません。その中で、Bolger、ビルというのはウィリアムですから、ファーストネームのWも合っています。これはビルではないかと思って、インターネットで調べると、まさしく、あのビルでした。
そして、論文の共著者の最後の一人は、そのグループのリーダーであることが多いです。ビルの現在の所属は、彼が卒業した医科大学だということまで分かりました。もしかしたら、母校の教授になっているのかも知れません。しかも、この論文の内容は、あの頃一緒にやっていた仕事の延長です。懐かしくまた嬉しく、当時のことを思い出しました。