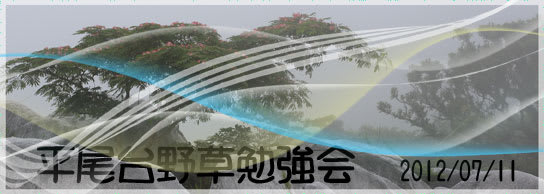
雨で何度となく出かけて帰るそんな中一日の晴れ間下見へ
キヌガサダケに、夢中で開花を逃がしたのではと
心配しましたが間に合ったようです。
エゾニガクサ「シソ科」
ニガクサにそっくりなのですが全体の毛が多い
藪の中の小さな花で見逃して
しまいそう。


シオデ雌花 ホウライタケ ツマミダケ
ムラサキ、タカサゴソウ、カキランなどが山頂では
咲いていました。
ヒオウギ
今年初めての咲き始めです。
11日早朝の森へキヌガサダケの様子を主人に見て来て頂き、その間に
お弁当を受け取りに志井へ戻る。大急ぎで戻ると開花株はナシとのこと
残念可愛い姿をお見せできなくて、
思い切ってヤマアジサイの観察へお天気も持ちそう・・みなさん雨具
は、バッチリ安心して出発です。


スズサイコ
スズサイコは北海道から九州、朝鮮・中国に分布する多年草。
日当たりのよいやや乾いた草地に生育する。花序は茎の先や上部の葉腋から出て
、2~3cmの総花柄があり、集散状にまばらに花をつける。
花冠は黄褐色で裂片は開出し、無毛で長さ5~8mm。副花冠は直立し、
卵形、鈍頭で蕊柱より短い。
花期は7~8月。花は早朝に開き、日が当たると閉じる性質がある
ヤマホトトギス
林緑や明るい林床に生育し、草丈は高さ1mほどになる。茎の毛は下向きに生えている。
やや小型の花を茎の先に散房花序に着ける。花被片の反曲するのが良い特徴である。
ホトトギス属の大部分の種には花被片の下部にオレンジ色の斑紋があるが、
この種の花にはこの斑紋がない。花は2日間咲く。花期は8月中旬から9月中旬である。
主に関東から西の太平洋側に分布する。
マルバハギ
前回に続き沢山の花を付け始めています。
写真:釘宮
![]()
いよいよヤマアジサイす。
雨がポツリ、ポツリと落ちてきます。
ヤマアジサイ


少し急ぎましょう。
アカショウマ「ユキノシタ科」
山地の林下に自生する多年草。名前の由来は、花茎の基部が赤みを帯び、
小葉のつき方が薬草のショウマ(升麻)に似ることから名付けられた。
円錐花序をだし、小さな花を穂状に多数つける。葉は互生し3回3出複葉、
小葉は長卵形で縁には重鋸歯がある。
ドリーネの縁などに生えるので藪に遮られ
見つけにくい植物です。
撮影:松島![]()

オオカモメヅル「ガガイモ科」
花梗も小花柄も花と同様の赤紫に染まり、白い伏した短軟毛が散生する。
ただしこの毛はほとんど目立たない。
小花柄は咲くまでに伸び、開花している花では花径の1.8から2倍程度に伸びて真っ直ぐになっている。
1.2cm程度の小さなはな。
小雨の中かさをさしながらの小さな花の撮影は大変です。
ノブドウ「ブドウ科」
落葉つる性木本
日本各地の山地や野原に生える。茎の基部は木質になり、つるは長くのびてジグザグに曲がり、
節はしばしは肥厚する。葉は互生し、直径4~13cmのほぼ円形で、
普通3~5裂する。基部は心形で、鋸歯があり、表面は無毛。裏面は淡緑色。葉に対生して集散花序をだし、
淡緑色で直径約3mmの小さな花を多数開く。花弁は5個で卵状三角形。果実は球形で、
花期は7~8月
撮影:鎌田
![]()


ムラサキシキブ「クマツヅラ科」
北海道南部から南西諸島に分布し、朝鮮・中国・台湾にも分布する落葉の低木。
ヤブムラサキより、星状毛は少なく、早期に脱落する。
春の時点では、ヤブムラサキと区別しにくいことがあるが、
星状毛が小さく、茎の地肌が見える。
頂芽の部分には、密に星状毛が残る。
初夏に薄紫の花を付ける。
撮影:鎌田・桃坂

トチバニンジン「ウコギ科」
トチバニンジンは、古くに日本に帰化したもので、
中国の何欽吉(かきんきつ)という人が
薩摩領内で薬草採集しているときに発見したものです。
地上部は、朝鮮ニンジン(御種ニンジンまたは、単にニンジン)によく似ていますが、
地下部が全く異なっていて驚き、
その後に「和人参(わにんじん・日本特産の人参)」として、よく知られるようになりました。
根を採取のためあまり見られなくなりましたが
生息を確認でき良かったです。
撮影:松島
ダイコンソウ「バラ科」
多年草、北海道~九州の山地や丘陵の林のふちなどに生える。
全体に柔らかな毛が密生し、高さ50~80cmになる。根生葉は羽状複葉、長さ10~20cm。
頂小葉は広卵形でとくに大きく長さ3~6cm。普通3裂し、縁は低い歯牙となる。
側小葉は小型で大小ふぞろい、1~2対で、付属小葉片がまじる。茎葉はほとんど単葉となり、
上部ほど切れ込みが少ない。茎と葉にはあらい毛がある。径1~2cmで黄色の花がまばらに咲く。
花の中心部に柱頭が多数ある。花柱には関節があり、花のあと花柱の先は柱頭が残り、
関節の部分で強くS字状に曲がる。
これもこんき初めてです。
アキノタムラソウ「シソ科」
多年草本州~九州の山野の道ばたなどに生える
葉は対生し、3~7個の小葉からなる奇数羽状複葉。下部の葉には長い柄がある。
茎の上部に長さ10~25cmの花穂をだし、長さ1~1.3cmの青紫色の唇形花を数段輪生する。
花冠の外側には白い毛が多い。花期は7~11月
撮影:釘宮
山肌に出る頃から雨足が激しく前方確認が出来ないほどでした。
1班桃坂班は
きっちりと
最後まで離れずきれいに行動されていましたが
後はバラバラ~この様な時ほど人数確認が大切です。
日ごろ班別行動をしている事を生かして
行動してほしかったです。
何はともあれ怪我人もなく無事帰る事が
出来ました事感謝します。
次回はお休み
8月8日(第2水曜日)
9:30分自然の郷発ですお間違いのない様お願いします。

















