
国立公文書館の平成31年春の特別展「江戸時代の天皇」記念講演会です。講師はお二人です。
お一人目は藤田 覚さん(東京大学名誉教授)、江戸時代の天皇研究は1970年台後半から始まり平成になってから盛んになってきました。
・江戸時代の天皇は後陽成天皇から明治天皇まで12代でうち8代が譲位です。
・天皇家の石高は3万石、公家全体でも11万6千石しかなく、朝廷財政・御所造成・臨時儀式費用は幕府丸抱え。
・年号は公家から提案して、幕府が選定し、朝廷が伝統な改元手続きにより決定、幕府が周知。改元の日は、幕府が選定した日。
・女性の天皇が明正天皇・後桜町天皇と二人いますが、一時的で跡継ぎが現れたら退位、肖像画がない。
・後桃園天皇に後継ぎが無くて、閑院宮家から養子を迎えて光格天皇(9歳)が継承。現在の天皇家。
・光格天皇が16歳のころから近臣の助けを受けながら、300年以上途絶えていた朝廷儀礼や神事を再興した。大嘗祭もその一つ。
・死後に光格天皇の称号を贈られる、「諡号+天皇号」になったのは954年ぶり。
⇒近代天皇制の起点となる。
知らなかっただけかもしれませんが、ずっと続いていた思っていた儀式が18世紀から19世紀にかけて復活したようです。
お二人目は、君塚直隆さん(関東学院大学国際文化学部教授)です。欧米の君主制を研究されています。今回。江戸時代(17~19世紀)の欧州の状況を説明していただきました。
・欧州でも「男系男子」にこだわっていましたが、日本と違って一夫一婦制、近親の結婚が続き子宝に恵まれなかったようです。











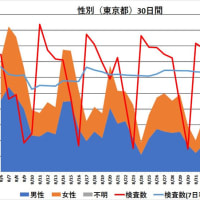
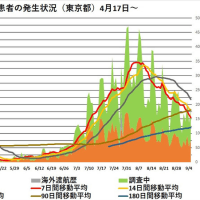
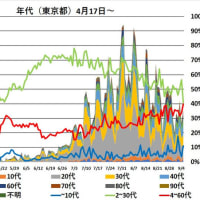
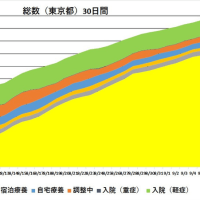
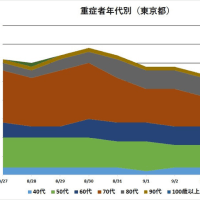
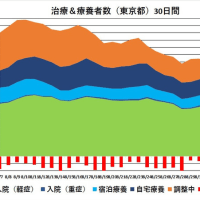
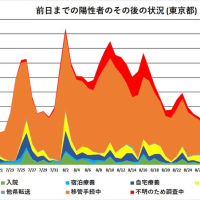
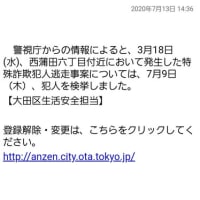
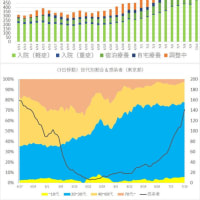
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます