
帝京大学総合博物館の企画展示「カビ展-医真菌学研究への誘い-」のイベントの最新研究講座 カビと闘う研究者たち!の「遺伝子工学と水虫」を見に行きました。講師は山田剛(帝京大学医真菌研究センター准教授)先生です。
先生は、NHKのガッテンの「水虫」特集にも出演されました。そのエピソードも含めた1時間のお話でした。
真菌とは、広い意味のカビ(酵母やキノコを含む)をあらわす医学用語です。生物科学の分野では「菌」または「菌類」とも呼ばれます。その種類は約10万種以上にものぼり、未知のものを合わせると150万種にも及ぶと考えられています。
水虫ですが、感染しても痒みを感じないことがあり、番組では自覚症状のない35人中8人が感染してました。水虫菌(白癬菌)が表皮に棲みついて、その下の真皮まで行かないからだそうです。真皮に到達すると免疫作用が働くとともに痒みがでてくるそうです。
以前は、プールや共同浴場で感染すると言われてましたが、水虫菌(白癬菌)は感染力が弱く、家庭で自覚症状のない家族がばらまく菌で感染する方が多いと考えられてます。
水虫は治療可能な病気です。症状が治まっても薬を塗り続けないと菌が無くならないそうです。爪が白くなる水虫は内服薬でないと治療は難しく、薬が肝臓に負担がかかるので皮膚科のお医者さんに行って下さい。











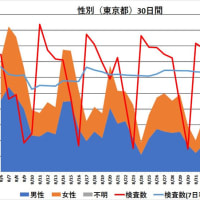
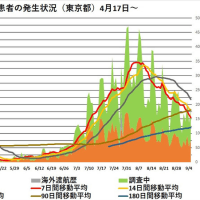
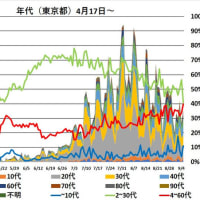
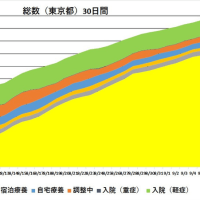
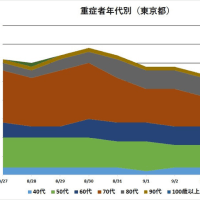
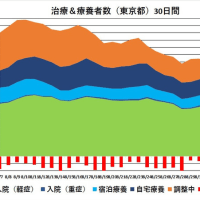
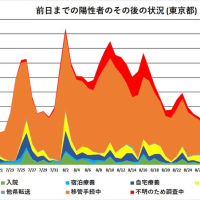
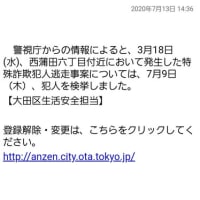
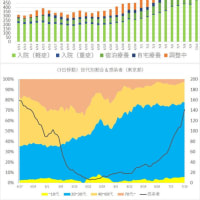
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます