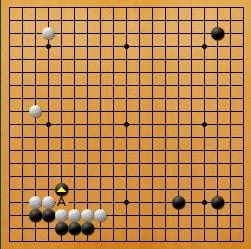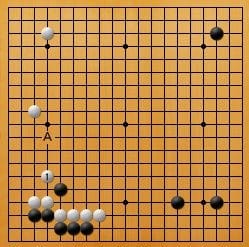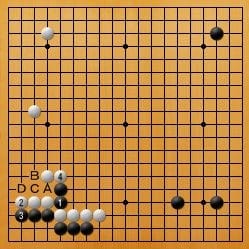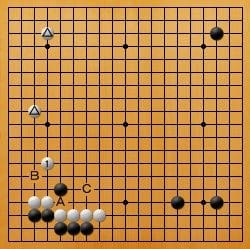皆様こんばんは。
本日は紀尾井町こども囲碁道場で講師を務めました。
私の担当は30級~26級クラスです。
参加者の年齢層は、4歳~13歳ぐらいだったと思います。
囲碁には「線の交わる所に交互に打つ」「相手の石を囲むと取れる」といった基本ルールがありますが、とりあえずそれらは覚えたという子供たちが対象ですね。
ただ、覚えたと言っても、大半の子供はいきなり実戦を打って完璧にこなすことはできません。
その最たるものが終局でしょう。
囲碁が難しく感じる点としてよく言われるのは、どうすればゲームが終わるかということですね。
例えば、将棋なら王様を取られたら負け、と言えば誰にでも簡単に理解できますが、囲碁では少し難しいです。
ただ、概念を説明するだけなら非常にシンプルです。
自分の番で、着手すると自分が損をすると感じた場合はパス(手番を相手に譲る)できますが、2人が続けてパスをすると終局になるのです。
終局の概念は決して難しくないことだけは、理解しておいて頂きたいところですね。
難しいのは、入門者・初心者同士が実戦で終局することです。
打つと損になるからパスする、ということは簡単な理屈ですが、これが最初はなかなかできないものです。
敵陣の中に打てる場所を探したり、自陣を埋めてしまったり・・・。
これを乗り越えるための何より大事なことは、とにかく数を打つことです。
終局間際の局面を何度も経験することで、自然と流れが掴めてきます。
ただ、完全に独力では練習すら難しいので、そこは指導者の手助けが必要ですね。
今回の教室では、保護者の方の中で希望者された方は子供に混じって参加することができます。
そこで、大人の対局も見て回りましたが、やはりそちらのほうが自然に終局の形ができていましたね。
理屈を考えたり数字を意識することには、ある程度年齢が上の方が有利です。
その代わり、直感に従って打つということは苦手な傾向があり、あれこれ考え過ぎて失敗することが多いように思います。
完璧な形で終局するためには、生き石と死に石の判定が必要です。
特に難しいのが中手(ナカデ)であり、有段者ですら時々間違えることがありますね・・・。
ですが、最初の内は中手まで気にしなくても大丈夫です。
とりあえず自然にパス2回で終わることができれば立派な終局です。
そこまでできれば、囲碁を覚えたと言って良いでしょう。
ところで、今回ちょっと驚いたことがあり、参加者の子から「どうしたらプロになれますか?」と聞かれました。
まだ覚えたてのはずですが、そこまで囲碁が好きになってくれたことは嬉しいですね。
本当にプロを目指すにしろ、趣味として楽しんでいくにしろ、きっと良い出会いをしたのでしょう。
なお、明日と明後日も続けて講師を務めます。
明日の講座のメインは眼と欠け眼の概念です。
これが分かれば、自然な終局にぐっと近づくでしょう。
本日は紀尾井町こども囲碁道場で講師を務めました。
私の担当は30級~26級クラスです。
参加者の年齢層は、4歳~13歳ぐらいだったと思います。
囲碁には「線の交わる所に交互に打つ」「相手の石を囲むと取れる」といった基本ルールがありますが、とりあえずそれらは覚えたという子供たちが対象ですね。
ただ、覚えたと言っても、大半の子供はいきなり実戦を打って完璧にこなすことはできません。
その最たるものが終局でしょう。
囲碁が難しく感じる点としてよく言われるのは、どうすればゲームが終わるかということですね。
例えば、将棋なら王様を取られたら負け、と言えば誰にでも簡単に理解できますが、囲碁では少し難しいです。
ただ、概念を説明するだけなら非常にシンプルです。
自分の番で、着手すると自分が損をすると感じた場合はパス(手番を相手に譲る)できますが、2人が続けてパスをすると終局になるのです。
終局の概念は決して難しくないことだけは、理解しておいて頂きたいところですね。
難しいのは、入門者・初心者同士が実戦で終局することです。
打つと損になるからパスする、ということは簡単な理屈ですが、これが最初はなかなかできないものです。
敵陣の中に打てる場所を探したり、自陣を埋めてしまったり・・・。
これを乗り越えるための何より大事なことは、とにかく数を打つことです。
終局間際の局面を何度も経験することで、自然と流れが掴めてきます。
ただ、完全に独力では練習すら難しいので、そこは指導者の手助けが必要ですね。
今回の教室では、保護者の方の中で希望者された方は子供に混じって参加することができます。
そこで、大人の対局も見て回りましたが、やはりそちらのほうが自然に終局の形ができていましたね。
理屈を考えたり数字を意識することには、ある程度年齢が上の方が有利です。
その代わり、直感に従って打つということは苦手な傾向があり、あれこれ考え過ぎて失敗することが多いように思います。
完璧な形で終局するためには、生き石と死に石の判定が必要です。
特に難しいのが中手(ナカデ)であり、有段者ですら時々間違えることがありますね・・・。
ですが、最初の内は中手まで気にしなくても大丈夫です。
とりあえず自然にパス2回で終わることができれば立派な終局です。
そこまでできれば、囲碁を覚えたと言って良いでしょう。
ところで、今回ちょっと驚いたことがあり、参加者の子から「どうしたらプロになれますか?」と聞かれました。
まだ覚えたてのはずですが、そこまで囲碁が好きになってくれたことは嬉しいですね。
本当にプロを目指すにしろ、趣味として楽しんでいくにしろ、きっと良い出会いをしたのでしょう。
なお、明日と明後日も続けて講師を務めます。
明日の講座のメインは眼と欠け眼の概念です。
これが分かれば、自然な終局にぐっと近づくでしょう。