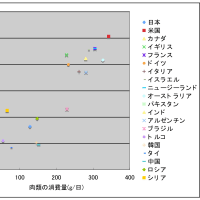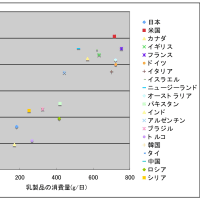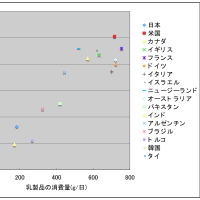先週,2005/2/16は,色々な意味で長く私の記憶に残ることだろう.この日は,地球温暖化防止のための国際協定である 京都議定書 が,発効した日である.
もちろん,京都議定書には色々な問題がある.アメリカは批准していないし,インドや中国はノーカウントである.また,日本の地球温暖化防止策は全くうまくいっておらず,すでに,当初目標よりもだいぶ二酸化炭素の排出量は増えていることも,新聞やTVのニュースをにぎわしている.やはり,短期的には,省エネルギー/環境負荷低減の協力者へのインセンティブを十分に考慮した施策,長期的には技術的な戦略が必要であると思う.
しかし,この議定書の発効は,地球環境に関して,政治的にも社会的にも新しい第一歩であることは間違いないだろう.
私自身にとっても,2005/2/16は,記念すべき日となった.京都議定書発効の数時間前に,母校の学長室で,博士号の学位記を授与されたのだ.私の学位論文は,二酸化炭素の削減に関わるものであり,その学位授与式の日に京都議定書が発効したことはある種の因縁かもしれなと,友人の研究者にメールしたところ,その友人からは「因縁と言うより、さらに発展させなさい、ということじゃないでしょうか。」と叱咤激励された.
とにかく,この日を「新しい出発の日」と考えて,次の第一歩をふみだそう.
もちろん,京都議定書には色々な問題がある.アメリカは批准していないし,インドや中国はノーカウントである.また,日本の地球温暖化防止策は全くうまくいっておらず,すでに,当初目標よりもだいぶ二酸化炭素の排出量は増えていることも,新聞やTVのニュースをにぎわしている.やはり,短期的には,省エネルギー/環境負荷低減の協力者へのインセンティブを十分に考慮した施策,長期的には技術的な戦略が必要であると思う.
しかし,この議定書の発効は,地球環境に関して,政治的にも社会的にも新しい第一歩であることは間違いないだろう.
私自身にとっても,2005/2/16は,記念すべき日となった.京都議定書発効の数時間前に,母校の学長室で,博士号の学位記を授与されたのだ.私の学位論文は,二酸化炭素の削減に関わるものであり,その学位授与式の日に京都議定書が発効したことはある種の因縁かもしれなと,友人の研究者にメールしたところ,その友人からは「因縁と言うより、さらに発展させなさい、ということじゃないでしょうか。」と叱咤激励された.
とにかく,この日を「新しい出発の日」と考えて,次の第一歩をふみだそう.