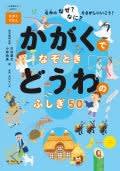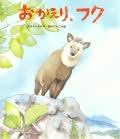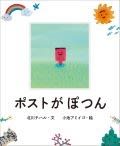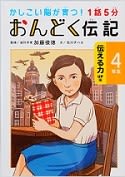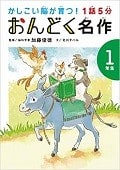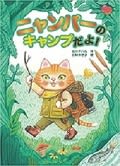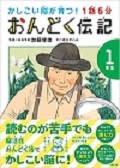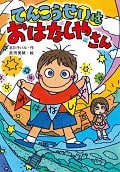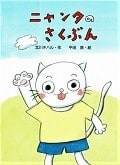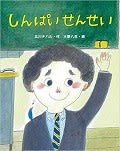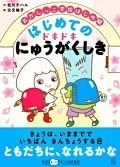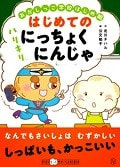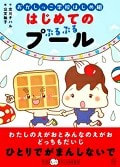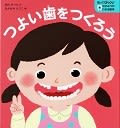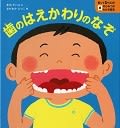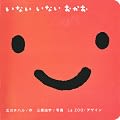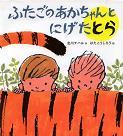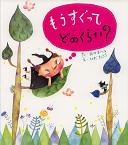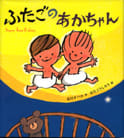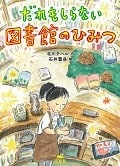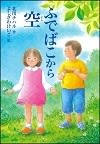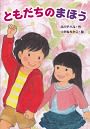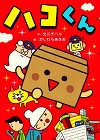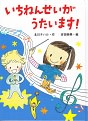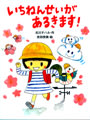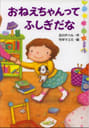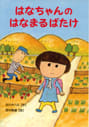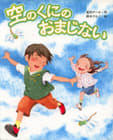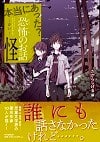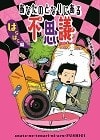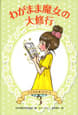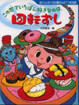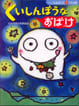子どものころから思ってました。あかちゃんって、不思議なちからがあるみたいって。母親になったいまも、そう。それで、このおはなしを書きました。生まれたばかりのふたごが、お母さんの寝顔を見ながら「かわいいね」ってしゃべったり、お父さんを探すため、夜の病院を冒険したり。はたこうしろうさんが絵筆をとってくださって、ふたごの「やっほー」と「うふふ」は、とびきりごきげんなスーパーミラクルベイビーズになりました。やったあ!
■マザーズブック あ・そ・ぼ<キンダーブック2 付録> 2008年6月号 あ・そ・ぼネットワーク掲載
絵本やおはなしをつくるとき、願うことがあります。それは、わたしの書いた物語の「おしまい」が、読んでくれた誰かさんにとって、すてきなできごとの「はじまりはじまり~!」になりますように…ということです。
たとえてみれば、こんなこと。
本を読んだ子、あるいは読んでもらった子が、あるとき、あるおはなしの、ある場面を思いだし、ふと、まねをしてみたくなる。
くちびるをつきだして、タコタコ星人のダンスなんかをソロソロユラーリ、おどけておどってみたりする。
すると、よっぱらって帰宅した父ちゃんが、わけもわからずまねをして、オカンムリの母ちゃんがふきだして、ふたりはアレレ、いつのまにやらナカナオリ…なんてことになったらば、それはもう、作者のあずかり知らぬ物語の「はじまりはじまり~!」になるのです。
わたしの書いたおはなしは印刷されて、何千何万、一字一句もたがわない本の形になりますが、それを読んでくれた方たちの、その後の現実世界のできごとは、唯一無二の物語。
いったいどんな物語が、はじまるのかな? いえいえ、わたしがなにを書こうとも、なんにもはじまりやしないかな? それは神のみぞ知る境地。
できれば、わたしのおはなしのおしまいが、読者のみなさんの幸せなひとときのはじまりになりますようにと願わずにはいられません。
そこでわたし、とろりとろりと考えました。自作の本からひろがる、いろんなあそび。
クイズ・まねっこ・なりきり、ゲーム。歌や手あそび、楽器あそび。お絵かきごっこ、親子で工作タイムも、おもしろそう…。
小さな読者さんから大きな読者さんまで楽しめちゃうあそびをと、欲ばる作者が、じつは、いちばんあそんでいるのかも?
これまで、読みがたりをメインに、おはなしライブを年に数回催しました。
これからは、もっとおはなしあそびを取り入れて、さらに楽しいイベントにしていきたいな。自治体からのお声がけで、子育て応援事業にも参加の予定。
かつて、わたしが保育士だったころ、「子どもとどんなふうにあそべばいいの?」と悩むママさんたちに出会いました。
子どもも大人もハッピーになれちゃう時間を、絵本やおはなしの世界をとおして、お届けできたらうれしいです。原稿も、ちゃーんと書きつつ、母親業も、どうにかこうにか、こなしつつ。
■京都新聞 2007年12月18日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
幼いとき、ふしぎなこと、わからないことがいっぱいでした。
あのころの私には、飽きるほど、ひまな時間がありました。身のまわりのものごとに、のんびりと触れながら、いつのまにか、ぼんやり考えあぐねていたのでしょう、いろんな「なぜ?」にぶつかって、まわりの大人に、よくものを尋ねるこどもでした。大人はなんでも知っている、そう思いこんでいたのです。
幼さゆえに、「なぜ?」をうまく伝えることが、できないときもありました。すると爪をかんだり、家の畳にぺたんと座り、窓越しに庭の松を途方に暮れて眺めたり。
つたないなりに、なんとか疑問を投げかけることができたとしても、ときとして、大人の口からこぼれる言葉は難解で、誰もがわかったような顔なのに、どうして私の心には、ストンと落ちてくれないの、と寂しくなったものでした。
小さな娘の好奇心は、ただ納得したい一心で、「なぜ?」のこたえを探して求めていたけれど、問いかけてみた相手から、「それは当たり前のことですよ」「きまりきったことだから」と、話の幕を引かれれば、当たり前ときめたのは、いったいぜんたい誰なのか、謎は深まるばかりとなったのです。
あのころのふしぎのひとつをモチーフに、絵本をつくりました。まほうつかいのポポちゃんシリーズ三作目『もうすぐってどのくらい?』(絵 ひだきょうこ/岩崎書店)です。
「もうすぐ」は、その場しのぎにちょうどよい便利な言葉であるけれど、幼いこどもたちにとってはどうでしょう。ふだん耳にはしていても、いまひとつピンとこない、ふしぎな言葉のように思います。
「もうすぐ楽しいことがやってくる」と聞いたなら、「もうすぐ」が具体的にいつなのか、知りたくてたまらないのがこども心。絵本の中の主人公と、その心にそって、楽しみながら書きました。そのじつ、不安もあったのです。幼い読者が納得できる「もうすぐ」のこたえって、あるのかなあ、と。
さいわいに、主人公は、みずからこたえを見出しました。なんてことない結末です。とはいえ、当たり前ですませずに、「なぜ?」と向きあう人の心には、手探りでつかみ得た、ふしぎのこたえの喜びをわかちあえるものでしょう。
さて大人になったはずのこの私、ふしぎなこと、わからないことがまだまだいっぱいあるのです。考えだせば不安や迷いもあるけれど、そのさきに、自分なりのこたえを見つけるしあわせが、きっと待っているのだと、いま、仕事部屋の小窓から、亀岡の夏空をぼんやり眺め、思っています。
■京都新聞 2007年8月28日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
さきごろ、絵本『ふたごのあかちゃん』(ひさかたチャイルド)を上梓しました。登場するのは生まれたばかりの男女の双子。しゃべります。歩きます。真夜中の病院で大活躍するスーパーベイビーズ!です。この現実ばなれした赤ちゃんの話を書いたのは、私が現実に赤ちゃんを生み育て、その小さな体に秘められた大きな力にビックリしたことがきっかけです。
はじめて子を授かったとき、妊娠悪阻で食事も水も喉を通らず、緊急入院することになりました。ミイラのようにやせ枯れていく私とうらはらに、豆粒ほどの赤ちゃんは元気に育ちつづけてくれました。母体の弱さに負けない命に、どれほど励まされたことでしょう。
無事に誕生したその娘、なぜか生まれてすぐには泣きませんでした。彼女は静かに看護士さんに体をふかれ、銀色の月のように輝く無垢の瞳で私をじっと見つめていたのです。「ふうん、これがお母さんか」というような顔つきで。新しい命の神々しさに、赤ちゃんよりもさきに私のほうが泣きました。
退院後はうってかわり激しく泣く娘でした。ほとんど昼寝をせず、泣き声で意思を伝え、要求し、不満を訴え、周囲の大人の生活どころか世の中さえひっくり返しそうな勢いでした。その一方で唐突に、「あはははは」と大人びた笑い方をしてみせたり、何の飾りもない壁に熱心に声をかけ、手足をぱたぱたふってみせたりするのです。
「赤ちゃんには、予想以上の特殊な力があるのかな」と眺めても、あどけないその姿に、まさかの疑問は、たちまち幸福感にかすみました。いえ、もしかして、彼女はこちらの心を見透かして、わざと赤ちゃんらしくふるまっていたのかもしれません。
思えば、赤ちゃんの愛らしさと不思議さ(不可解さ、というべきか)にふりまわされ、そして救われた日々でした。かえりみて気づくのです。親が、この世に不慣れな赤ちゃんを、大切に守り育ててきたことは、結果的に赤ちゃんが、子育てに不慣れな親を守り育ててきたことでもあるのだな、と。
とにもかくにも、赤ちゃんの未知なる力について、わくわく想像するうちに『ふたごのあかちゃん』はできました。はたこうしろう氏が、かわいらしい双子を愉快に描いてくださって、魅力的な赤ちゃんパワー全開です。各所の読み語りの会で、この絵本にふれた子が、「すっげぇ!」「赤ちゃんなのに、なんで?」と目を丸くするたび、私は心の中でつぶやきます。
そうよ、赤ちゃんってすごいのよ。そしてだれもがみんな、偉大な赤ちゃんパワーをふりまいて、この世に生まれてきたんだよ。
■京都新聞 2007年5月8日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
「俺が出てくる話を書いてよ」
自称「若かりし頃は松田優作」M氏がたびたび私に言うのです。気安い兄のような人。
「物語を書くにはネタがなくちゃ。ちょっと変わった事件とか」
「事件なァ……。おぅあるある!」
M氏は憂いを帯びた横顔で、クリスマス・イブの思い出話をはじめました。
「何年前やったかな、娘が寝たあと、嫁はんがお札を包んどうねん。サンタのプレゼント買う暇のうて、かわりに現金を娘の枕元に置いとくゆうてな。けど、そらあかんやろ、贈り物やねんから。俺、あわてて家中探してな、台所にあったチキンラーメン、包んでん。ほな次の朝、娘が泣いとうねん。包み紙、びりびりに破いてな、ラーメン、ごみ箱に捨てとうねん。あれは、えらい事件やったヮ」
……サンタクロースって、子どもにラーメンをプレゼントしたりするのかなあ……?
泉下で優作サンも泣いてるョ、なんて笑いつつ、しばし想いを馳せました。
サンタの贈り物を心待ちにしていた、娘さんの大ショック。
子への懸命な愛が空振りしちゃった父ちゃん、M氏の落胆。
捨てられたチキンラーメンだってかわいそう。クリスマスには、チキンがもてはやされたりするのにさ、チキンラーメンは、そっぽを向かれちゃうなんて。
さらにM氏には気の毒ながら、この事件は、童話向きでないように感じました。
とはいえ、創作の力をもってすれば、既存のクリスマス童話とは一味ちがったものができるかな。ものすご~く現実的で、はちゃめちゃだけど、愛にあふれた家族の物語が生まれそう……。
そんなこんなを心のすみであたためていたところ、M氏と天のお達しか、出版社から「明るく愉快な絵童話を」と、嬉しい依頼が舞いこみました。
そして書きあげたのが最新刊『うちゅういちのタコさんた』(国土社)です。タコ焼き屋の父ちゃんと、トラック運転手の母ちゃん、元気な関西生まれの女の子、たまこファミリーの物語。
この物語を書くにつれ、主人公たまこの気持ちに触発されて、自らのおさない記憶が呼び覚まされていきました。
そういえば、私はサンタさんからプレゼントをもらったことがなかったなァ。それでも別段気にとめず、のびのびとすごしていたのはなぜかしら?
もしかして、クリスマスにも動じない、超現実的な家族から……目には見えない贈り物を、受け取っていたのかもしれないな。
■京都新聞 2006年12月5日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
▼クリスマスの衝撃
幼い頃のこと。十二月生まれの私に母から誕生日の贈り物がありました。包装紙には、赤服姿の爺様が、うじゃうじゃ笑っているのでした。そして夏生まれの兄も同じ日に、同じ包装紙の贈り物をもらうのだから不思議でした。
「お兄ちゃんは、夏にプレゼントがあったのに。なぜまたもらえるの?」
「今回のはクリスマス・プレゼントよ」
答える母に、聞くこと再び。
「私のは、クリスマス・プレゼント? それとも誕生日プレゼント?」
「ふたつぶん、まとめてあるんだよ」
えっ! 私の大事な記念日が、あやしげな赤服さんのイベントにまとめられてしまうなんて……。しかも包装紙からして、どちらが主役か一目瞭然。
ヒドイヨヒドイ、赤服爺。生身のあなたは家に一度もきてくれず、おまけに誕生日のじゃままでするつもり?
▼タコ焼きの衝撃
結婚を機に関西に住みはじめた私は、タコ焼きの大歓迎を受けました。
① 昼食にと夫が台所でタコ焼きを作りだした。(自家用タコ焼き器があるなんて。そもそもタコ焼きって、ゴハンになるの?)
② 近所のママさんグループによる「タコ焼きパーティ」の開催。(全員myタコ焼き器持参。朝から夕まで焼いて焼いて食べつづける…)
③ 道端のいたるところにタコ焼き屋。(競争率激しそう。やっていける?)
④ スーパーの冷凍食品売り場に、チンするタコ焼きジャンボパック。(おやつに弁当に大好評!?)
自分には無関係だと思っていた事がらが、ふとした出会いの衝撃で、きわめて私的で重要な意味を持ちはじめることもある――そんな変哲のない日常が、おかしくて、愛おしくてなりません。
絵童話『うちゅういちのタコさんた』の主人公、大阪生まれのたまこにも、作者とは一味違う「タコ焼きとクリスマスの衝撃」がありました。それについては、たごもりのりこさんの描かれた、愉快なタコタコ星人にお会いになっていただければわかります。
■こどもの本<日本児童図書出版協会> 2006年12月号 私の新刊掲載
子どもって、魔法つかいみたいだなぁ、と思うことがあるのです。たとえば、それは、こんなこと。
パン生地みたいに柔らかい、ちっちゃな指で、上着のボタンをつかむ幼い子。
ボタンは、めざすボタンホールにふれるけど、いつのまにやら、あともどり。
あんまり引っぱるものだから、いびつなトンネル口となりはてたボタンホールは待ちぼうけ。手を貸そうにも、ひとりで成しとげたい幼子(おさなご)は、泣いたり、かんしゃくを起こしたり……。
ところが、どうして。まわりの大人が肩をすくめ、見守ることしかできぬなか、ある日とつぜん、幼子が、不思議な力を得たかのように、ボタンはトンネルをすりぬける。成就のよろこびに満ち満ちた、小さなすがたを、魔法つかいと見まがう瞬間です。
ほんのささいなことであれ、きのうまで叶わぬことが今日叶う。そんな幼子のひとこまが、わたしはとても愛おしく、手がける絵本の仕事にも、投影されていくようです。
シリーズ絵本のポポちゃんも、まさに幼い魔法つかい。わずかに使える魔法にしても、泣けばたちまちとけちゃうていたらく。
それでも君は、りっぱな魔法つかいのはしくれよ、なぁんてペンをとるうちに、ふと気づいたことがありました。
魔法において肝心なのは、その方法ではなく、条件なんじゃあないかしら?
呪文を唱えりゃ即叶う、そんなたやすいものでなく、「こうしたい、ああなりたい」と、いちずに望む意思がなによりで、その意思をつらぬくことができるのは、まわりの愛情あればこそ。
ポポの場合、まがりなりにも、その力を発揮できるのは、魔法の道具(杖やほうき)にこめられた、両親の大きな愛が支えになっているからと、感じられてなりません。
できぬ子が、それでもボタンにしがみつき、結果、かけちがいの服を着るはめになったとしても、それをともに見届ける誰かがそばにいることが、いまだ叶わぬステップへ、はずみをつけていくのでしょう。
いちずな意思と周囲の愛。これこそ魔法のような瞬間が、生まれる条件なのかもしれません。
先月、神戸の園で、ポポちゃん絵本の新作『まほうのケーキをつくりましょ』(岩崎書店発行)を読みました。手製の杖をふりながら、「ルルリルルリラプンのプン!」と、園児らと呪文を唱え、いっしょにあそんだ楽しい時間。
まばゆい笑顔のかれらもまた、作者に勇気をあたえてくれる、偉大な魔法つかいなのでした。
■京都新聞 2006年8月8日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
「肉屋の看板の絵の豚は、なぜ笑っているのか?」
高校へ入学した春、担任の先生が、自己紹介されたときのお言葉です。哲学の先生でした。
テツガク先生は、生徒の名前を覚える気がないらしい――しばらくすると、そんな噂がたちました。
どうやら事実のようでした。
名簿順の面談で、ひとり前の加藤さんが欠席した日、制服に〈北川〉と名札をつけた私にむかい、「加藤さん、加藤さん」と微笑む姿は、ふしぎに感動的でした。 とうとう私は最後まで、「加藤さん」になりすましてしまったほどでした。
おそらく先生は、生徒の名を覚えるよりも、看板の豚くんへの探求に熱心だっただけなのでしょう。周囲の噂や、人目なんて気にとめず、ひたすらに我が道を行く先生は、後光がさして見えました。
いっぽう私は、人目が気になる年頃でした。学校から、「読書ノート」というものが、新入生に配られました。読んだ本の所感をまとめ、担任に提出するためのものでした。
ある日、テツガク先生が、私のノートを見つめ、おっしゃいました。
「キミ、もっと年齢相応の本を選んではどうだろう?」
私は、恥ずかしさにうつむきました。
世界に名だたる文豪の著作を読みふける級友たちの中にいて、〈高校生へのオススメ文学〉なるものをひろげてはいたものの、実際、私のノートには、大好きな絵本や童話のことが、びっしりつらねてあったのです。なんて幼稚な生徒と思われたことでしょう……。
当時、私の心には、「童話作家になりたいな」という夢が、すでにもぞもぞとありました。でも、どうすれば叶うのか、全くわかりませんでした。ただ気まぐれに、好きなものを読んだり書いたり。やっぱり幼稚だなァと、自覚は充分あったのでした。
笑われたってしかたない――私はついに顔をあげ、テツガク先生に、たよりない夢を伝えました。
「絵本や童話、児童文学の勉強をしていきたいと思っています」と。
「ならば、どんどん読むといい」
先生は、あっさりとうなずいて、エンデやトールキンの名を挙げながら、私向きの本をいくつか紹介してくださいました。
生徒の名前は、ひとつひとつ覚えてなくても、ひとりひとりの心には、真摯に向きあうことを忘れない、テツガク先生なのでした。
あれから何年もたちました。
先生、その後、豚くんへの探求は、いかがでしょうか?
私はあのころと、たいして変わらぬ心のままに、夢の行く手を追っています。
■京都新聞 2006年3月24日金曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
こどものころ、家の書棚にあったのは、母が時折ひろげる「家庭の医学」と父の仕事に関する専門書ばかりでした。
わたしは読みたい本を求め、学校の図書室に足しげく通うこととなりました。
小学五年生のある日のこと。担任の先生が、ずっしりとした重みのある本を手渡してくださいました。灰谷健次郎さんの『太陽の子』。鮮烈でした。この本で、はじめて〈戦争〉を見たように思いました。
テレビっ子世代であるわたしが、しばしばかじりついた画面のなかに、戦争を伝える報道はありました。けれど目前の惨状は、その後、せかせかと切り替わるコマーシャルや、ゆかいな別番組の登場で、現実みを帯びることなく混乱のうちに消えました。
戦争の恐ろしさや愚かさを真に伝えてくれたのは本でした。不思議です。前掲の本は、戦場を直接描いているのではありません。けれど、ブラウン管から押し寄せる、まさしく起こったはずの戦闘シーンよりもまざまざと、その実体を心に焼きつけていったのは、なぜなのでしょう。
かえりみて、思うのです。
活字をたどり、物語にひたり、登場人物たちの痛みや祈りを分かちあう、そういった、ゆるやかな時間のなかで、フィクションを超える真実を心に深く受けとめた、ということではないのかな、と。
ものごとを理解するのに大切なこと――現実をただ眺めるだけでなく、心のまなこでとっくり見つめることを、あのとき教わったような気がします。
暮らしが高速化していくなかで、本を読むゆるやかな時間は貴重です。急ぎ足では見落としがちな、ささいで、そして、かけがえのない風景を心のまなこにのびのびと映しだしてくれるから。
その心地よさを知ってから、わたしはテレビからしだいに遠ざかっていきました。一方的なスピードで、見せられたり聞かされたりすることに、心がすりへるような寂しさを覚えるようになったのです。
本はまことに寛容です。
読み手の好みや気分にあわせ、リズムやテンポをまかせてくれます。言葉の意味に迷ったり、趣旨がのみこめなくて立ちどまってしまうとき、あともどりや繰りかえしを心ゆくまで許してくれます。ページを伏せても、つづきを流さず、いついつまでも静かに待ってくれるのです。なんてすてきな友でしょう。
じっくりと世界を見つめるように本を読む、このゆるやかで幸福なひとときが、わたしはとても大好きです。
■京都新聞 2005年11月29日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
長女が小学校に入学して、まもないある日のことでした。すでに童話を書く仕事をしていた私に、「ここを舞台に書いてみたら」という小牧和彦校長先生のお言葉。亀岡の山に抱かれて佇む小さな東別院小学校は、「山のした小学校」として、この夏発売された私の最新刊『きらちゃん ひらひら』(小峰書店)にお目見えすることとなりました。
といってもフィクションです。入学への期待に胸をふくらませ、未知の世界に飛びこんでいく純真無垢なきらちゃんと、きらちゃんのはずむ体、ゆれる心をまるごと迎える先生たちとの出会いに満ちた物語。それは、私の思い出の中から生まれました。
出身の愛知県の小学校に入学した当初、席につくのがもどかしく、気ままにうろつく幼い私を、学校中の先生が、両手を広げて受けとめてくださいました。あのときの私には、「学校ってどんなところ?」という好奇心、そして、「本当にここにいてもいいのかな?」と居場所を求める不安な気持ちが、ないまぜになっていたように思います。
私にとって小学校は、得体の知れない巨大な社会の入り口でした。そこには、規律という名の風がびゅうと吹き、驚くばかりの知識の花が、咲きみだれていたのです。
風に打たれ、花にみとれて飛び歩く傍若無人な迷い子を抱きあげてくれた腕の中。そこが、私の心の居場所でした。誰かに決められた席でなく、自分自身が納得しながら見つけた拠り所。幸福な体験は、のちのち、自分の居場所を何度も見失ってしまうたび、くずれ落ちていきそうな心の支えとなりました。
こどもにとって、家庭に居場所があることは幸せです。けれども、社会にだって居場所がなければ、なかなか巣立つ勇気をふるえるものではありません。
さまざまな事情から、こども同士で遊ぶ時間や、存分に摩擦をおこす空間が減少しているご時世です。だからこそ思うのです。こどもたちと社会をつなぐ場所として、小学校が、さらに魅力あふれる入り口であればいいのにな、と。
巨大な社会の入り口で、居場所を見つけた日々があったから、いまの私がここにいる――とすれば、『きらちゃん ひらひら』は、童話を書いている私の原動力の物語。
こどもたちのみずみずしい魂が安堵して、羽ばたく勇気を得られるような出会いの恵みを祈りつつ、私はこの物語を書きました。
これから入学する子に、いま通う子に、きらちゃんの元気な声が届くならばうれしいな。
「さあ行くよ。心の居場所をさがしにね!」
■京都新聞 2005年8月16日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
新年度が始まって、早ひと月がたちました。なにかと心浮き立つ出会いの春、できれば真の自分に上乗せして、周りからよく見られたらいいのにな……と、つい背伸びをしてしまうことって、ありませんか?
この春発売された私の新刊『パーティーがはじまるよ』の主人公ポポがそうでした。ポポは魔法使いの女の子。森でパーティーが始まると知り、魔法でおしゃれに挑戦するのですが大失敗。ね? こんな経験、きっと誰にでもあるでしょう。おしゃれでなくても、自分をよく見せようと頑張った結果が裏目に出てしまうようなこと。でも、落ちこむことはありません。人間万事塞翁が馬、未来は素敵に予測不可能です。ポポが行ったのだって、実は、おしゃれなんて必要なしの「どろんこパーティー」でしたから。(これから絵本を手にする子たちには、どうぞ内緒に!)
ポポは重いマントやブーツや帽子を脱ぎ捨て、どろんこ沼に飛びこみます。見栄や束縛を払いのけ、混沌とした明日にだって、ありのままの姿で飛びこんで行けばいいじゃない、そんな作者の想いが、ラストで体現されたのでした。
けれども、私は子どもたちに、作者の秘めたる想いなどそっちのけで、ページをめくってほしいと思います。ただ絵本の世界に夢中になって、「おもしろかった!」と遊んでもらうことこそ本望です。
幼年時代の心地よい絵本体験は、豊かな心の栄養となって沈殿し、時を重ねるごとに、ゆっくりと結晶していくことでしょう。やがて大人になり、思い出の本と向き合う時、新たな発見を見出すことがありますが、それは自分の内なる結晶が、多面的な見方を可能にしたからかもしれません。
良質な子どもの本というのは、一生涯にわたり新鮮な出会いの喜びを与え続けてくれるもの。私が心から作りたいと願うのは、そのような本なのです。
この絵本は、幼い子らが存分に楽しめるようにと、オペレッタ(歌劇)のリズムを意識し、ファンタジックでシンプルなストーリーに仕立てました。読み語りをしてくださる大人の方にも楽しんでいただけましたら幸いです。
おしまいに少し気になっていることを。子どもの遊びから、どろんこが疎遠になりつつあるようです。理由の多くは「汚れるから」、「汚すと叱られてしまうから」。
泥には土と水のぬくもりがあります。大地の恵みを肌に伝え、自然への情緒を育むどろんこ遊び。お日様のもとで興じる子らの笑顔は、さながら太陽のよう。小さな地上の太陽が、いつまでも、未来を明るく照らしますように。
■京都新聞 2005年5月10日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
運命の人と巡りあうおまじない、乗り物酔いや緊張しないおまじない――いろんなおまじないがあるけれど、どうしてそれが生まれたの? って、ついつい想いを馳せたくなるものです。
『空のくにのおまじない』は、どんなに泣いている子も笑わせちゃう、とっておきのおまじない。
このおまじないを見つけたのは、小学一年生の男の子、ユウくんでした。
ユウくんが名づけた『空のくに』は、はたから見れば、なんてことのない原っぱです。けれど、自然をそのまま利用した秘密基地だともいえます。
秘密基地というのは、完全に隠された場所であるかどうかということよりも、そこが当人にとって心の解放区=魂のセイフティーゾーンとなり得るかが絶対条件だと思うのです。
そして、子どもというのはおそらく秘密基地を完全に独り占めにしたいとは望みません。遅かれ早かれ、秘密の時間を共有できる誰かを喜んで招き入れようと扉を開いているものではないでしょうか。
もちろん、招待する相手は、誰でもいいってわけではありません。
ユウくんが『空のくにの招待状』を手渡す相手は、クラスでいちばん泣き虫の女の子、あすかちゃんにほかなりませんでした。だって、あすかちゃんには、ユウくんが見つけたおまじないが必要で、ユウくんにも、そのおまじないを唱えてくれるあすかちゃんの存在が、とても大切なんだもの。
ちょっぴりしょっぱい涙のぬくもりを二人が確かめあったとき、『空のくに』で、ささやかな奇跡は起こるのです。
わたしはこの物語を、自らのハンディキャップやコンプレックスと向き合いながらも、まっすぐ生きようと輝くふたりのために、なかば祈りにも似た気持ちで書きあげました。
いいえ、ユウくんとあすかちゃんのためだけでなく、つまずき転びながら、いまを生きるすべての方へのエールです。
この本は、作者からの『空のくにへの招待状』です。
■子どもの本<日本児童図書出版協会> 2004年11月号 私の新刊掲載
物語を書く際、私は〈ぬくもり〉という感覚を、ことに大切に描きます。
日なたのぬくもり、木のぬくもり、動物とふれあう時のぬくもりなど、様々なものがありますが、一番伝えたいのは、人と人との間で日常感じるあたたかさ。
手をつないで歩いたり、肩をならべて食事する、そういった何気ないぬくもりを、家庭や社会の中で得る人は多いでしょう。
ところが、この幸せを噛みしめながら生きることは、案外難しいかも知れません。
時間に流され、慌ただしさに追い立てられ、肌を通して感じるぬくもりが心に届く間もなく過ぎてゆく――そんな人もいるのでは?
心配は子どもたちにも及びます。
子どもたちの心には、ぬくもりが確かに届いているでしょうか。寒さに震えてしまう時、あたためてくれる手が、いつもそばにあるでしょうか。
ぬくもりとは、命のあたたかさ。
暖房器具では、人の心まで暖めることはできません。自分と異なる体温を受け止めて、人は他者の命を確認し、互いの心をぬくめ合っているのです。
便利なモノに囲まれたこの国は、しだいに人と人との距離があき、他者の体温を感じる機会は減少の途をたどっているように思われます。そのことが、人間関係だけでなく、親子関係のもろさにも拍車を掛けているのでしょう。
けれど、たとえわずかでも、心に届くぬくもりは深く沁み、決して消え失せないと信じます。
光を浴びた葉が、やがて土にかえり森を育てていくように、人の心にかえったぬくもりも、生きる力を育む土壌となっていくのです。
デビュー作『チコのまあにいちゃん』を書きながら、思い出したことがありました。
冷えた晩、足の裏を兄のふくらはぎにくっつけて眠りについた幼い頃の記憶です。とうに忘れていたけれど、あのぬくもりは、私の心の片隅でひっそりと息づいていたのです。
私たちは、数え切れないぬくもりを肌に感じながら生きています。形をなさないものだけに、忘れてしまいがちではあるけれど。
私は物書きとして、己の力も省みず、〈ぬくもり〉に文字という形を与えようと試行錯誤を重ねています。
永遠に冷めないぬくもりを、読者のもとへ届けたい。心にじんわり沁みわたる物語を生み出したい。
そしてもし、自らのそばにある〈現実のぬくもり〉に、私の本を読んでくれた誰かが、ふと気づいてくれたなら――作者として、こんなに嬉しいことはありません。
■京都新聞 2004年10月19日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載
童話とは子ども用のものである、と考える人は多いでしょう。侮るなかれ、童話は、「子どもから楽しめるもの」、つまり万人の文化であると言っても過言ではありません。
そこに繰り広げられる物語は実にシンプルで分かりやすく、そのうえ生きていく力となり得る希望や勇気、想像力をかきたてる遊び心が含まれています。その魅力に取り憑かれ、私は童話を書いているのです。
これまでに出版された私の本の中には、いずれもハンディキャップを抱える子が登場します。
ことさら障害問題に取り組もうなどという気負いはありません。誰しも多かれ少なかれ、また程度の差こそあれ、ハンディキャップやコンプレックスを持っているものではないでしょうか。いわば、それが個性なのです。
かけがえのない個性をありのままに受け止め、自他を愛そうとすることは、人間の自然な心の働きです。時として、それを忘れてしまうことが少なからずあるとしても。
忘れた思いを呼び覚ましてくれるものとしても、童話は老若問わず必要なものかもしれません。〈大人〉〈子ども〉といった枠にとらわれず、私は作者として読者に、本の中に登場する個性あふれる子どもたちを、身近な存在、友だちのように感じてもらえたらいいなと思っているのです。
本とは、いま自分が生きる場所から安心して別世界へと旅立てる軽らかな扉です。世界には様々な文化をもった国があるように、人間の生きる姿も千差万別。それを知ることは個々の世界を豊かに広げ、やがて社会を潤す一条の流れとなっていくでしょう。
昨今、活字離れに歯止めをかけようと種々の動きが活発です。その中で、ファンタジーの人気は、ますます高まっているようです。
現実を離れ、とてつもなく大きな夢を見せてくれたり、胸躍る冒険を疑似体験させてくれる物語は、私も大好き。
けれど、平凡な日常、日々繰り返される、ありふれた生活の中にも、きらきらと輝く宝物のような一瞬はあるのです。
すぐそばにあるぬくもり、手に届くきらめき、生きているという確かな手ごたえ、明日を信じて、ほんの少しだけ踏み出す勇気、それらをできれば多くの人に感じてほしいと願いつつ、私はこれからも童話を愛し、新たな物語を紡いでいこうと思うのです。
あなたも童話の世界を楽しんでみませんか。一人では気恥ずかしいと思われましたら、お子さんやお孫さんたちとご一緒に。
■京都新聞 2004年6月15日火曜日 丹波ワイド版 口丹随想掲載