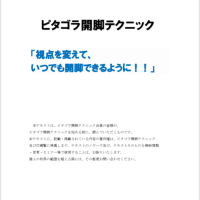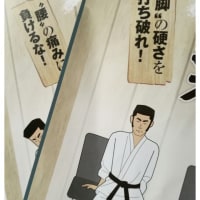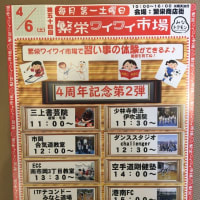テコンドーの型
タングントゥルについて
ここから述べるのは、
全て僕の見解であり、
正解であるかはわかりません。ご参考に。
テコンドーでは、タングントゥルの型で、始めて上段突きが出てきます。
よくよく、考えてみると
おかしくないですか?
実戦を考えるのなら、
上段突きを練習する方が早いのでは。
実際の組手練習でも、
ボディをパンチするより、顔にパンチする方が圧倒的に多いですよね?
では、なぜ⁉︎
通常、手を上にバンザイすると、腰って反っててしまいやすくなりますよね?
→それは、上段への突きでも、おこりうることです。

そして、コンヌンソギ(立ち方のこと)
の後ろ足の部分が崩れる。そうすると、足元が崩れるので、重心が安定しない。
なので、コンヌンソギの上段突きは、腰が崩れやすいのです。
なので、まずは
白帯で、中段突きのコンヌンソギを練習するわけです。
まずは、腰が反りにくい体勢で、突く練習を行い、重心を下に安定させるのをやるわけです。
そうすると、
なぜ、8級課題で始めて
上段突きが出てくるかわかりますよね?
そして、上段受け
(チュキョマッキ)が出てくるのも、同等の理由です。
多分、抵抗なく型をこなしていると出てこない疑問です。
でも、
普通に考えると
なぜ、上段突きが出てこないの?
という疑問から
テコンドーの型の素晴らしさが見えてきます。
タングントゥルについて
ここから述べるのは、
全て僕の見解であり、
正解であるかはわかりません。ご参考に。
テコンドーでは、タングントゥルの型で、始めて上段突きが出てきます。
よくよく、考えてみると
おかしくないですか?
実戦を考えるのなら、
上段突きを練習する方が早いのでは。
実際の組手練習でも、
ボディをパンチするより、顔にパンチする方が圧倒的に多いですよね?
では、なぜ⁉︎
通常、手を上にバンザイすると、腰って反っててしまいやすくなりますよね?
→それは、上段への突きでも、おこりうることです。

そして、コンヌンソギ(立ち方のこと)
の後ろ足の部分が崩れる。そうすると、足元が崩れるので、重心が安定しない。
なので、コンヌンソギの上段突きは、腰が崩れやすいのです。
なので、まずは
白帯で、中段突きのコンヌンソギを練習するわけです。
まずは、腰が反りにくい体勢で、突く練習を行い、重心を下に安定させるのをやるわけです。
そうすると、
なぜ、8級課題で始めて
上段突きが出てくるかわかりますよね?
そして、上段受け
(チュキョマッキ)が出てくるのも、同等の理由です。
多分、抵抗なく型をこなしていると出てこない疑問です。
でも、
普通に考えると
なぜ、上段突きが出てこないの?
という疑問から
テコンドーの型の素晴らしさが見えてきます。