現在、井山名人と挑戦者河野臨九段の囲碁名人戦が真っ最中、内藤女史も大活躍。(朝日
は別に社会面や政治面だけではない。でも僕は15年以上前から、とってもいないし、読ん
でもいない。ゴメンナサイ、、、。)三局終わって、河野九段が一つリード。(七局全部
見せて!心情的に応援している、秀行先生のお弟子さんの高尾山じゃなくて高尾さんも
頑張って!)前に「いつの間にか半目勝ちをしてしまう名人」と書きましたが、ここに、
「あえて難しい手を打たなくても、平易なわかりやすい手で」と書き加えても良かった。
打てないのではない、打たないのだ。最近の若い棋士の碁は、序盤も布石も吹っ飛ばして
いきなり最初から難解な戦いに突入して、そのまま終局まで雪崩れ込むという碁が多い。
昔の、チクリン時代の大竹九段や林海峰九段の頃のような、四隅の定石から辺に移って、
ややしばらくあってから、いよいよ石と石がぶつかります、(それも辺が多かった、、、)
なんて事はない。(だが当時でも藤沢秀行さんだけは、異星人のように、現在に通じるよ
うな碁を打っていた、、。)
プロなら、ある局面で、どんな難しい手でも読める。(ほっといても、読めてしまう。)
ただ、実際の、ある局面で、そんな難しい手を、わざわざ選択して打つかどうかは、別の
問題なのだ。囲碁は難しさを競う競技ではない。(難しいのと、難解なのとは、違う。)
定山渓の第三局でも、解説の武宮正樹九段は、あえて難しい手を選択し続ける両対局者
に、困惑しているように思えた、、。(実は、若い頃、武宮先生の入門書で囲碁の勉強を
始めました、、、。「宇宙流」好きでした、、、。まるで建築みたい、、、。)
最近の若い人の建築の設計は、わざわざ難しい設計に持ち込もうとしているだけなので
は?と思えるものも少なくない。 (それにしては大事なところは「ポッカリ」抜けていた
りして、、、。囲碁なら簡単に負けてしまいます。投了です。)
設計って、難しさを競うためにあるのではないのでは? 渡辺一夫さんは、「狂気につい
て」と言うエッセイの中で、人間の愚かしさについてふれている。後世の人から見たら、
「何で、こんなことを?」としか思えないようなことを、ヨーロッパのお姫様たちは繰り
返していた、、、、。(山本学冶先生は、東大で渡辺一夫さんの講義を聞いていた様な気
がする、、、。入学試験で「ガルガンチュア物語」出たもの。)
は別に社会面や政治面だけではない。でも僕は15年以上前から、とってもいないし、読ん
でもいない。ゴメンナサイ、、、。)三局終わって、河野九段が一つリード。(七局全部
見せて!心情的に応援している、秀行先生のお弟子さんの高尾山じゃなくて高尾さんも
頑張って!)前に「いつの間にか半目勝ちをしてしまう名人」と書きましたが、ここに、
「あえて難しい手を打たなくても、平易なわかりやすい手で」と書き加えても良かった。
打てないのではない、打たないのだ。最近の若い棋士の碁は、序盤も布石も吹っ飛ばして
いきなり最初から難解な戦いに突入して、そのまま終局まで雪崩れ込むという碁が多い。
昔の、チクリン時代の大竹九段や林海峰九段の頃のような、四隅の定石から辺に移って、
ややしばらくあってから、いよいよ石と石がぶつかります、(それも辺が多かった、、、)
なんて事はない。(だが当時でも藤沢秀行さんだけは、異星人のように、現在に通じるよ
うな碁を打っていた、、。)
プロなら、ある局面で、どんな難しい手でも読める。(ほっといても、読めてしまう。)
ただ、実際の、ある局面で、そんな難しい手を、わざわざ選択して打つかどうかは、別の
問題なのだ。囲碁は難しさを競う競技ではない。(難しいのと、難解なのとは、違う。)
定山渓の第三局でも、解説の武宮正樹九段は、あえて難しい手を選択し続ける両対局者
に、困惑しているように思えた、、。(実は、若い頃、武宮先生の入門書で囲碁の勉強を
始めました、、、。「宇宙流」好きでした、、、。まるで建築みたい、、、。)
最近の若い人の建築の設計は、わざわざ難しい設計に持ち込もうとしているだけなので
は?と思えるものも少なくない。 (それにしては大事なところは「ポッカリ」抜けていた
りして、、、。囲碁なら簡単に負けてしまいます。投了です。)
設計って、難しさを競うためにあるのではないのでは? 渡辺一夫さんは、「狂気につい
て」と言うエッセイの中で、人間の愚かしさについてふれている。後世の人から見たら、
「何で、こんなことを?」としか思えないようなことを、ヨーロッパのお姫様たちは繰り
返していた、、、、。(山本学冶先生は、東大で渡辺一夫さんの講義を聞いていた様な気
がする、、、。入学試験で「ガルガンチュア物語」出たもの。)



















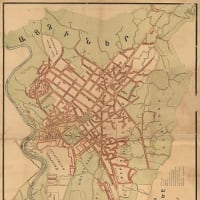






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます