直江廣治さんの『屋敷神の研究-日本信仰伝承論-』(吉川弘文館1977年4版)
という本に「ニソの杜」のことが書かれています。(416~417ページ)

近来学会の注目を浴びてきたのは、福井県大飯郡大島村(現大飯町大島)の
「ニソの杜」の信仰である。従来の調査によって明らかにされた点を要約すれば
ほぼ、次のごとくになろう。
(1) この村は24宗家といわれる家の先祖たちによって開拓されたと伝え
られ、これらの宗家は、家の祖霊と信じられるものを「ニソの杜」にお
いて祀っている。
(2) 「ニソの杜」は30ヵ所あり、それぞれ同族団を中核として「ニソの講」を
結成して祀っている。
(3) 杜はタモ・椎・椿などの古木を中心に、竹藪などで周囲をおおわれ、
神聖視されている。
(4) 旧霜月22日から23日にかけて、輪番頭屋制で祭りが営まれ、献餞を
調えるための「ニソ田」が付属している。
(5) 杜に接して墓地の存する例、また杜が古墳をなしている事例も認めら
れる。

(頭屋の夫婦でしょうか?)
筆者も昭和39年夏30ヵ所の「ニソの杜」を調査してみたが、詳しい報告は後日に
譲るとして、心づいた点を指摘しておく。
(1) ニソの杜は小さな谷の頭、山の尾根の末端に位置するものが多い。杜の
大きさはニ~三畝ていどのものが多い。
(2) ニソの杜は一般の森とは樹相を異にし、その特色はタモの古木にある。
(3) 現在の民家は海に接して集まっているが、かつてはもっと山添いに「ニソ
の杜」に近く位置していた。したがって「ニソの位置」は、集家の屋敷続きの
裏山或いはやや離れた持山にというのが基本的な形であったと推定される。
(4) 小祠の存しない杜では、杜のほぼ中央にある通例タモの古木に供えものを
して祀る。したがって、特定の古木を選んで依り代として祀るのが古態で
あったと思われる。
(5) 小祠を据えている場合、中には浜石や御幣を納めただけのものもあるが、
神札の入っているものが多く、神札には地神・地之神・地主・明神・荒神
遠祖大神・山之神・大明神などの文字が書かれている。
以上のごとき「ニソの杜」の形態並びに信仰は、薩南の「モイドン」や「ウッガン」と
きわめて類似したものと考えられる。
ニソの杜 その3 につづきます。
という本に「ニソの杜」のことが書かれています。(416~417ページ)

近来学会の注目を浴びてきたのは、福井県大飯郡大島村(現大飯町大島)の
「ニソの杜」の信仰である。従来の調査によって明らかにされた点を要約すれば
ほぼ、次のごとくになろう。
(1) この村は24宗家といわれる家の先祖たちによって開拓されたと伝え
られ、これらの宗家は、家の祖霊と信じられるものを「ニソの杜」にお
いて祀っている。
(2) 「ニソの杜」は30ヵ所あり、それぞれ同族団を中核として「ニソの講」を
結成して祀っている。
(3) 杜はタモ・椎・椿などの古木を中心に、竹藪などで周囲をおおわれ、
神聖視されている。
(4) 旧霜月22日から23日にかけて、輪番頭屋制で祭りが営まれ、献餞を
調えるための「ニソ田」が付属している。
(5) 杜に接して墓地の存する例、また杜が古墳をなしている事例も認めら
れる。

(頭屋の夫婦でしょうか?)
筆者も昭和39年夏30ヵ所の「ニソの杜」を調査してみたが、詳しい報告は後日に
譲るとして、心づいた点を指摘しておく。
(1) ニソの杜は小さな谷の頭、山の尾根の末端に位置するものが多い。杜の
大きさはニ~三畝ていどのものが多い。
(2) ニソの杜は一般の森とは樹相を異にし、その特色はタモの古木にある。
(3) 現在の民家は海に接して集まっているが、かつてはもっと山添いに「ニソ
の杜」に近く位置していた。したがって「ニソの位置」は、集家の屋敷続きの
裏山或いはやや離れた持山にというのが基本的な形であったと推定される。
(4) 小祠の存しない杜では、杜のほぼ中央にある通例タモの古木に供えものを
して祀る。したがって、特定の古木を選んで依り代として祀るのが古態で
あったと思われる。
(5) 小祠を据えている場合、中には浜石や御幣を納めただけのものもあるが、
神札の入っているものが多く、神札には地神・地之神・地主・明神・荒神
遠祖大神・山之神・大明神などの文字が書かれている。
以上のごとき「ニソの杜」の形態並びに信仰は、薩南の「モイドン」や「ウッガン」と
きわめて類似したものと考えられる。
ニソの杜 その3 につづきます。



















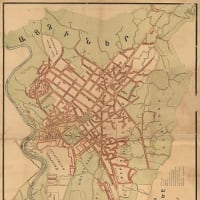






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます