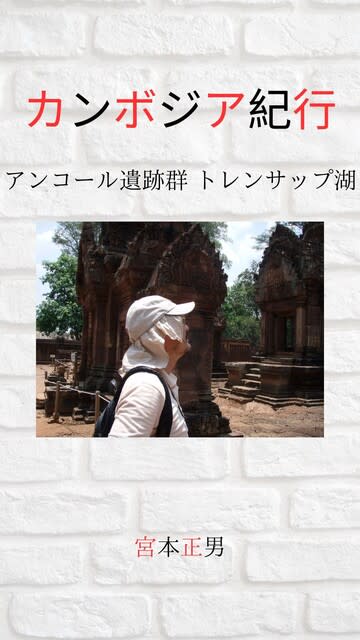
はじめに
18年前のアンコールワット紀行を編んでみた。
過去の旅は時間という竈で美味しいスープに仕上がる。回想しながら編んでいく作業はこの上なく楽しい。
アンコールワットとアンコールトムをひとまとめにしてアンコールワット紀行としている。アンコールワットは寺院でアンコールトムは王宮の意だ。
アンコール朝の中興の祖ジャヤーヴァルマン7世がチャンパに対する戦勝を記念して12世紀末ごろから造成に着手した。石の積み方や材質が違うことなどから、多くの王によって徐々に建設されていったものであると。
1933年の調査によって中央祠堂床下からブッダの像が発見された。建造物部分に仏像を取り除こうとした形跡や、ヒンドゥーの神像があることからは大乗寺院から後にヒンドゥー化したものか。三島由紀夫や開高健の作品に触発された旅でもあった。
4月とはいえ既に相当に暑い季節だ。遺跡はどこの場合もそうだがとにかく歩く。この地も万歩計をつけて歩いたが3万歩近く歩いたのではないか。暑さと肉体的疲労とでやっとの思いで辿り着いたアンコールワットだがその広大な内堀の前に立った瞬間来てよかったと思った。
600メートルもある参道を内堀の緑の水に囲まれて歩きながら、はるばるやってきたとの感慨に浸ることができた。1632年=寛永9年に日本人がこの地を訪れていたという。そして寺院の壁に次の墨書を残した。
御堂を志し数千里の海上を渡り
一念を念じ世々娑婆浮世の思いを清めるために
ここに仏四体を奉るものなり
摂州津池田之住人森本儀太夫
とある。
池田の住人森本儀太夫 がどのようないきさつで長崎から御朱院船に乗り込めたかは不明だが不思議な池田の縁を感じる。森本儀太夫自身はこの地を祇園精舎と思いこんではるばる海を渡りたどりついたという。
2025年1月31日










