先日某TV局の特集報道を観て「自出を知る権利」なる言葉とその背景にある問題や現状の一端を初めて知った。
この知る権利に関する議論は裾野が広く、門外漢の老生には初めて聞き知ることばかりだった。
議論の焦点は、第三者から提供された精子・卵子・胚を使い、生殖補助医療により生まれた子が、自分のルーツ・出所を知る権利を、どんな理由で何故、認めるか否かにあった。この問題の前提として、AID(非配偶者間人工授精)そのものを是認すべきではないとする意見もあった。いずれの議論・論点も、生命倫理・人間の出生・尊厳に関ることに繋がっているので、「自出を知る権利を認めるか否か」の問題は、法律論だけでは到底律し難いことは確かだ。
しかし、近年晩婚化等の影響もあってAIDによる出生者が年々増加(H22年度厚労省統計:人口受精による出生者28,945人、総出生人口の約2.7%)し、将来的には日本の総人口が逓減することは明白な趨勢だ。そうした将来見通しの下で、生みたくても埋めない親が、熟慮の末に生みの親・育ての親となる権利はしっかり守られるべきだし、生まれたその子が後年、自出を知る権利も認められ、擁護されて然るべきであろうと思う。但し、その場合でも、①精子等の提供者、②成人に達した以降の子と③その育ての親の同意を前提として、この「自出を知る権利」はしっかり認めらるべきではないか・・・とTV番組を観てそう思った。
この知る権利に関する議論は裾野が広く、門外漢の老生には初めて聞き知ることばかりだった。
議論の焦点は、第三者から提供された精子・卵子・胚を使い、生殖補助医療により生まれた子が、自分のルーツ・出所を知る権利を、どんな理由で何故、認めるか否かにあった。この問題の前提として、AID(非配偶者間人工授精)そのものを是認すべきではないとする意見もあった。いずれの議論・論点も、生命倫理・人間の出生・尊厳に関ることに繋がっているので、「自出を知る権利を認めるか否か」の問題は、法律論だけでは到底律し難いことは確かだ。

しかし、近年晩婚化等の影響もあってAIDによる出生者が年々増加(H22年度厚労省統計:人口受精による出生者28,945人、総出生人口の約2.7%)し、将来的には日本の総人口が逓減することは明白な趨勢だ。そうした将来見通しの下で、生みたくても埋めない親が、熟慮の末に生みの親・育ての親となる権利はしっかり守られるべきだし、生まれたその子が後年、自出を知る権利も認められ、擁護されて然るべきであろうと思う。但し、その場合でも、①精子等の提供者、②成人に達した以降の子と③その育ての親の同意を前提として、この「自出を知る権利」はしっかり認めらるべきではないか・・・とTV番組を観てそう思った。










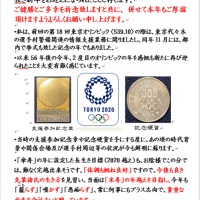


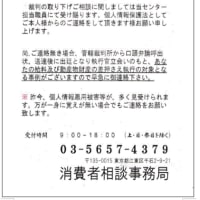
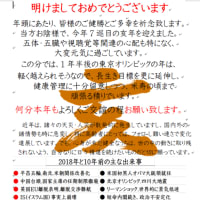
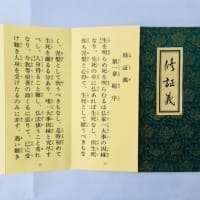
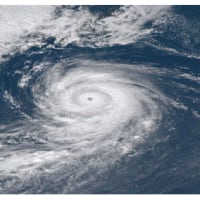


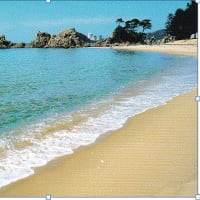
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます