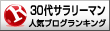話題が複数あるので少しずつ触れていきましょう。
新語新札
今日から1000円札と5000円札の絵柄が変わった新札が出回っているらしいです
(僕はまだ触れていませんが…)。どうも絵柄が変わったにも拘らず、旧キャラと新キャラのインパクトがあまり変わらないような…。
5000円札→いまいち影が薄い路線(願わくばわれ太平洋の橋とならん→全て文にまれ、歌にまれ、気骨というものこそあらまほしけれ)
新渡戸稲造と樋口一葉の名言を並べてみました。
↑こう書かれないと誰だかわからないのではないでしょうか。
ちなみに、一葉は24で亡くなっているそうですのでこの理論で行くと僕もいずれ5000円札に
載るのかもしれません。(別に載りたくもないが)
1000円札→髭。
以前の1000円担当者も伊藤博文、聖徳太子と髭揃いです。
ちなみに僕は聖徳太子の死んだ年齢を知りませんので、この理論で行くと僕もいずれ1000円札に
載るのかもしれません。(別に載りたくはないのです)
タイトルの「新語」についてはまた最後に。
精神と時の部屋
今日はバイトがありました。
ここでバイトの詳細について述べる気はあまりありませんが、
とりあえず、人の住所や年齢を打ち込んだりすることのある仕事です。
今日入力した人の中に
"1988年4月1日生まれ(44歳)"
という生年月日を持つ(入居者がそう主張している)鉄人がいました。
?? いやいや、本人がそう書いているのだから僕が気を利かせるのは野暮というものです。
まあ、時間の流れがこことは若干違うところで丹念に時間を測ったら、あるいはそういう年齢になるのかもしれません。
そんな意味を込め上記のタイトルです。
で、僕は結局どう入力したか。
説明が遅れましたが、うちの入力システムでは何も入力しないと0000/00/00生まれと同じ扱いになります。
困った挙句、そのシステムに任せたら2004歳ということになりました。
まあ、事実と違うことに変わりはないのでそれでいいのだと思います。
諭吉以前の自由
さて、本日最初のトピックスに洩れてしまった福沢諭吉。
それはともかく、彼が「自らを由とする」という意味を込めて自由という言葉ができたのだそうです。
それ以前に生きていた人は、その状態をどのように呼んでいたのか…
いわば、慶應義塾(大学)を作ったことで有名な諭吉がその一方で未来へ続く言葉をも作っていた。
時代が変われば、その心を記述する言葉が変わるのもまた必然。
さあ、皆さんも今の時代に合ったエレガントな言葉を続々と考えていきませんか?
格言なんていろいろありますが、
「過ぎたるは及ばざるが如し」
なんて
「やりすぎってのもどうよ?」
って言っているだけだし
「サルも木から落ちる」
に至っては、、、たまたま見ただけのことを大袈裟に言ったのではないかと。
最初はその事実があって、後付で格言化されたかのような印象があります。
(実際はどうだかわかりません)
それを考えていくと、今の世をちょっとだけ頭をひねって言い表せば、もうそれは格言です。
周りの皆にその日本語を普及してもらえば、瞬く間に周囲を席巻するでしょう。
大学もその勢いでできるに相違ありません。
この理論で行くと僕もいずれ10000円札に載るのかもしれません(これは載りたい)。
結論:僕は全ての札に載る資格を備えつつある。
皆も頭を絞って全ての紙幣に載る資格を捏造してみませんか?
タイトルについて
日記のタイトルとして並列に並べられる言葉はせいぜい3つ。
同シリーズとして
「待っていた男、振り払うことのできないもの、人は島嶼にあらず」
(村上春樹、ねじまき鳥クロニクル)
なんてものがありますね。
ちなみにこの作家からはそういう一見無関係なものを題名に配置しておきながら
内容をなんとなく有機的に結びつける、というノウハウを学んでいると思います。
…今日は読む人を置いてけぼりにした感のあるBlogでしたが。
まぁ、いいか。
新語新札
今日から1000円札と5000円札の絵柄が変わった新札が出回っているらしいです
(僕はまだ触れていませんが…)。どうも絵柄が変わったにも拘らず、旧キャラと新キャラのインパクトがあまり変わらないような…。
5000円札→いまいち影が薄い路線(願わくばわれ太平洋の橋とならん→全て文にまれ、歌にまれ、気骨というものこそあらまほしけれ)
新渡戸稲造と樋口一葉の名言を並べてみました。
↑こう書かれないと誰だかわからないのではないでしょうか。
ちなみに、一葉は24で亡くなっているそうですのでこの理論で行くと僕もいずれ5000円札に
載るのかもしれません。(別に載りたくもないが)
1000円札→髭。
以前の1000円担当者も伊藤博文、聖徳太子と髭揃いです。
ちなみに僕は聖徳太子の死んだ年齢を知りませんので、この理論で行くと僕もいずれ1000円札に
載るのかもしれません。(別に載りたくはないのです)
タイトルの「新語」についてはまた最後に。
精神と時の部屋
今日はバイトがありました。
ここでバイトの詳細について述べる気はあまりありませんが、
とりあえず、人の住所や年齢を打ち込んだりすることのある仕事です。
今日入力した人の中に
"1988年4月1日生まれ(44歳)"
という生年月日を持つ(入居者がそう主張している)鉄人がいました。
?? いやいや、本人がそう書いているのだから僕が気を利かせるのは野暮というものです。
まあ、時間の流れがこことは若干違うところで丹念に時間を測ったら、あるいはそういう年齢になるのかもしれません。
そんな意味を込め上記のタイトルです。
で、僕は結局どう入力したか。
説明が遅れましたが、うちの入力システムでは何も入力しないと0000/00/00生まれと同じ扱いになります。
困った挙句、そのシステムに任せたら2004歳ということになりました。
まあ、事実と違うことに変わりはないのでそれでいいのだと思います。
諭吉以前の自由
さて、本日最初のトピックスに洩れてしまった福沢諭吉。
それはともかく、彼が「自らを由とする」という意味を込めて自由という言葉ができたのだそうです。
それ以前に生きていた人は、その状態をどのように呼んでいたのか…
いわば、慶應義塾(大学)を作ったことで有名な諭吉がその一方で未来へ続く言葉をも作っていた。
時代が変われば、その心を記述する言葉が変わるのもまた必然。
さあ、皆さんも今の時代に合ったエレガントな言葉を続々と考えていきませんか?
格言なんていろいろありますが、
「過ぎたるは及ばざるが如し」
なんて
「やりすぎってのもどうよ?」
って言っているだけだし
「サルも木から落ちる」
に至っては、、、たまたま見ただけのことを大袈裟に言ったのではないかと。
最初はその事実があって、後付で格言化されたかのような印象があります。
(実際はどうだかわかりません)
それを考えていくと、今の世をちょっとだけ頭をひねって言い表せば、もうそれは格言です。
周りの皆にその日本語を普及してもらえば、瞬く間に周囲を席巻するでしょう。
大学もその勢いでできるに相違ありません。
この理論で行くと僕もいずれ10000円札に載るのかもしれません(これは載りたい)。
結論:僕は全ての札に載る資格を備えつつある。
皆も頭を絞って全ての紙幣に載る資格を捏造してみませんか?
タイトルについて
日記のタイトルとして並列に並べられる言葉はせいぜい3つ。
同シリーズとして
「待っていた男、振り払うことのできないもの、人は島嶼にあらず」
(村上春樹、ねじまき鳥クロニクル)
なんてものがありますね。
ちなみにこの作家からはそういう一見無関係なものを題名に配置しておきながら
内容をなんとなく有機的に結びつける、というノウハウを学んでいると思います。
…今日は読む人を置いてけぼりにした感のあるBlogでしたが。
まぁ、いいか。