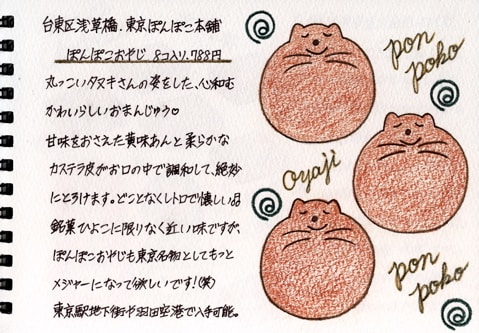こちら、自由が丘ペット探偵局 作者 古海めぐみ
19
次の日。朝から爽やかな青空になった。
しかし犬飼健太は、自由が丘の呑川緑道を預かり犬のキャバリアの散歩を
させながら心の中に靄がたち込めているのをどうにも晴らせないでいた。
ものごとの成り行きには、いつもどこか少しづつ綻びていて、慌てて留めた
シャツのボタンのしばらく進んではじめてズレていることに気づいて一から
やり直す、みたいな間の抜けた経験と似たことがよくあるものだ。
迷子犬ナナの発見の一報が調布の保健所からもたらされたのが今朝一番の
9時にこれから犬の散歩に出ようかとしていたところだった。すぐに田村
良弘に電話したが、それは自分の犬じゃないしもう関係ないからとツッケン
ドンに怒鳴られ、じゃ彼女の清水さんに連絡したいと申し出ると、一切彼女
のものは焼いて捨ててしまったのでわからないと益々ケンモホロロだった。
掛け違いー。
ちょっとした気持ちの掛け違いじゃねえか。
何云ってんだ。カワカミ犬の雑種一匹の命がかかってんだ。もしかしたら
珍しいオオカミ犬かもしれないんだ。てめいらの好きだ嫌いだの痴話喧嘩に
いくら逞しいと云ってもまだ子犬が殺されてしまうんだ。ふざけるな。健太
はつい大きな声を出していた。 気がついたら、健太は、預かり犬のキャバ
リアのリードを力まかせにグイグイと引っ張っていた。キャバリアは、植え
込みと歩道の間でうんちをしながら引きずられていた。
くうーんーーー。
おおお。悪かったよ。と慌てて健太は、手製のペットボトルでつくったバキ
ュームでうんちを吸い取った。
ナナの確認に行かなくちゃならないけど健太は実物に遭っていない。飼い主
でしか確認のしようがない。どうすることもできない自分にシャツのボタン
が最後のところで揃わない間抜けなもどかしさと徒労を感じて煙突のない蒸
気機関のようにプーと膨れて爆発しそうだった。
そして掛け違いは、健太だけでなく猫田春にも起こっていた。時間がハル
おばちゃまランチの後にさかのぼるけど、上田祐二、サチ、健太と和風カフ
ェで別れて春は、ハルさんと写真館に帰った。午後の三時に近かった。
ワインに火照っていたハルさんをソファに座らせて、冷たいお水を飲ませよ
うと1階の自販機でミネラルウォーターを買いに行っている間にハルさんが
いなくなった。
すぐに階段へ走ってみると、階段室の窓から駅前ロータリーをサクサクと歩
いていくハルさんを見つけたが追いかけても間に合わなかった。
どうして黙っていなくなったのだろう。まだ少し酔いが残っていたので風に
吹かれでも行ったのか。しかしその日の夕方になっても夜になってもついに
スタジオには姿を見せなかった。しかも仕上がりのポートレート写真と人物
画とを写真館HALのカウンターに置いたまま。せっかくあんなに喜んだ写
真を忘れて帰ってしまった。
掛け違いは、予期しない落とし穴。
春は、よく考えると注文書にハルおばちゃまの住所を書いてもらったが電話
の記入がなかった。そのときはまあ、いいかっと思っていたがこんなことに
なるなら無理しても聞いとけばよかったと思ったが後の祭りだった。
春にとってこのハルおばちゃまとの掛け違いはこれだけにとどまらなかった。
三日後にやってきたその掛け違いも落とし穴もメガトン級だった。
それは、ちょうど春が子供のスタジオ撮影を終らしてお昼にしようかという
ときだった。
五十がらみの二人とも白髪の夫婦がやってきて、「うちの母は来ていないか」
と受付に訪ねてきた。水野正と清美と名乗った。
よくよく聞いてみるとハルおばちゃまだった。
ポートレート写真を見せると、開襟シャツの夫の正がやや涙目でそうです、
これですと大きく頷いた。
「もう三日帰って来ないんで警察に捜索願いを出してきたところなんです。」
春は、小さな流氷の上に残されて荒巻く氷の海に流されていくエゾジカの子
のように孤立感と恐怖と後悔とにぐるぐる巻きになるのを感じた。
「ちょくちょくこんなことが去年からあって、母は、痴呆が始っていてそろ
そろ施設に申し込もうとしていたところだったんです。」
「では、ここに行くということは云っていたんですか。おばちゃま。」
春が信じられないという顔で聞くと、ガリガリに痩せた妻の清美が細い声で
答えた。
「お義母さんの鞄にここの開店チラシが入っていていなくなる日に渋谷から
一度電話をしてきたんで自由が丘のこの店に来てみたんです。」
「で、昔ここにあったネコタ画材店のことはおっしゃっていたんですか。
若い頃この近くに住んでいたとか・・・」
「はあ?画材店?」
水野正が驚いた顔をした。
「若いときも何も母と私は札幌生まれでずっと北海道にいました。仕事の関係
で八王子にが来てまだ十年ぐらいです。」
「では私のお爺ちゃんと交流があったという話は・・・・」
妻の清美が急に冷たい笑いを漏らした。
「だから早く施設に入れようって言ったでしょ!」と夫を睨み付けた。
「そんなこと云ったって・・お前。」
「私、知らないよ。もう。あっちこっちで作り話ばかり云い散らかして。お
義母さん。」
「病気なんだから仕方ないだろ。」
「何よ。他人にこうして迷惑ばかりかけて。」
冷たい火花が散っている中、春は割って入った。
「ちょっと待ってください。ハルおばちゃまの云っていたこと、作り話?」
「すいません。ご迷惑かけて・・」
夫婦は、われに返って頭をさげた。
19
次の日。朝から爽やかな青空になった。
しかし犬飼健太は、自由が丘の呑川緑道を預かり犬のキャバリアの散歩を
させながら心の中に靄がたち込めているのをどうにも晴らせないでいた。
ものごとの成り行きには、いつもどこか少しづつ綻びていて、慌てて留めた
シャツのボタンのしばらく進んではじめてズレていることに気づいて一から
やり直す、みたいな間の抜けた経験と似たことがよくあるものだ。
迷子犬ナナの発見の一報が調布の保健所からもたらされたのが今朝一番の
9時にこれから犬の散歩に出ようかとしていたところだった。すぐに田村
良弘に電話したが、それは自分の犬じゃないしもう関係ないからとツッケン
ドンに怒鳴られ、じゃ彼女の清水さんに連絡したいと申し出ると、一切彼女
のものは焼いて捨ててしまったのでわからないと益々ケンモホロロだった。
掛け違いー。
ちょっとした気持ちの掛け違いじゃねえか。
何云ってんだ。カワカミ犬の雑種一匹の命がかかってんだ。もしかしたら
珍しいオオカミ犬かもしれないんだ。てめいらの好きだ嫌いだの痴話喧嘩に
いくら逞しいと云ってもまだ子犬が殺されてしまうんだ。ふざけるな。健太
はつい大きな声を出していた。 気がついたら、健太は、預かり犬のキャバ
リアのリードを力まかせにグイグイと引っ張っていた。キャバリアは、植え
込みと歩道の間でうんちをしながら引きずられていた。
くうーんーーー。
おおお。悪かったよ。と慌てて健太は、手製のペットボトルでつくったバキ
ュームでうんちを吸い取った。
ナナの確認に行かなくちゃならないけど健太は実物に遭っていない。飼い主
でしか確認のしようがない。どうすることもできない自分にシャツのボタン
が最後のところで揃わない間抜けなもどかしさと徒労を感じて煙突のない蒸
気機関のようにプーと膨れて爆発しそうだった。
そして掛け違いは、健太だけでなく猫田春にも起こっていた。時間がハル
おばちゃまランチの後にさかのぼるけど、上田祐二、サチ、健太と和風カフ
ェで別れて春は、ハルさんと写真館に帰った。午後の三時に近かった。
ワインに火照っていたハルさんをソファに座らせて、冷たいお水を飲ませよ
うと1階の自販機でミネラルウォーターを買いに行っている間にハルさんが
いなくなった。
すぐに階段へ走ってみると、階段室の窓から駅前ロータリーをサクサクと歩
いていくハルさんを見つけたが追いかけても間に合わなかった。
どうして黙っていなくなったのだろう。まだ少し酔いが残っていたので風に
吹かれでも行ったのか。しかしその日の夕方になっても夜になってもついに
スタジオには姿を見せなかった。しかも仕上がりのポートレート写真と人物
画とを写真館HALのカウンターに置いたまま。せっかくあんなに喜んだ写
真を忘れて帰ってしまった。
掛け違いは、予期しない落とし穴。
春は、よく考えると注文書にハルおばちゃまの住所を書いてもらったが電話
の記入がなかった。そのときはまあ、いいかっと思っていたがこんなことに
なるなら無理しても聞いとけばよかったと思ったが後の祭りだった。
春にとってこのハルおばちゃまとの掛け違いはこれだけにとどまらなかった。
三日後にやってきたその掛け違いも落とし穴もメガトン級だった。
それは、ちょうど春が子供のスタジオ撮影を終らしてお昼にしようかという
ときだった。
五十がらみの二人とも白髪の夫婦がやってきて、「うちの母は来ていないか」
と受付に訪ねてきた。水野正と清美と名乗った。
よくよく聞いてみるとハルおばちゃまだった。
ポートレート写真を見せると、開襟シャツの夫の正がやや涙目でそうです、
これですと大きく頷いた。
「もう三日帰って来ないんで警察に捜索願いを出してきたところなんです。」
春は、小さな流氷の上に残されて荒巻く氷の海に流されていくエゾジカの子
のように孤立感と恐怖と後悔とにぐるぐる巻きになるのを感じた。
「ちょくちょくこんなことが去年からあって、母は、痴呆が始っていてそろ
そろ施設に申し込もうとしていたところだったんです。」
「では、ここに行くということは云っていたんですか。おばちゃま。」
春が信じられないという顔で聞くと、ガリガリに痩せた妻の清美が細い声で
答えた。
「お義母さんの鞄にここの開店チラシが入っていていなくなる日に渋谷から
一度電話をしてきたんで自由が丘のこの店に来てみたんです。」
「で、昔ここにあったネコタ画材店のことはおっしゃっていたんですか。
若い頃この近くに住んでいたとか・・・」
「はあ?画材店?」
水野正が驚いた顔をした。
「若いときも何も母と私は札幌生まれでずっと北海道にいました。仕事の関係
で八王子にが来てまだ十年ぐらいです。」
「では私のお爺ちゃんと交流があったという話は・・・・」
妻の清美が急に冷たい笑いを漏らした。
「だから早く施設に入れようって言ったでしょ!」と夫を睨み付けた。
「そんなこと云ったって・・お前。」
「私、知らないよ。もう。あっちこっちで作り話ばかり云い散らかして。お
義母さん。」
「病気なんだから仕方ないだろ。」
「何よ。他人にこうして迷惑ばかりかけて。」
冷たい火花が散っている中、春は割って入った。
「ちょっと待ってください。ハルおばちゃまの云っていたこと、作り話?」
「すいません。ご迷惑かけて・・」
夫婦は、われに返って頭をさげた。