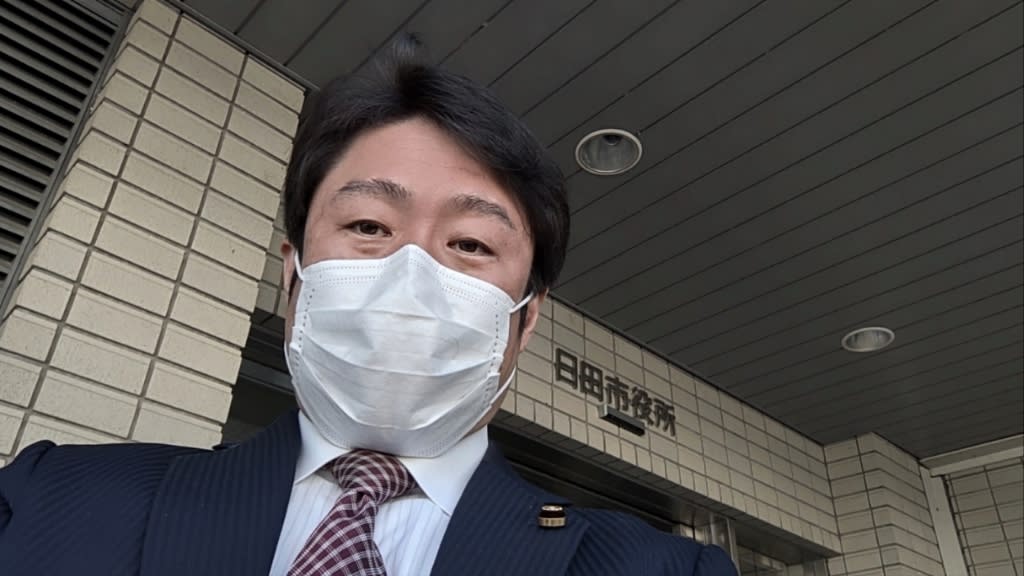令和4年10月17日(月曜日)
今日は、日田市が実施した「総合的な子ども支援拠点整備計画」についてのパブリックコメント(以下「パブコメ」という)の締切日でした。
昨年12月市議会定例会の開会日、全員協議会において素案が示された際、本年1月にパブコメを実施した上で、基本案の確定を行い、3月定例会での議案提出というスケジュールが説明されました。しかし、その通りに事業は展開せず、6月定例会の教育福祉委員会で、実施設計の予算案を提出する予定の9月定例会と並行して、パブコメを実施するという説明を受けた時には、それで、市民の意見が本当に実施設計へ反映されるのかどうか、疑問である旨を意見として述べました(そもそも、実施設計は、ハコモノ建設を前提としているようで、疑問を感じていました)。
この事業について、私は、昨年9月定例会の一般質問で「学校で長い間、子供たちと接して、子育てに大きな影響を持つ、学校現場、いわゆる教育の視点を盛り込むことが重要だ」と述べました。今回、学校現場に対しては、パブコメとは別の方法で、意見を求めるとの説明がありました。活発に意見が出るためには、整備計画案を学校の先生方が知っておく必要があります。市は、そのための工夫や努力をしたのか。それなくして、的確な意見が出るはずがありません。確認してみたいと思います。
また、今日は、先日の決算審査特別委員会教育福祉分科会について、私なりに振り返りました。
決算対象の昨年度の新規事業として「里親リクルート地域連携事業」がありました。県の補助が10分の10。当初予算250万円。決算額263万2,858円。年度途中に11回の補正予算の編成がありましたが、この分の補正はありませんでした。
えっ? まさか、予算以上の支出なのか?
市長公約の一丁目一番地「総合的な子ども支援拠点創設事業」は、当初予算66万円。これも年度途中の補正がありませんでしたが、最終予算が440,200円に変更された上で、決算額は100,822円でした。
市民の皆様への周知のための「講演会」の開催、検討委員会の委員による「先進地視察」は、ともにコロナを理由として見送っています。私は、令和3年度の当初予算の審査は、別の委員会で行ったので(総務環境委員長在任中)、迂闊にも、この予算の詳細を把握しないままでした。
なお、「里親リクルート地域連携事業」について、どんなに分厚い資料をめくっても、予算オーバーとしかならないのですが、そこは「予算の流用」という手法で対応していました。そして、その原資が「総合的な子ども支援拠点創設事業」で実施しなかった講演会と先進地視察で浮いた分ということを、審査の中の質疑で突き止めました。
決算審査において、資料中の行や列に潜む数字を追いかけ、課題や問題を発見し、質疑することが、非常に大事だと改めて認識しました。
さて、「総合的な子ども支援拠点創設事業」については、必要性があるからこそ提案したはずの講演会と先進地視察を実施しないまま、パブコメまで行い、遮二無二、事業を次の段階に進めようとしているように見えるのは私だけでしょうか。執行部からは、講演会や視察を行っていないから、事業を進められないとは思っていないという驚くべき答弁がありました。
パブコメは抜きとして、同じような事例が、過去にもありました。覚えている方は、あまりいないと思います。
上津江・中津江地区に対して、住民自治組織を立ち上げるべく、平成28年3月定例会に、新規事業「新しい公共推進事業」の予算が提案されました。その1年後、設立する組織に対する交付金予算が提案された際、事業の前提ともいえる、まちづくりを進める上での基本的な方針である地域活性化プランが策定されておらず、アイデアの具現化の場として期待をされたまちづくり会議が一度も開かれなかったという事実を捉え、手順を踏まない事業の推進にストップをかけるべく、予算を減額修正したことを思い出しました。それを分科会審査の中で、執行部にも伝えました。
なぜ、そんなに急ぐのか? 6月定例会、9月定例会の一般質問では、その視点を全面に押し出して、執行部の見解を問い質したつもりです。急ぐ理由が、「市長の公約であり、市の重要な施策」というだけでは、当然ながら納得できません。