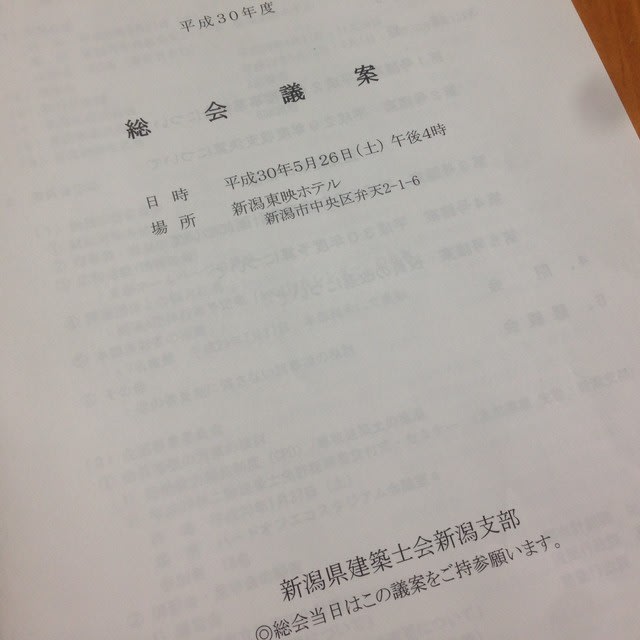
昨日、建築士会新潟支部の総会でした。
総会前には新潟市行政から、基準法の改正部分の解説や基準法の新潟市での取り扱い方についての解説、木造住宅の耐震改修における低コスト工法の紹介などのお話を聞きました。
今回の基準法の改正の特徴は規制緩和が増えた事。
小規模な店舗であれば、特殊建築物ではなく住宅と同じ規制で建てられちゃいます。
法律が緩くなったからと喜ぶ人はただの人。
より設計者の責任が重くなると捉えるのが普通です。
試される時代に突入です。
そこでありがたいのが建築基準法の解釈について。
あの難しい文章をどう読み解けばいいのかは、なかなか個人では難しい所ですが、それを新潟市がこう読み解いてくださいという解説を公開しました。

これはすでに建築士会から発売されているハンドブックの追補版みたいなものなので、合わせて読むと理解の範囲が広がります。
このハンドブックでは全国と比べてもここまで細かく整備されているものはなく、しかも平成7年の発行以来改訂を繰り返してきた歴史ある解説本です。
と、なんでここまでアピールが強いかと言えば、私もこのハンドブックの編集に携わっていたから。
ということで、設計者、法律好きの方、3冊セットでどうぞ。
建築士会新潟支部で購入できます。
そして、講習会終了後にいよいよ総会。
この総会で、4年間務めた「交流研修委員長」を退きました。
いや、絶対無理だからと断りながら、半分押し付けられたような委員長でしたが、結局2期4年間の担当でした。
あっという間でしたし、今思えば「まぁなかなか楽しかったな」という感想です。
この会で自分が何ができるのか、何を求められているのかを探り続けて終わったような感じですが、建築士会から何かを与えられるのではなく、建築士会をこうしていこうという思いを委員に伝えてからは、随分前向きにはなったかなと思います。
まずは自分が楽しんで、それが会員に伝染するようなネットワークを築きたくて、それを次の委員長に引き継ぎました。
今年度からは別の委員に所属して、別の角度から建築士会をサポートする立場になります。
引き続き、理事にもなりましたので、建築士会が目立つようにちょこちょこ発信していきます。
総会前には新潟市行政から、基準法の改正部分の解説や基準法の新潟市での取り扱い方についての解説、木造住宅の耐震改修における低コスト工法の紹介などのお話を聞きました。
今回の基準法の改正の特徴は規制緩和が増えた事。
小規模な店舗であれば、特殊建築物ではなく住宅と同じ規制で建てられちゃいます。
法律が緩くなったからと喜ぶ人はただの人。
より設計者の責任が重くなると捉えるのが普通です。
試される時代に突入です。
そこでありがたいのが建築基準法の解釈について。
あの難しい文章をどう読み解けばいいのかは、なかなか個人では難しい所ですが、それを新潟市がこう読み解いてくださいという解説を公開しました。

これはすでに建築士会から発売されているハンドブックの追補版みたいなものなので、合わせて読むと理解の範囲が広がります。
このハンドブックでは全国と比べてもここまで細かく整備されているものはなく、しかも平成7年の発行以来改訂を繰り返してきた歴史ある解説本です。
と、なんでここまでアピールが強いかと言えば、私もこのハンドブックの編集に携わっていたから。
ということで、設計者、法律好きの方、3冊セットでどうぞ。
建築士会新潟支部で購入できます。
そして、講習会終了後にいよいよ総会。
この総会で、4年間務めた「交流研修委員長」を退きました。
いや、絶対無理だからと断りながら、半分押し付けられたような委員長でしたが、結局2期4年間の担当でした。
あっという間でしたし、今思えば「まぁなかなか楽しかったな」という感想です。
この会で自分が何ができるのか、何を求められているのかを探り続けて終わったような感じですが、建築士会から何かを与えられるのではなく、建築士会をこうしていこうという思いを委員に伝えてからは、随分前向きにはなったかなと思います。
まずは自分が楽しんで、それが会員に伝染するようなネットワークを築きたくて、それを次の委員長に引き継ぎました。
今年度からは別の委員に所属して、別の角度から建築士会をサポートする立場になります。
引き続き、理事にもなりましたので、建築士会が目立つようにちょこちょこ発信していきます。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます