
これまでにもハーブやアロマの本の中に経絡や生薬、五行学説のことなどが書かれていたので目にしてはいるのですが、やはり興味があるかないかって肝心ですね。これまではそういった部分はさらっと読み進んじゃっていました。
西洋のハーブなどではヒポクラテスの四体液論が基本になっているので、体質は基本3通りか4通りなのが普通です。アーユルヴェーダもおおまかな分類は3通りですよね。5行って1つ多く、しかも更に細かく分類されていて面倒くさいというか覚えにくいイメージがあったんですね、なんとなく。季節も春夏秋冬のほかに土用なんていうのがあって。
ただ、アーユルヴェーダにしろ静養の体質学にしろ、3つか4つの分類なので、自分はこれに当てはまると思っていても完全に一致はしませんね。どこかが外れている。本書でも勿論完璧に一致はしないのですが、こういう病気にかかりやすい傾向のある、こういう体質・・・というのがわりとピンポイントにあたっている気がするんです。
私の場合は、風邪を引いても咳から始まって咳に終わる。どうも肺があまり健やかじゃない。そういう人は金(肺・大腸タイプ)といって肺も弱くてアレルギー疾患にかかりやすい。そういえば小児湿疹にかかりやすい子はアトピー性皮膚炎になりやすく、その後喘息へ発展する傾向があるので、皮膚と肺って全然関係ないようで、やはり繋がっているんだなと改めて思いました。
五行の理論でいくと木が燃えて火になり、火は土(灰)になり、土から金(金属)が採れる・・・。それと同じように肝臓は血液を貯蔵して心臓を助け、心臓は脾臓をあたためる・・・というようにやはり係わりあっている。ちょっと感動。
経脈と絡脈もリフレクソロジーのようにポイントで反射しているでけでなく、大腸のライン、象徴のラインというふうに系列で連なっている。これを覚えるのは相当時間がかかりそうだけど、少しずつでも覚えたら楽しいだろうな。マッサージの仕方も掲載されていた。サロンで行うにはちょっと疑問だけど、セルフマッサージには充分効果がありそうに思える。


↑ポチっとよろしく↑お願いします。
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとことお書きください。コメントのないもの、記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。
西洋のハーブなどではヒポクラテスの四体液論が基本になっているので、体質は基本3通りか4通りなのが普通です。アーユルヴェーダもおおまかな分類は3通りですよね。5行って1つ多く、しかも更に細かく分類されていて面倒くさいというか覚えにくいイメージがあったんですね、なんとなく。季節も春夏秋冬のほかに土用なんていうのがあって。
ただ、アーユルヴェーダにしろ静養の体質学にしろ、3つか4つの分類なので、自分はこれに当てはまると思っていても完全に一致はしませんね。どこかが外れている。本書でも勿論完璧に一致はしないのですが、こういう病気にかかりやすい傾向のある、こういう体質・・・というのがわりとピンポイントにあたっている気がするんです。
私の場合は、風邪を引いても咳から始まって咳に終わる。どうも肺があまり健やかじゃない。そういう人は金(肺・大腸タイプ)といって肺も弱くてアレルギー疾患にかかりやすい。そういえば小児湿疹にかかりやすい子はアトピー性皮膚炎になりやすく、その後喘息へ発展する傾向があるので、皮膚と肺って全然関係ないようで、やはり繋がっているんだなと改めて思いました。
五行の理論でいくと木が燃えて火になり、火は土(灰)になり、土から金(金属)が採れる・・・。それと同じように肝臓は血液を貯蔵して心臓を助け、心臓は脾臓をあたためる・・・というようにやはり係わりあっている。ちょっと感動。
経脈と絡脈もリフレクソロジーのようにポイントで反射しているでけでなく、大腸のライン、象徴のラインというふうに系列で連なっている。これを覚えるのは相当時間がかかりそうだけど、少しずつでも覚えたら楽しいだろうな。マッサージの仕方も掲載されていた。サロンで行うにはちょっと疑問だけど、セルフマッサージには充分効果がありそうに思える。
 | 中医アロマセラピー家庭の医学書―大切な人を守るための30トリートメント |
| 有藤 文香 | |
| 池田書店 |

↑ポチっとよろしく↑お願いします。
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとことお書きください。コメントのないもの、記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。










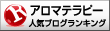
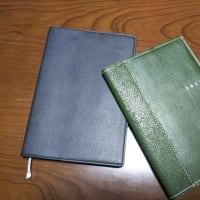















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます