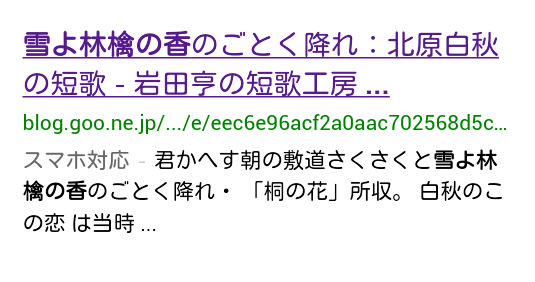
君かへす朝の敷道さくさくと雪よ林檎の香のごとく降れ(北原白秋)
有夫の愛人との朝の密会。女性だけ帰って行く場面。美しい歌だ。第2句は「敷石」と記憶していたが、ネットで調べたら敷道と紹介されている。韻律としては石のほうが良いと思うし、そちらが正解だろうと思うが、道も悪くは無い。石に視線が向くより、作中主体から遠ざかってゆく風景が浮かぶのも良い。ここでは、あえて真偽は調べず、岩田亨版としておこう。
一般論では、「さくさく」のようなオノマトペは、定型詩においては音数の無駄遣いだから避けよ、と言われるが、時間の経過と動作の継続が2音で表現されるという意味では有用と言えよう。
死に近き 母に添寝のしんしんと 遠田のかわず 天に聞ゆる(斉藤茂吉)
初夏の、水田が広がった場所で、蛙がいっせいに鳴く中にいると、慰謝される心理になる。この歌で、「しんしん」というオノマトペが何を意味しているかについては、解釈が分かれるだろうと思うが、僕は慰謝だろうと思うのだ。もちろん、強烈な印象を与えつつ、意味を曖昧にするところに、この歌の魅力があるのだから、詮索しようとは思わないが。
朝日子は女の子だからキラキラのビーズをまといそこに来ている(椎名夕声。短歌人2016年3月号)
朝の太陽光のことを、昔の人は「あさひこ」と言ったのです。















