近代以後の短歌の巨人といえば正岡子規(根岸短歌会)、与謝野晶子(明星《東京新詩社》)、斉藤茂吉(アララギ)、北原白秋(多磨)、俵万智(心の花)の5人だろう。
5人にしぼろうという考えは全く無くて、ウィキペディアの「歌人一覧」を2回見ても、これ以外の巨人はいない。
巨人じゃなくて「偉い歌人」なら北原白秋と俵万智は入らず、かわりに10人くらい入ることになる。巨人と言うには、新境地を開くとか何かと戦った人という条件が必要だ。名歌1首作っただけでは巨人とは言えまい。ひとつの役を演じて名優となっても、一流かとなれば別なのと同じようなもの。
改めて思ったが、巨人は皆短歌結社を大切にしている。
凡人も見ならうべきだろう。
結社に属するということは楽しいことばかりじゃなく、むしろ苦痛なことが多いかもしれないが、参加することに意義があると思っている。
なお、結社というと、政治結社や秘密結社を思い浮かべる人もいるだろうが、同好会のようなものである。
僕が入っている短歌人という結社の中地俊夫は敬愛する歌人のひとり。
去年永眠されたが、生前何度かお会いしたことがある。
十二万円あれば食へるといふ人の喉もと見つつ食へないと思ふ(中地俊夫)
食えると主張したのは政治家だ、と第三者が書いているが、確かに一般人と見るより政治家と見た方が構図がくっきりしてくる。「喉もと」が普通は鑑賞上のキモとされるだろうが、「思う」というのも意外に肝だと僕は思う。
何の世界でもそうだが、センスの良い人は難局をこともなげにクリアする。
12万円という数字は、知る人ぞ知る、ザックリ表現した最低生活費(後述参照)である。中地はそのことを知らないかもしれないが、「食えない」と作品上断定しないことにより、一見理屈っぽい短歌をキッチリ作品として成立させている。一見偶然のように見えて、センスの良さのなせる技なのである。そのことは、中地の作品を沢山読めば誰もが納得すると思うが、僕は初対面で気付いていた。その時は、多分あまり中地作品を読んでいなかったと思うが、中地は長く短歌人の発行人を勤めていたことから、新人によく話しかけたからである。
政治家が知ったかぶりに「12万円あれば皆生活できるんだよ」と言うのは、ザックリ言って1人世帯なら8万円、2人世帯なら12万円が生活保護の基本である生活扶助として支給されるという「根拠」を意識してのことだが、この数字には医療費等が含まれておらず、実は生活費そのものでは無い。この金額で生活できる人もいるが、生活できない人もいるのである。
(正確には1人世帯7万円、2人世帯11万円が支給されるが、住居費及びアローワンスを足す意味でそれぞれ8万円、12万円と言い習わしている。この何十年物価が少ししか上がらず、生活保護費は抑制傾向だからこの言い慣わしは変わっていない。)
センスというのは重要で、センスが悪い人はどれだけ努力しても駄目。
逆に頑張り過ぎることが害を成す。
親あれば放免される任侠(わたくし《ふりがな》)も本日からは斬られる哀れ(椎名夕声。短歌人2021年9月号)
「死なばもろとも」という有名な文があり前半「死なば」は仮定条件句だが、「親あれば」というのも仮定ですね。作品全体から古語じゃなく現代語であることが明らかなので「あらば」と言う必要はありませんが、古語作品なら必ず「あらば」となるべきところです。
なお、僕の母が1月にコロナ以外の病気で入院し、5月にコロナにはかからないまま亡くなった。その挽歌である。(母は昔盲腸で入院した以外で初めての入院で、年相応に老化した以外晩年まで元気だった)
このたびの災禍に関しては、あとからならなんだって言えるので、僕はリアルタイムを心掛け、短歌人の2020年4月号から1年5か月間発表し続け、今月号で第1部が終了した。
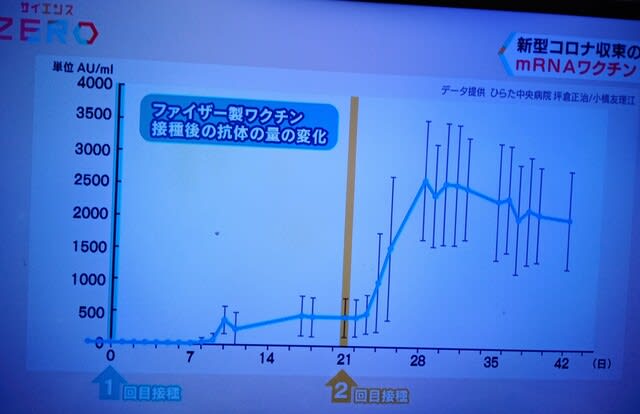
僕は結社では古くなって参じた兵だが、18歳から短歌をやっているので歌歴は長い。
長く縁が無かったというか、どの結社へ入ったら良いか判断が出来なかったのです。
結社の意義についてふたつ指摘しておく。
まず、一流の人がいることにより刺激を受けるということ。これは指導を受けるということではなく、あくまで刺激だ。
ふたつめは商業主義に流されないこと。文学は売れてはいけないとまでは言わないが、古来から言われているように、文学の意義は真善美であり、大衆に迎合することではない。
文学なんてのは、読者の千人に1人薬になったとか、良い意味で毒になりましたと言われればいいものなのだ。
結社のデメリットは、他人の選を経なければ自分の作品が掲載されないこと。
選者も人の子である以上完璧なはずはなく、間違った認識を持っていたり、自分の主義主張を押し付けてくることもある。
さらには、1首独立という意識で6首中に混ぜた作品が、連作とは異質という理由で機械的に捨てられてしまうというミスマッチも、有り得ないとは言えないでしょう。(同人以外はタイトルをつけることが禁止されているのだが、同人である選者の反射的反応は有り得るはず)
特定の個人の選をパスしないと闇に葬られるというのは、結社に限らず文芸選考一般の宿命である。例外なのは朝日新聞の朝日歌壇で、そこでは高名な選者たちが全ての投稿作品に目を通す。ただし、多くの作品を送っても全部ボツになることが普通で、張り合いがないだろう。
だから、せめて選者を選ぶことができる結社ということが必須と考えている。
あと、月刊誌の宿命として、毎月一定量のボリュームが必要だから、作品を沢山提出させておき、全体との関係で削るというルーティンになっている。作品が集まらなくて困るより、削るのに苦労した方がマシだから、とにかく沢山(と言っても、自ずと限度があるが)提出するよう仕向けられている。
その結果、ページを開くと毒にも薬にもならない文が目につくことになる。
これは宿命だから、諦めるより仕方がない。
ただ、寡作タイプの人が、無理して沢山作ることは、本人のためにならないと思うので、無理せず上手に付き合った方がいい。
最後に、与謝野晶子に関する「ちょっといい話」を。
短歌研究8月号に松平盟子が紹介していたが、東京朝日新聞の明治45年6月26日付けに発表された次の作品。
若ければふらんすに来て心酔ふ野辺の雛罌粟(こくりこ)街の雛罌粟
恥ずかしいほどの駄作だ。しかし、これが原作となって、次の名歌が誕生したそうだ。
ああ皐月仏蘭西の野は火の色す君も雛罌粟われも雛罌粟
(後日記)
せっかく結社の話題なのに、結社の最大のメリットを書かなかったので補っておく。
結社の歌会では、作品を批評するときに作者名を伏せる。出席者が少ないと、誰のものか予想できるケースがあるが、40〜200人だと忖度ない意見を言いやすい。
文学は批判を経て育つ。批判をはねつけて我が道を行くとしてもバージョンアップする。















