
先日コメントでも書いたのですが、青森はお赤飯が甘いんですよね。
実家で食べていたお赤飯は味はなくて、ごま塩をかけていました。
たまに食べたくなるお赤飯ですが、道の駅で買って食べてみて、甘くてビックリした事がありました。
「山梨の知人宅に泊まりに行ったら出されたお赤飯が甘かった。作り方を聞いたら炊きあがったもち米に甘納豆を混ぜるらしい」
人からこの話を聞いたときに、世の中にはいろいろな食文化があるのだと驚きました。
歴史を見ると鎌倉時代に山梨県南巨摩郡を本拠としていた南部氏が室町時代に青森県の三戸地方に移ってきたという事になっています。
いつ、どのような理由で来たのかは諸説ありますが、共通する食文化は確かに残っています。
山梨県の郷土料理「ほうとう」と青森県での「はっと」は同じルーツを持つように、甘いお赤飯も同じで、山梨県と青森県岩手県の南部地方には共通するものが多く残っています。
実家で食べていたお赤飯は味はなくて、ごま塩をかけていました。
たまに食べたくなるお赤飯ですが、道の駅で買って食べてみて、甘くてビックリした事がありました。
「山梨の知人宅に泊まりに行ったら出されたお赤飯が甘かった。作り方を聞いたら炊きあがったもち米に甘納豆を混ぜるらしい」
人からこの話を聞いたときに、世の中にはいろいろな食文化があるのだと驚きました。
歴史を見ると鎌倉時代に山梨県南巨摩郡を本拠としていた南部氏が室町時代に青森県の三戸地方に移ってきたという事になっています。
いつ、どのような理由で来たのかは諸説ありますが、共通する食文化は確かに残っています。
山梨県の郷土料理「ほうとう」と青森県での「はっと」は同じルーツを持つように、甘いお赤飯も同じで、山梨県と青森県岩手県の南部地方には共通するものが多く残っています。
















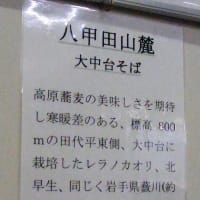



栗ご飯と言えば塩味が効いて…と思うとさに非ず、栗の甘露煮がちりばめられた赤飯は微妙な甘さ。
赤飯のふたを開けると南天の葉があるはずなのに…。
ちなみに、長崎も同様に甘いもの文化が形成されているそうで、代表的な物が長崎カステラ、ちゃんぽんも甘いのが正当と言われ、見た目と味のギャップに泣きながら食べたのは最近の思い出です。
塩が採れても砂糖は採れない、故に砂糖は貴重で高級というのがいわれだとか。
南部と山梨の関係のように、津軽と九州に関係があるとどこかで聞いた記憶があるのですが、出典などが不明で調べられずにいます。
十三湊の交易の事だったのか・・
歴史を調べながら民俗を見るのは楽しい作業ですね。
青森といっても津軽地方はまた違うのではないかと思っています。
他にも甘いお赤飯を作る土地もあるのですね。参考になります。
甘味については砂糖以前の甘味料の利用だったのではないかと思います。
高度成長までは贈答品として砂糖を配ることもありましたし、比較的最近まで砂糖は貴重だったのでしょうね。
砂糖の普及以後は、それまで甘味として使っていた麦芽、米芽や麹や甘味を持つ自生植物の利用はなくなってきています。蜂蜜も含めて、サトウキビ・甜菜以前の甘味にも興味がわいてきます。