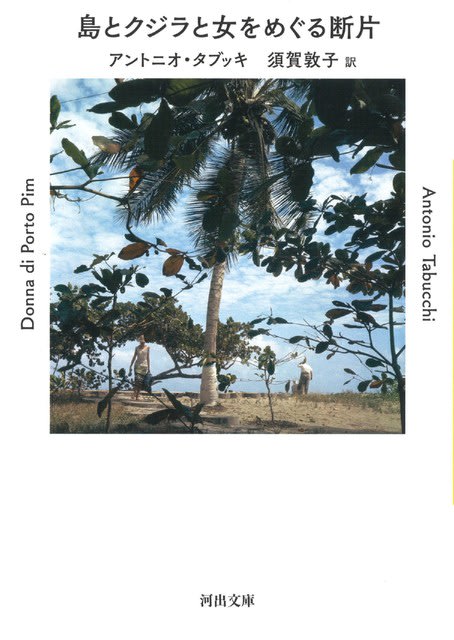あら、おかえりなさい。早かったのね~。
ご飯にする?お風呂にする?それとも
…ブ・ロ・グ?
こんばんはみなさま。金曜夕方ですね。今日は朝から予定が詰まっていて疲れました、今は人間の形状を保つのがやっとです。でも最後の力を振り絞ってブログを書きます。アッ形が崩れる、腐ってやがる、早すぎたんだ!!
さて今日紹介するのは最近読み終わったチェーザレ・パヴェーゼの『月と篝火』、川島英昭氏という東京外大の教授が翻訳してます。パヴェーゼはイタリア人作家で、活躍した時期はイタロ・カルヴィーノやナタリア・ギンズブルグの少し上の世代になるでしょうか。本作を出してすぐ、42歳で服薬自殺をしています。余談ですが自殺する作家って格好いいですよね、ヘミングウェイとか芥川とか。しかし太宰、テメーはダメだ。三島もちょっとな。友達には絶対なれないな。
本作について。ざっとしたあらすじ。
私生児として生まれた「ぼく」は、壮年の年頃に差し掛かっていた。経済的に成功し、青年期まで過ごした故郷、イタリアの北部の農村を訪れる。かつて愛した人たちは、親友のヌートを除いてほとんどいなくなっていた。あるものは病に伏し、あるものは戦争に巻き込まれた。故郷を歩いているうちに思い出す、過去の記憶の断片たち。悲しい出来事だけでなく、今になって思い起こされる美しい記憶もある。しかし最終的に思い知らされるのは、戦争の余韻と世界の残酷さ。そんな感じの話です。
悲しい話なんだけど、戦争もののベタなお涙ちょうだい小説ではなく。布が水を吸ってじっとり重くなるように、あとから悲しさが余韻として襲い掛かってきました。雰囲気で言えばフォークナーの『響きと怒り』に似ているでしょうか。あるいはアーヴィングの『ホテル・ニューハンプシャー』にも少し近いかもしれない。あちらの方がもう少し世俗的な感は否めませんが、セックスの話多いし。
しかし途中までは別の要素で読むのが辛かった。何の断りもなく次々と人が出てきたり、イタリアの地名(しかも北部で馴染みがない)が出たりして、人なのか土地なのか頭がさっぱりコーンな状況で読んでいくことになります。あっ土地が喋ってるー!と思ったこともありました、そんなわけあるかい。
とはいえ。とりあえず流し読みをして、おおよそこんなことがあったんだな、と思いながら読んでいくと段々主人公の過去の物語が明らかになってくるのですね。貧しい家庭で育ったこと、13歳を迎え農場で働くようになったこと、そこの主人や娘たちとの交流、親友のヌートの存在。
ごくミクロな世界、あの土手がどうとか、丘やぶどう畑がどうとか、そういった話も淡々としていて面白いのですが、唐突にドイツ兵の死体が見つかったり、友人がパルチザン(イタリアのレジスタンス組織)に加わっていたことを匂わせたり、ところどころで第二次世界大戦の名残りが語られます。
パヴェーゼ自身は探偵小説を意識したようですが、最後の方に謎が明らかになるというか。そのせいもあって構成が複雑なので、一度読んだだけでは消化しきれない部分が多い。人かなと思ったら土地だったりする部分もありましたからね、人の上にぶどう畑ができるかよな。
それから。構成が複雑になってたり、話があちこちに飛んだりしているのは、もしかしたら自分にとって非常に大切なものである≪故郷≫を失い、茫然自失とした状態なのかな、とも思ったり。自然は相変わらず当時の名残りを残しているぶん、自分たちと一緒に過ごした人が戦争や病気で死んだり、ろくでもない結末になったり、そういったことがより一層残酷に感じられるのかもしれない。
余談。
私も故郷から遠く隔たって生きておりますが、自分の生まれ故郷は20年後30年後、どうなっているのだろうな、と思うことがあります。少子高齢化を代表するような土地なので、やがて人はいなくなるのでしょう。そんな時、自分は故郷に戻って何を思うのだろう。悲しいような、でも仕方ないな、という気持ちになるのかもしれませんね。それはそうと、東京生まれ東京育ちの人は、そういった「故郷ロス」みたいなのはあんまり味わえないんじゃないかなと思うのですが、どうなんでしょうね。