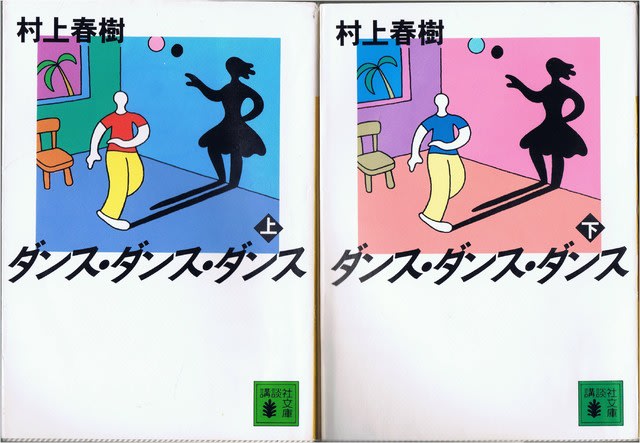クリスマスなのでブログを書きます。
11月下旬、山手線1周RTA後に引いた風邪がまだ完治しておりません。
よくなってきたタイミングで酒を飲んだり、エアコンつけて寝落ちしたりした結果、ぶり返しています。
人間、調子に乗るとよくないですね。油断せず生きていかないと。
まあまあ真面目に働いていたら12月があっという間に過ぎていって。
気づけば月末、というか、もうすっかり年末ですね。
年末らしいことをまったくしていません。
油断せずサボっていかないと。
漱石の『三四郎』を読み返しました。
ものすごく面白かったです。昔読んだ時よりも、作品の奥深さが感じられるようになって。
というわけで今日は『三四郎』について。
はじめて読んだときは、ヒロインである美禰子にばかり目が行っていました。
この美禰子(みねこ)という人物は、主人公の同郷の先輩である野々宮さんの妹、よし子の友人です。
わりあい明瞭な性格であるよし子と対比されるかたちで、本性がわからない、冗談なのか真面目なのか曖昧な態度を取る、非常にミステリアスな女性として描かれます。
漱石のほかの作品でいうならば、『草枕』の那美、『行人』の直に重なる部分があるように思います。
簡単に言ってしまえば青春群像劇のような小説です。
帝国大学(現在の東京大学)に進学するため、熊本から上京してきた小川三四郎。
彼は様々な人物と出会いますが、なかでも美禰子に強く惹かれていきます。
友人たちと菊人形を見に行った際に、主人公と抜け出して谷中付近を散歩したり、また別の日に一緒に絵画の展覧会に行ったり。
物語の冒頭で会った女性から「あなたは余っ程の度胸の無い方ですね」と言われ、母親からも手紙で「お前は子供の時から度胸がなくっていけない」と言われた三四郎。
しかし美禰子には、あるとき意を決して「あなたに会いに行ったんです」と伝えます。これで自分の思いが十分伝わると踏んでの発言です。
その後美禰子は、初めて三四郎と会った日のことをほのめかします。
そして…というストーリーなのですが、まだ読んだことがない人はぜひ読んでみてください。
青空文庫にもあります。
登場人物も個性豊かで。
恐らくADHD的で騒動を巻き起こしていく与次郎や、知識は豊富だけど何を研究しているのかさっぱりわからない野々宮さん、ぱっとしない知識人の広田先生をめぐるエピソードも面白いです。
特に広田先生の言動には、漱石自身の気持ちや思考がかなり投影されているのではないか。自我を主張する近代人、偽善と露悪をめぐる話も漱石らしくて。『私の個人主義』で述べられている内容と、重なるように思います。
また、広田先生が何故結婚をしないのか、それとなく主人公に伝えるエピソードも興味深くて。
物語の終盤になって「たとえば」と先生は話を始めます。
たとえばここに一人の男がいる。父が早くに死に、母と生活をしていた。しかし母も病気になり、いよいよ死ぬ間際になった時に「私が死んだらこの男を頼れ」と言う。会ったこともない、知りもしない人だ、妙だと思って問い詰めたら、実は自分が不義理をした末に生まれた子である、その人がお前の本当の父親だと告げられる。
そうすると、その男は結婚に対して強い幻滅を抱くことになる。
広田先生はそう語ります。
三四郎は「しかし先生のは、そんなのじゃないでしょう」と、あくまで寓話の1つとして受け取りますが、先生はハハハハ、と笑った後に「ぼくの母は憲法発布の翌年に死んだ」と答えます。
この対話の描写がすごいなと思います。
三四郎の問いかけに対して直接返答するわけではないし、明確に肯定も否定もしない。
しかし自分の母親がすでに亡くなっていることは伝えている。
三四郎が美禰子に対して、「あなたに会いに行ったんです」と言えば十分伝わると踏んだように、広田先生も自分の母親の死に言及することで、自分の言いたいことが三四郎に十分伝わると考えたのかもしれません。
「自分の親は本当の親ではなかった」というエピソードは、漱石自身の体験でもあります。
以前『坊っちゃん』について書いた時にも触れましたが、彼は幼少期に里親に出された経緯があります。
その体験は漱石の人生に大きく影を落としていて。
『彼岸過迄』でも、主人公の友人が似たような生い立ちを持つことが明らかになります。
漱石のそういった体験が、どのように作品に影響しているか。
マクロな視点で言えば、「安定した環境のなかでの適度な愛情供給が不足すると、他者に対する強い不信感に結びつく」ということになるのかもしれません。
この『三四郎』で主人公は、美禰子の件でも与次郎の件でも、いろんな形で裏切られることになります。先輩の野々宮さんも、裏切られることになります。このへんの「人から裏切られる」ことによる苦しさ、たまんないですね。漱石を読むことでこそ、得られる栄養です。
彼の代表作『こころ』では、先生は親戚から裏切られるし、親友を裏切ります。『三四郎』の次の作品『それから』では、自然の心に従った結果、主人公は友人や家族を裏切ります。比較的シンプルな作品である『坊ちゃん』でも、赴任先の松山の人間に対して著しい不信感を抱いていました。
こういう猜疑心や不信感を、漱石自身も抱いていたのかもしれません。
そう思うと、さぞ苦しかっただろうなと勝手に気の毒に思います。
みなさんはどうでしょう。
ちゃんと信頼できる人はいますか。
人を裏切って傷つけた経験はありますか、裏切られたことはありますか。
私は裏切ったことも、裏切られたこともあります(今も職場を裏切ってブログを書いてます)。
だからこそ、漱石の作品が染み入るのかもしれません。
年を重ねても、また読み返したいです。