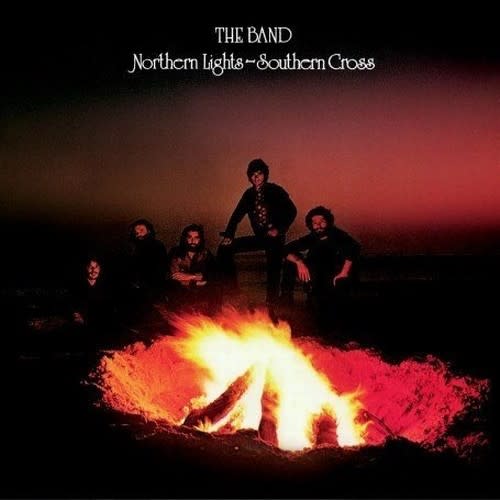ネタが切れそうなのと低気圧が来たのとで更新が遅れてしまった。
もうじき梅雨も明けそうだ。この時期になると一年の半分が過ぎたことになる。そうしたことに漠然とした焦りと不安を感じるのは私だけだろうか。もちろん焦ったり不安になったりしても、どうにかなることでもないのだけれども。
さて今日取り上げるのは旧千円札で笑ったり怒ったり忙しかった漱石先生である。きっと誰もが高校3年生の現代文で『こころ』を読み、「なぜKが自殺したのか」とテストで書かされたことだろう。
なぜもっと早く死ななかったのだろう。そう記していたKの気持ちが、20年も生きていない高校生にわかるかって話。個人的には野口英世のような性格が劣悪な人間より、漱石先生がずっと千円札であってほしかった。先生も結構大変な人だったらしいけれど。
漱石の経歴はウィキに乗っているからごく簡単に。東京、牛込生まれ(現在の早稲田の近く。生誕碑の隣には現在やよい軒がある)。東大英文科を出て、教師になる。ロンドンに留学しビスケットばかり食べる。精神的に具合が悪くなる。友人の高浜虚子に進められて小説を書き始め、『吾輩は猫である』でデビューする。その後も優れた作品を書き続けるが胃病に苦しむ。子どもをジャイアントスイングする。49歳のときに胃潰瘍で死去。亡くなったのが1916年だから、昨年が没後100周年だったわけだ。
今回紹介するのは彼の後期三部作の一つである『行人』である。これは「こうじん」と読む。そのままの意味だと「道を行く人」だ。同じ漢字で「修行をする人」という宗教的な意味もある(もっとも、その場合だと発音が漢音ではなく呉音になるため「ぎょうにん」と読む)。
自分は数ある漱石の作品のなかで、たぶんこの作品が一番好きだと思う。何が好きかって読んでいてすごく苦しくなるのだ。そして人と人が―男女の間柄もそうだし親しい友人、親子やきょうだいであっても―「わかりあえない」ということがこれでもかと描かれている。でも読むたびに新しい発見がある。再読に耐えるというのが、やはりいい文学作品の条件なんじゃないだろうか。そういった点では漱石の作品は再読に耐えるものが多い。
本作は「友達」「兄」「帰ってから」「塵労」の四部構成となっている。1つ1つの章は関連があるようでもあり、物語の中に入れ子構造のようにいくつかのエピソードが散りばめられているため、どこか断片的にも感じられる。『こころ』や『道草』のように、一貫して何かの主題を描いているようには見えないが、かといってちぐはぐしているわけでもない。不思議な小説だ。ただ結構長い話なので、紹介するにあたって好きな場面を抜粋してお伝えしよう。
第一章では友人の三沢が胃を患い、旅先の大阪で入院する。ややあって彼は無事に快復し、夜行列車で東京に帰ろうとする。その直前に、彼は自分のせいで同じ病院に入院し、助かるかどうかわからない胃病の女のことを話す。
「あの女はことによると死ぬかも知れない。死ねばもう会う機会はない。万一癒るとしても、やっぱり会う機会はなかろう。妙なものだね。人間の離合というと大袈裟だが。それに僕から見れば実際離合の感があるんだからな。あの女は今夜僕の東京へ帰る事を知って、笑いながら御機嫌ようと云った。僕はその淋しい笑を、今夜何だか汽車の中で夢に見そうだ」
彼はそう語る。さっぱりした言い方にも聞こえるが、「夢に見そうだ」というくらいだから、よほど三沢のこころに引っかかっているのかもしれない。自分がしでかしたことで人が死ぬというのはどんな心持ちなのだろう(とはいえ実際三沢がしたのは、その女に無理に酒を勧めたことくらいなのだけど)。それはきっと恐ろしいようにも思えるし、自分のせいではないと言い張って逃げ出したくなるのかもしれない。しかしここでの三沢の態度は、どこか女との距離や諦めがある。悲しいとか申し訳ないとか、そういった感情とは隔たりがあるように感じるのだ。だからと言って彼が何かしようとしても、もはやできることはないのだが。
さてその後、大阪に出てきた兄やら嫂(あによめ)やらとひと悶着あるのだが、この兄と嫂の関係が物語の中核となっていく。兄はかなり性格に問題を抱えた人物だ。神経質で気分屋で不機嫌な空気を漂わせる、いかにも気難しい学者といったふうである。しかし内面はとても繊細で傷つきやすく脆い部分があることが、物語が進むにつれて語られていく。一方で嫂には、不愛想とも冷淡ともとれる平静さが常に漂っている、ミステリアスな人物として描かれる。そして彼女の言動が夫である兄を苛立たせ、母親をはらはらさせ、主人公の二郎に疑問を抱かせる。しかし和歌山の宿の場面で彼女もまた意外な一面を見せる。とにかくこの二人の人物描写が非常に立体的で、それぞれ奥に抱えているものが徐々に明るみに出て行く展開が面白い。
小説だから人物の性格、心境、考えなどの描き分けはやって当たり前だと思う向きもあるだろう。しかしながら漱石の描く人物たちは、そりゃもう生半可じゃないくらい「ちゃんとマジに悩んでいる」のだ。この懊悩の描き方が、月並みな表現だが尋常ではない。その悩みっぷりがすごすぎて、読んでいるこちらまで苦しくなってくる。人が抱えている荷物の一部を譲り渡されたような気持ちになる。
人の苦悩を直接的に、あるいは間接的に聞くという話は漱石の後期の作品によくみられる。代表作『こころ』はもちろんのこと『彼岸過迄』でもふとした好奇心がきっかけに、最後は友人の大きな秘密を知る話だ。彼の作品を読んでいると思うのは、現実の世界でこれほど苦悩している人間がどれほどいるだろうか?ということだ。もちろん我々が生きている時代とは隔たりがあるため、男女の関係などは当時と悩みの質も変わっているだろう。あるいは小説である以上、読者の興味を惹くために謎が謎を呼ぶようドラマティックに書かれている部分もあるかもしれない。だけど漱石の小説の登場人物が抱えている悩みは、「自分の利益のため他人を裏切ってしまった苦悩」「どこまでいっても自分は幸せになれない」など、得てして現代に生きる私たちにも通じる、普遍的な部分があるようにも思う。そのせいか、読んでいるとある考えに襲われる。自分は、あるいは自分の周囲の人間はどうだろうか、こんな風に真剣に悩むことがどのくらいあるだろうか、と。
そしてこれほどまでに一生懸命悩んでいる人物を前にして、自分がいかに軽薄な人間であるかということを思い知らされる(知らず知らずに主人公である二郎に感情移入してしまうのだ)。背筋がひやりとすることもある。自分は彼らほど真摯に、悩みながら生きているだろうか。目先の事ばかりにとらわれていやしないだろうか。
きわめて辛そうで苦しそうだけれども、「ちゃんとマジに悩んでいる」登場人物たちが、どこかでうらやましくも感じるのだ。
漱石の文章は風景描写も美しい。特に二章の和歌の浦、それから四章の実家の描写。周囲のさりげない変化を、季節の移り変わりとともにうまく描き出している。漱石というと現代知識人の苦悩であったり、隠されていた秘密の告白であったり、そういった内面的な部分にフォーカスされることが多い。しかし何気ない風景描写も、大げさすぎずかつ美しいのである。このあたりの「風景を見る眼」「風景を描く言葉」は、漱石が漢詩や俳句を嗜んでいたことも影響しているのかもしれない。きっと人が見る以上のものが見え、人が考える以上のことを考えた人なのだと思う。