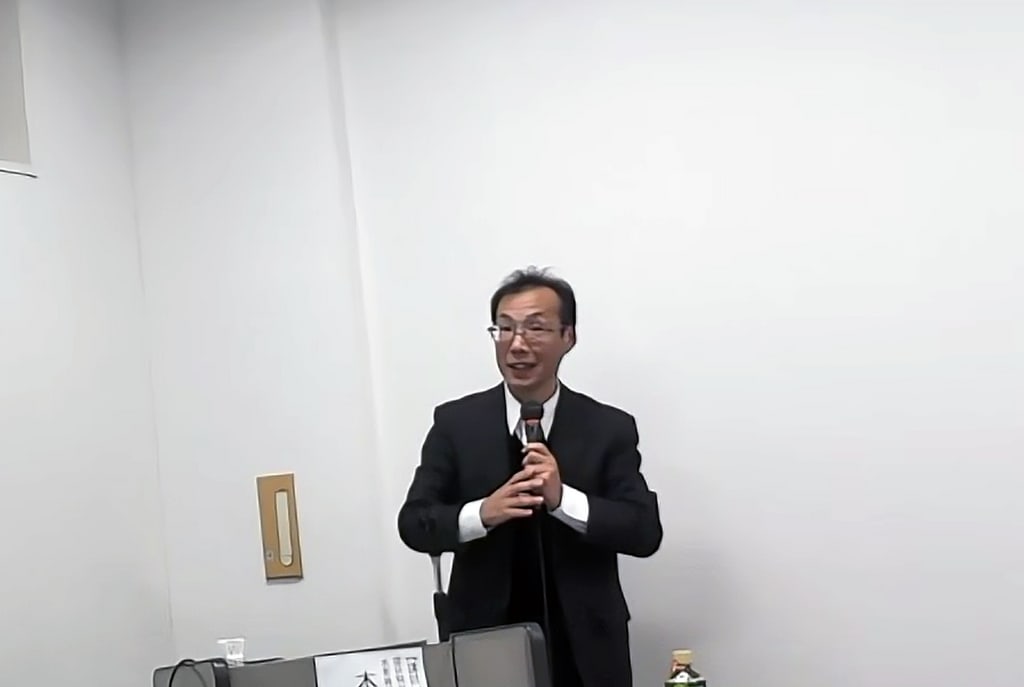
水産研究・教育機構の木所底魚資源部副部長
水産・食料研究会(馬場治会長)の第151回講演会が1月15日、東京都中央区の会議室(ウェブ併催)で開催され、水産研究・教育機構水産資源研究所の木所英昭底魚資源部副部長が『気候変動がもたらす水産資源や漁業への影響と対応〜これからの海と社会の変化に向けて〜』をテーマに現状と課題を報告し、50人余りの参加者が熱心に聞いた。
馬場会長が「以前から気候変動への対応は検討され。水産分野でも検討されたが、あまり進んでいるとは思えない。災害の激甚化で保険・共済が成り立たない状況になっている。気候変動の影響は漁業・養殖ではかなり短期間で出ることが予想され、漁業経営の継続が心配される」と挨拶した。
さっそく木所副部長が気候変動・海洋環境の変化と水産資源の応答をとりあげ、①魚種交代、レジームシフトなど数十年規模の変化(周期的な海洋環境変動)、②気候変動・温暖化による変化(長期的な水温上昇)、③短期・局地的な海洋環境の変化に整理し、「様々な時空間スケールが関与し、温暖化の影響ばかりではない」「要因を明確化しての対応が有効となる」とした。
周期的な海洋環境変動は、かつてのような温暖期はスルメイカ、カタクチイワシが増え、寒冷期はマイワシが増えるという水温の変化だけでは予測ができない。気候変動の影響で、北海道でブリが急増し、日本海でサワラが急増しており、地域ブランド化など有効利用のため、今後の安定来遊が課題となっている。最後に「海洋環境(温暖化、魚種交代)によって獲れる魚・食べる魚が変わってくる。水産業・消費者も長期的・短期的な適応が必要」とまとめた。
















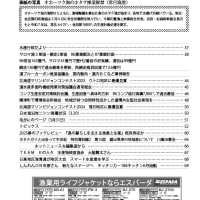



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます