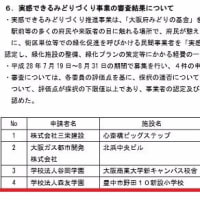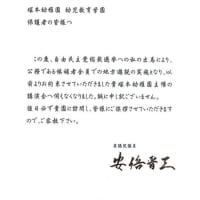前回、ナポレオン戦後のイギリスにおいて、穀物法をめぐって、又、当時の不況状態でのマルサスについて若干触れました。イギリスではナポレオン戦後、略、慢性的に不況だったわけですが、そういう中、当時のイギリスの通貨制度は“ハ行金本位“とでも言うべき体制でしたが、(多くの諸国は銀本位制乃至複本位制であった)その主としては、通貨制度の技術的理由から、1816年に金本位制となります。(世界的に金本位制になったのは、略、19世紀の後半である。)そして地金委員会の報告により、兌換再開を勧告されていましたが、1816年11月から順次兌換を再開することになります。一説によればそれは兌換再開にどれだけの正貨が必要であるかを確認する為であったとも言われていますが、当初は殆ど兌換請求は起こらず、1818年以降になって不作による穀物輸入の増大等に伴う金流出等で準備が減少した事により、1819年初頭には兌換を中止します。その間、1817年には当時の不況、失業状態の改善の為、“資本主義史上初めての“(前掲メンデリソン)公共事業が行われます。これについては、マルサスが同年、人口論の第5版を出し、その中で不況救済の為の公共事業の必要性を説いています。-小林昇編:資本主義世界の経済政策思想 その連関性は現段階では投稿者も詳らかにしていませんが、関連性は有りうる事と思います。失業対策としての公共事業はその後の19世紀の歴史の中で頻々と登場します。(メンンデリソン、Unemployment in History: John A.Garraty)そういう中1819年2月、兌換に関し、正貨兌換再開秘密委員会が持たれ、5月には報告を出し、兌換実施の方向が出され、同年7月には兌換再開法が作られます。その背景としては、やはり、不換銀行券の過剰発行→金価格上昇、物価上昇、過度投機→過剰生産という認識があったとされます。(前掲吉岡)又その法案で注目すべきは、リカードが唱えたインゴットプラン(金塊で交換する 結果として少額貨幣は兌換できない)が取られ、暫時的に金貨での兌換を目指すと言う事になっていました。しかし、地方銀行券やイングランド銀行の準備等は何ら触れられない等の点も有りました。参照:Fetter Developmennt of British Monetary Orthodoxy 投稿者も欧文献は最低限参照するのみですが、これは19世紀イギリス金融史では必読文献であると思います。2008.8.14一部訂正
最新の画像[もっと見る]
「景気政策史」カテゴリの最新記事
 景気政策史―60 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その16 “大不況”と商工業...
景気政策史―60 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その16 “大不況”と商工業... 景気政策史―59 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 “自由貿易”と砲艦...
景気政策史―59 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 “自由貿易”と砲艦... 景気政策史―58 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 英仏通商条約と...
景気政策史―58 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 英仏通商条約と... 景気政策史―57 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その14 後発国の自由と...
景気政策史―57 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その14 後発国の自由と... 景気政策史―56 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その13 後発国の自由と...
景気政策史―56 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その13 後発国の自由と... 景気政策史―55 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その12 関税改革及び穀...
景気政策史―55 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その12 関税改革及び穀... 景気政策史ー54 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その11反穀物法同盟...
景気政策史ー54 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その11反穀物法同盟... 景気政策史ー53 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その10穀物法、通貨、...
景気政策史ー53 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その10穀物法、通貨、... 景気政策史ー52 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その9穀物法、通貨、不況
景気政策史ー52 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その9穀物法、通貨、不況 景気政策史ー51 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その8自由貿易と機械輸出
景気政策史ー51 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その8自由貿易と機械輸出