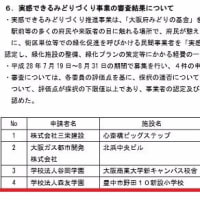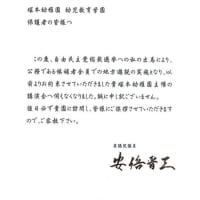上記で1820年の商人請願を受けて議会に委員会が持たれそれらを受けて関税の引下げや航海法の緩和等、多数の諸国との互恵通商条約の締結が行われた事を述べたが、それらと並行して勢いを増しつつあったのがマンチェスター商業会議所であり1820年5月に結成し上記ロンドン商人の請願も支持し1822年1月には年次総会を行い規約等を決めたが、其の骨子はマンチェスター周辺の商人と製造業者の利益の保護を目的とし(第1条)其の利益に関係する議会の議事に注意を払い適切な手段を用いて[通商の自由にとって有害な現存の規制の除去を求め](第3条)と言う内容の規約を決めた。(因みに、周知の事であるが”マンチェスター派”とはマンチェスターの綿業資本家を中心とする19世紀中葉のイギリスの自由貿易論者の事を呼ぶとされる(熊谷次郎 マンチェスター派経済思想史研究 日本経済評論社1991年)
これら自由貿易派とされる商人、資本家が自由貿易の主体的推進勢力で有った事は論を待たない事とは思うがここで問題にしなければならないのはその唱えるところの”自由貿易”が全ての面で額面どおり行われていたかを考えるのも必要な事と考える所である。
ここで自らの製造業が産業革命以来も持ち続けてきた保護主語的な面を述べるのも意義なしとはしないと思われる。それは何かと言うなら”機械輸出”の事であり、産業革命初期の1774年に始まった”職人の海外移住の禁止”と”機械の輸出禁止”である。これらは1820年代以降、ハスキソンの”自由主義改革”によりやはり1824-25年当時議会で問題となり[職人と機械に関する特別委員会]がもたれたがそれは職人の海外移住と機械輸出緩和の動きであるとみなしたマンチェスター、バーミンガム、リバプール等々の製造業者たちが反対運動を起こし、マンチェスターも強硬な反対の立場を明らかにした。
このような動きの結果委員会は職人の移住に関しては廃止を勧告したが機械輸出に関しては”継続調査”に留まった。
1827年2月の年次総会でマンチェスターが穀物の自由化を述べる他方で機械の輸出を主張するのは利己的行為であるとする主張に対し”我々自身の私的利益を促進するためでなくこの国の一般的福祉の増進の為に行っている”と強弁したがこれにつき、Musson.Aはその”The Manchester School”and Expportaion of Machinery”で[自由貿易派は彼らの対立者である保護貿易者同様、徹頭徹尾、利己的であった](前掲イギリス綿業自由貿易論史:熊谷次郎 による引用)
これらの動きに対し1830年代半ばの不況に対してマンチェスターの機械製造業者から輸出禁止に対して不満の動きも強まりその様な中、紆余曲折を経て1843年に至って税関関係法改正法により機械輸出が完全に自由化された。
参照;本稿は イギリス綿業自由貿易論史 熊谷次郎に多くよっている。(因みに同書は19世紀英自由貿易史としてかなり有益である)