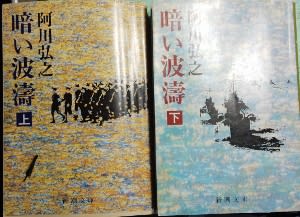阿川弘之著の『暗い波濤』(文春文庫版)を読んだ。阿川弘之氏は1920年広島市生まれの人。東大国文科を繰り上げ卒業し、海軍予備士官として海軍に入る。戦後、志賀直哉に師事し、自らの学徒兵体験に基づく『春の城』で読売文学賞を受賞。主な作品に『雲の墓標』、『舷灯』、『暗い波濤』、『志賀直哉』の他、『山本五十六』、『米内光政』、『井上成美』の海軍提督三部作がある。
『暗い波濤』は、各大学を繰り上げ卒業し第二期海軍予備学生550余名を乗せた、特設巡洋艦愛国丸が台湾での基礎教育を終え、帰国の途につくところから始まり、日本の敗戦によって生き残った予備士官たちが、戦後の日本社会に立ち向かおうとするまでを描く。予備学生たちは飛行科あり、砲術科あり、兵学校の教員あり、電波探知ありと様々な専門訓練を受け、少尉として任官し戦地に出ていく。『暗い波濤』では、それぞれが戦地でいかに悲惨な戦いをしていたか、丁寧に描いている。一方、敗戦必死の情勢の中で、戦争を終わらせるために動いた人たちのことも書かれている。
読んで感じたのは、ひとたび戦争が起これば、人間の良心や理性といったものは奪われ、いやでもおうでも殺し殺されるという状況になるということである。今、安倍内閣は「現行憲法下でも集団自衛権を行使できる」という方向に舵を切ろうとしているが、『暗い波濤』に書かれたあの戦争の実態を見るとき、空恐ろしいものを感じる。やはり安倍さんも「戦争を知らない世代」なのだろう。「危ない火遊びをするようなことはやめて」と言いたい。
私は、19歳で日本共産党に入党する時から、「反戦平和のためにたたかう」ことを一つの信条にしてきた。危険な方向に政治の舵が切られようとしている時だからこそ、このブログを通じても多くの皆さんが反対の声をあげること呼びかけたいと思う。