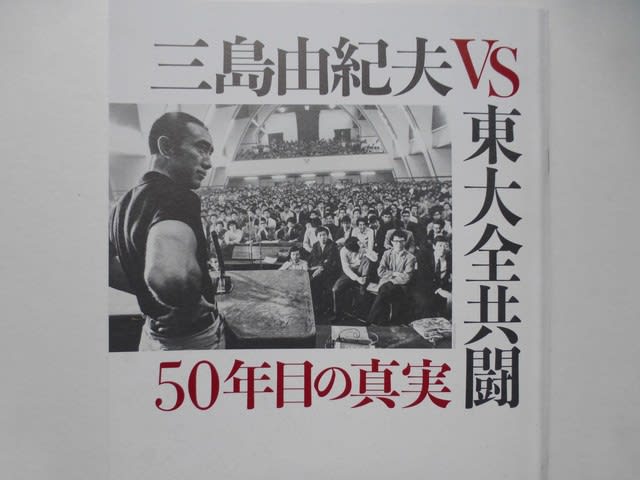2005年に発行された豊田徹也の漫画「アンダーカレント」の映画化作品。原作本は残念ながら未読だが、今泉力哉監督をはじめ、出演者の顔ぶれに惹かれて選んだ一作である。冒頭にアンダーカレントの説明として「表面の思想や感情と矛盾する暗流」とテロップが出るが、心の奥底に沈めていた思いが徐々に浮かびあがってきた時、人はその抱えきれない思いとどう付き合っていくのだろうか。
かなえ(真木よう子)は亡き父親のあとをつぎ夫婦で銭湯を経営していた。しかしある日、夫の悟(永山瑛太)が突然失踪する。途方に暮れるかなえだったが、何とか銭湯を再開すると、堀(井浦新)と名乗る男が働きたいとやって来る。資格を沢山もち、銭湯組合からの紹介で来たという謎の男との共同生活が始まる。
銭湯を営む女主人と蒸発した夫と言えば「湯を沸すほどの熱い愛」(中野量太監督、2016年)を思い出す。薪が赤々と燃え、その炎の暖かさと湯の温もりが感じられる作品。一方この作品は、銭湯が舞台ではあるが、湯気が立ちのぼる温もりが感じられない。それよりもタイルの冷やかさ、水の冷たさが忍び寄る。死のイメージに全体が覆われている。
大学時代の友人の菅野(江口のりこ)の紹介でかなえは探偵の山崎(リリー・フランキー)に会い、夫の調査を依頼する。カラオケボックスや遊園地で調査報告をする、いかにも胡散臭い山崎だが、調査期間内に悟の居場所を突きとめ、かなえは悟と会うことになる。リリー・フランキーがまさにはまり役で、チャーミングに演じている。やがて、悟の思いがけない半生や堀の素姓、かなえが水中に沈んでいく悪夢の正体が徐々に明らかになっていく。
堀を演じる井浦新はメッセージ性の強い作品に出演しているとの印象が強い。直近では「福田村事件」(森達也監督)があり、遡れば「かぞくのくに」(ヤンヨンヒ監督、2012年)を思い出す。舞台挨拶ではいつもゆっくりと言葉を選び、力強いメッセージを発信していく。堀は無口で誠実そうに見えるが、一方で何を考えているのか分からないミステリアスな人物。かなえに亡き妹の姿を重ねているようだが、かなえに寄り添い支えていく。一見して熱量の少ない演技に見えるが、繊細で緻密な演技の出来る俳優だ。作業着のような服装でも格好良く、さまになっている。井浦新には大人の色気がある。
物語は終盤に向かうにつれて死のイメージが払拭されていくが、それとともにアンダーカレントな深みは希薄になっていく。
ラストシーンの構図は印象的だ。かなえと堀が距離を置き前後してスクリーンの上方に向かって歩いていく。二人の向かう方向は、新しい世界にちがいない。(春雷)
監督:今泉力哉
脚本:澤井香織、今泉力哉
原作:豊田徹也
撮影:岩永洋
出演:真木よう子、井浦新、永山瑛太、リリー・フランキー、江口のりこ、中村久美、康すおん、内田理央
かなえ(真木よう子)は亡き父親のあとをつぎ夫婦で銭湯を経営していた。しかしある日、夫の悟(永山瑛太)が突然失踪する。途方に暮れるかなえだったが、何とか銭湯を再開すると、堀(井浦新)と名乗る男が働きたいとやって来る。資格を沢山もち、銭湯組合からの紹介で来たという謎の男との共同生活が始まる。
銭湯を営む女主人と蒸発した夫と言えば「湯を沸すほどの熱い愛」(中野量太監督、2016年)を思い出す。薪が赤々と燃え、その炎の暖かさと湯の温もりが感じられる作品。一方この作品は、銭湯が舞台ではあるが、湯気が立ちのぼる温もりが感じられない。それよりもタイルの冷やかさ、水の冷たさが忍び寄る。死のイメージに全体が覆われている。
大学時代の友人の菅野(江口のりこ)の紹介でかなえは探偵の山崎(リリー・フランキー)に会い、夫の調査を依頼する。カラオケボックスや遊園地で調査報告をする、いかにも胡散臭い山崎だが、調査期間内に悟の居場所を突きとめ、かなえは悟と会うことになる。リリー・フランキーがまさにはまり役で、チャーミングに演じている。やがて、悟の思いがけない半生や堀の素姓、かなえが水中に沈んでいく悪夢の正体が徐々に明らかになっていく。
堀を演じる井浦新はメッセージ性の強い作品に出演しているとの印象が強い。直近では「福田村事件」(森達也監督)があり、遡れば「かぞくのくに」(ヤンヨンヒ監督、2012年)を思い出す。舞台挨拶ではいつもゆっくりと言葉を選び、力強いメッセージを発信していく。堀は無口で誠実そうに見えるが、一方で何を考えているのか分からないミステリアスな人物。かなえに亡き妹の姿を重ねているようだが、かなえに寄り添い支えていく。一見して熱量の少ない演技に見えるが、繊細で緻密な演技の出来る俳優だ。作業着のような服装でも格好良く、さまになっている。井浦新には大人の色気がある。
物語は終盤に向かうにつれて死のイメージが払拭されていくが、それとともにアンダーカレントな深みは希薄になっていく。
ラストシーンの構図は印象的だ。かなえと堀が距離を置き前後してスクリーンの上方に向かって歩いていく。二人の向かう方向は、新しい世界にちがいない。(春雷)
監督:今泉力哉
脚本:澤井香織、今泉力哉
原作:豊田徹也
撮影:岩永洋
出演:真木よう子、井浦新、永山瑛太、リリー・フランキー、江口のりこ、中村久美、康すおん、内田理央