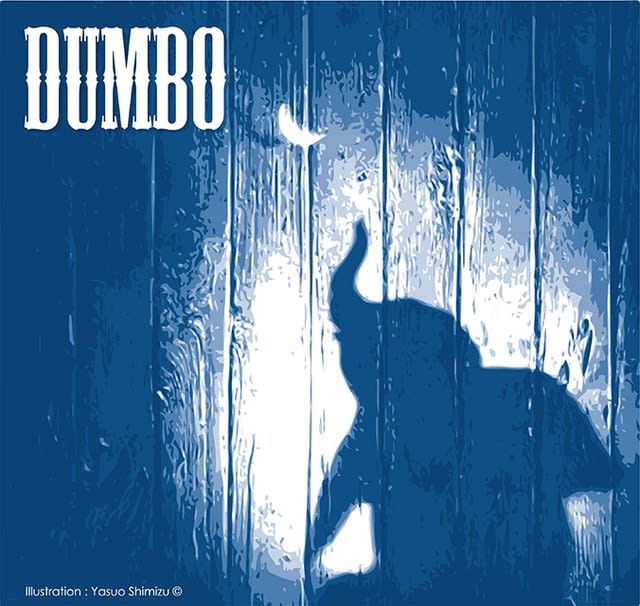ブッカー賞受賞の英国作家ペネロピ・フィッツジェラルドの原作を「死ぬまでにしたい10のこと」のスペイン監督・脚本家イザベル・コイシェが映画化した作品です。
背景は1950年代の英国の田舎が舞台です。古き良きイギリスの街並み、風景が印象的な作品です。ストーリーは戦争で夫を亡くした女性が本屋の無い保守的な街に周囲の反対にあいながらも、東奔西走して本の楽しみを広げたいという思いで、何とか古民家を手に入れ念願の本屋をするのだが……ところがその物件はオールドハウスと呼ばれる歴史的建造物だった。町の有力者ガマート婦人(パトリシア・クラクソン)もまたこの建物を別の用途で使いたいと目を付けていた。これがきっかけでいろんな嫌がらせを受けるはめに。ただそれだけでは終わらない。といった所でしょうか?
好きなシーンは嫌がらせを受けるフローレンス(エミリー・モーティマー)にブランディッシュ(ビル・ナイ)が「嫌がれせを止めるよう言いに行く」とその事を告げるシーン。ブランディッシュはフローレンスの手を取り、そっとキスをする。年齢差ゆえ、素直に思いを伝える事は出来ない。フローレンスも、その気持ちを充分すぎる程わかっている。孤立を恐れず、正しいと信じる事を貫く勇気。同じ心を持つ2人の思いが詰まったシーンでした。
まず思ったのが、出てくるキャストが皆さん上手い!!子役(名前わかりませんが)の子もこの作品に馴染んでいる!!主役のフローレンス演じるエミリー・モーティマー、あまり存じ上げない役者さんなのですが、ハマってましたね。地味だけどいい味出してる役者さんです。他の作品もチェックしたくなりました。「メリーポピンズリターンズ」にも出てるんですね。引きこもりな読書家ビル・ナイ演じる老紳士、渋くて恰好いいです。パトリシア・クラクソン演じる嫌味な権力者。ビル・ナイとの口論のシーンは圧巻です。
あと、印象的だったのが衣装ですね。
衣装さんに拍手を送りたいです。
まずエミリー・モーティマーさんの衣装。地味ではあるけれど、この作品の主役の通り、粋でこだわりがあって芯を感じましたね。
パトリシア・クラクソンさんの衣装は凄かったですね。まるで絵画のような衣装とでも言えばいいですかね。一般人には着こなせません……。子役の衣装もチャーミングで惚れ惚れしました。
伏線もしっかりしていて回収もキチンとしている。脚本もしかり、構成も素晴らしいと思いました。決して明るい映画では無いですが、観ていて「これもエンタメなんだな」そう感じさせられる作品です。
演出でびっくりしたのはエミリー・モーティマー演じるフローレンスが街を離れる時に、子役役の取った行動に「凄い!」そう思ってしまいました。そしてエンディング。素晴らしいすぎる!
改めて映画は脚本だな。そう思える。思わせてくれる映画でした。
映画ってやっぱりいいですね。
個人的に見応えのある作品でした。(CHIDU)
監督:イザベル・コイシュ
脚本:イザベル・コイシュ
原作:ペネロピ・フィッツジェラルド
撮影:ジャン=クロード・ラリュー
出演:エミリー・モーティマ、ビル・ナイ、パトリシア・クラークソン、ジェームズ・ランス、フランシズ・バーバー他
背景は1950年代の英国の田舎が舞台です。古き良きイギリスの街並み、風景が印象的な作品です。ストーリーは戦争で夫を亡くした女性が本屋の無い保守的な街に周囲の反対にあいながらも、東奔西走して本の楽しみを広げたいという思いで、何とか古民家を手に入れ念願の本屋をするのだが……ところがその物件はオールドハウスと呼ばれる歴史的建造物だった。町の有力者ガマート婦人(パトリシア・クラクソン)もまたこの建物を別の用途で使いたいと目を付けていた。これがきっかけでいろんな嫌がらせを受けるはめに。ただそれだけでは終わらない。といった所でしょうか?
好きなシーンは嫌がらせを受けるフローレンス(エミリー・モーティマー)にブランディッシュ(ビル・ナイ)が「嫌がれせを止めるよう言いに行く」とその事を告げるシーン。ブランディッシュはフローレンスの手を取り、そっとキスをする。年齢差ゆえ、素直に思いを伝える事は出来ない。フローレンスも、その気持ちを充分すぎる程わかっている。孤立を恐れず、正しいと信じる事を貫く勇気。同じ心を持つ2人の思いが詰まったシーンでした。
まず思ったのが、出てくるキャストが皆さん上手い!!子役(名前わかりませんが)の子もこの作品に馴染んでいる!!主役のフローレンス演じるエミリー・モーティマー、あまり存じ上げない役者さんなのですが、ハマってましたね。地味だけどいい味出してる役者さんです。他の作品もチェックしたくなりました。「メリーポピンズリターンズ」にも出てるんですね。引きこもりな読書家ビル・ナイ演じる老紳士、渋くて恰好いいです。パトリシア・クラクソン演じる嫌味な権力者。ビル・ナイとの口論のシーンは圧巻です。
あと、印象的だったのが衣装ですね。
衣装さんに拍手を送りたいです。
まずエミリー・モーティマーさんの衣装。地味ではあるけれど、この作品の主役の通り、粋でこだわりがあって芯を感じましたね。
パトリシア・クラクソンさんの衣装は凄かったですね。まるで絵画のような衣装とでも言えばいいですかね。一般人には着こなせません……。子役の衣装もチャーミングで惚れ惚れしました。
伏線もしっかりしていて回収もキチンとしている。脚本もしかり、構成も素晴らしいと思いました。決して明るい映画では無いですが、観ていて「これもエンタメなんだな」そう感じさせられる作品です。
演出でびっくりしたのはエミリー・モーティマー演じるフローレンスが街を離れる時に、子役役の取った行動に「凄い!」そう思ってしまいました。そしてエンディング。素晴らしいすぎる!
改めて映画は脚本だな。そう思える。思わせてくれる映画でした。
映画ってやっぱりいいですね。
個人的に見応えのある作品でした。(CHIDU)
監督:イザベル・コイシュ
脚本:イザベル・コイシュ
原作:ペネロピ・フィッツジェラルド
撮影:ジャン=クロード・ラリュー
出演:エミリー・モーティマ、ビル・ナイ、パトリシア・クラークソン、ジェームズ・ランス、フランシズ・バーバー他