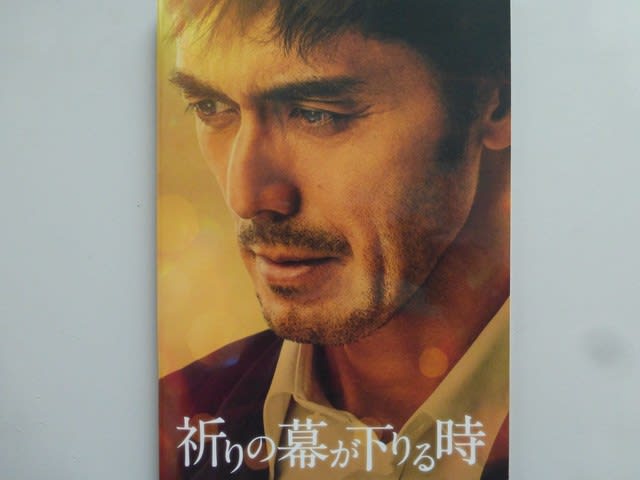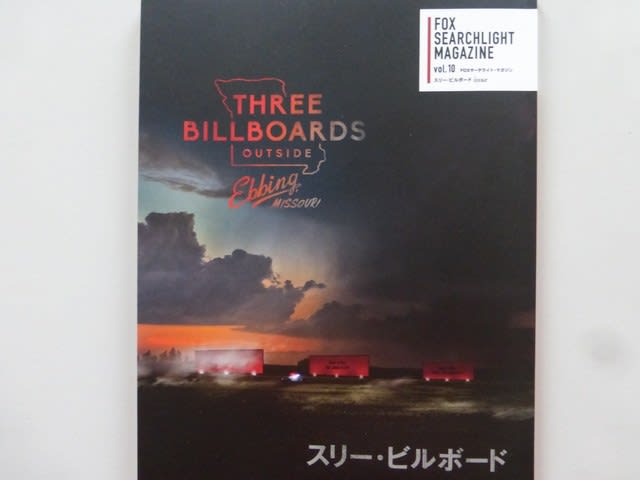2016年の東京国際映画祭で審査員特別賞と最優秀女優賞を受賞した映画。
1930年代を舞台に、劣等民族として差別を受けていたサーミ人として生きることを捨てて、街に出ることを選んだ少女エレ・マリャの人生を描いている。サーミ人とはスウェーデン・ノルウェー・フィンランド・ロシアのラップランド地方でトナカイを飼って暮らす先住民族。エレ・マリャを演じたレーネ=セシリア・スパルロクは、ノルウェーに暮らすサーミ人でトナカイの飼育に従事しており、監督のアマンダ・シェーネル自身もサーミ人の血をひいている。
エレ・マリャは妹と一緒に村の寄宿学校に通っているが、学校ではサーミ語を話すことは禁じられ、スウェーデン語で会話することを強制されている。成績が良く進学することを望んでいるエレ・マリャは、むしろスウェーデン語を話す自分が自慢であった。しかし進学して教師になりたいと相談した時に教師から返ってきた「この学校の生徒は進学できないの。あなたたちの脳は文明に適応できない。それよりもサーミ人としての暮らしや伝統を残すようにしなさい」という言葉に、エレ・マリャは屈辱に傷つき憤りを覚える。
都会から来た人類学者と思われる人物が彼女たちを身体検査に集め、頭蓋骨の大きさなどを測定し、果ては全裸の写真を撮影する場面が出てくる。これはアイヌ民族に対して日本政府が行った調査とも通している。サーミ語での会話や、ヨイクというサーミの民謡を歌っているのを聞き咎めてはすかさずに罰を与える一方で、伝統的な生活様式を守れと矛盾したことを平然と言ってのける。差別をする側が持ち出す非科学的で非情な論理は、時代や国・地域が違っても同じだ。他者の言語や文化を奪い、さらに劣等性を強調して、社会の底辺で暮らすことを当然と見なす。
エレ・マリャはスウェーデン人のふりをして忍び込んだ村の夏祭りで、都会の少年ニクラスと出会い恋をする。トナカイを飼う暮らしから何とかして抜け出したい彼女は、ニクラスを頼って街へ行くことを決意する。ラップランドから一人で街に出てきた少女を待ち受ける運命は厳しく辛いものであった。しかし、私はスウェーデン語を話すスウェーデン人、サーミ族出身だからといって自分の望みを捨てることは出来ないと、エレ・マリャは持ち前の強い意志で自らの人生を切り拓いていく。
エレ・マリャを演じたレーネ=セシリア・スパルロクの、物事の本質を真っ直ぐに鋭く見つめる眼差しがとても印象的な映画だ。(久)
原題:Sameblod
監督:アマンダ・シェーネル
脚本:アマンダ・シェーネル
撮影:ソフィア・オルソン、ペトルゥス・シェービング
出演:レーネ=セシリア・スパルロク、ミーア=エリーカ・スパルロク、マイ=ドリス・リンピ、ユリウス・フレイシャンデル、オッレ・サッリ、ハンナ・アルストロム