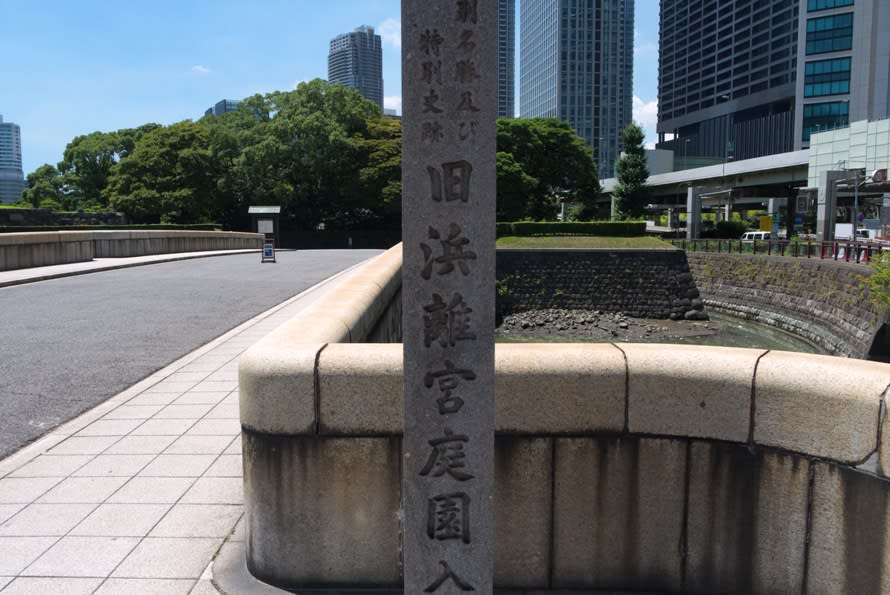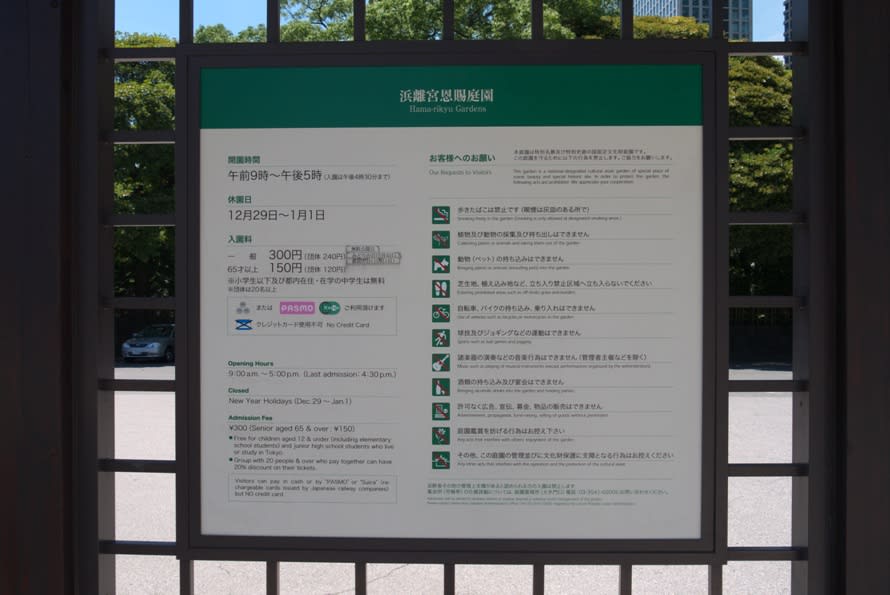2012年8月3日 東京ウォーカーより引用
3月17日より大阪天保山特設ギャラリーで公開され、記録的な動員となった「ツタンカーメン展~黄金の秘宝と少年王の真実~」。関西ではあまりの人気に会期が予定より約1か月延長され、来場者数93万3130人を記録したという“お化けイベント”だ。同展がいよいよ8月4日(土)より、東京・上野の森美術館に上陸!オープニングセレモニーでは「東京は、日本美術史上最多の記録を作るのでは」と株式会社フジテレビジョン代表取締役会長日枝久氏も力を込めた。早速、編集部では、ひとあし先にプレス内覧会へ。その人気の秘密を探ってきた。
同展は、2004年スイス・バーゼルを皮切りにボン、ニューヨーク、ロンドン、メルボルンなど世界各都市を巡回し、1000万人以上という驚異的な入場者数を記録した話題の展覧会。この世界的な巡回も、いよいよ東京が最後となり、さらなる注目が集まっている。
「今回、世界各国を巡回してきて、日本の東京・上野の森美術館がラストとなります。東京で開催されるのは、1965年に開催され、日本美術展史上・最多入場数を記録した“ツタンカーメン展”から47年ぶり。この後は、エジプト考古学博物館(カイロ博物館)へ戻り、新設されるグレートクエロミュージアムに返却されるため、今後、貸し出しされることはないと思われます」と同展スタッフ。日本では、もう一生見ることはできない(!?)展覧会なのだ。歴史的にも貴重であり、まさに一生に一度見られるかどうかという展示品の数々は見逃せない。
また、世界最大のミステリーに触れることができるというのもポイントが高い。古代エジプト第18王朝のツタンカーメン王は、なんと9歳で即位し、19歳の若さで死亡したと推定されており、ほかの王墓が盗掘されていたにもかかわらず、ツタンカーメン王墓はほとんど完全な形で副葬品が残っていたこと、発掘にかかわった人々が次々と謎の死をとげたことなどから“20世紀最大のミステリー”と呼ばれ、注目されているのだ。
近年、この少年王ツタンカーメンの謎が、科学と考古学の融合によって解き明かされているとのことだが、世界的なエジプト考古学者ザビ・ハワス博士は、CTスキャンやDNA鑑定によって、ツタンカーメン王の健康状態、死因、死亡年齢、親子関係など、今まで仮説の域を出ることがなかった真実が明らかにすることに成功。今回の展覧会も、3000年以上のミステリーが解き明かされて行く面白さを加えた、斬新で画期的な内容となっている。
今回、展示されるのは「ツタンカーメンの黄金のカノポス」(ツタンカーメンの内蔵が保管されていた器)をはじめ、ツタンカーメンのミイラが身にまとっていた黄金の襟飾りや短剣など、ツタンカーメン王墓から見つかった副葬品約50点など、日本未公開の展示品を含むエジプト考古学博物館(カイロ博物館)所蔵の122点。是非ともお見逃しのないよう!【東京ウォーカー】
2012年8月14日 東京ウォーカーより引用
東京が“エジプト”ブームに沸いている。上野の「ツタンカーメン展」と六本木の「大英博物館 古代エジプト展」が同時期に開催され、いずれも多くの来場者で盛り上がっているのだ。この夏の東京のアートシーンを牽引する“2大エジプト展”の魅力を紹介しよう。
まずは上野の森美術館にて開催されている「ツタンカーメン展」。12月9日(日)まで開催中の同展覧会は、先に開催された大阪では会期中に93万人が来場した行列必至のイベントだ。東京でも初日となる8月4日には、開場前に500人を越える行列ができ、開場時間を早める措置が取られた。また、公式HPで会場の様子をつぶやく“イマつぶ”サービスでも、8月13日は15時前後に当日券販売の終了が告げられるなど、ますますの盛り上がりが見て取れる。
それもそのはず、この展覧会、東京での開催は47年ぶりとなるのだが、前回1965年には今なお日本美術展史上・最多入場数となる約295万人の来場者数(東京、京都、福岡を合わせた総入場者数)を記録している、まさしく“黄金の展覧会”なのだ。
もちろん内容もゴージャス。元エジプト考古大臣のザヒ・ハワス博士監修のもと、「ツタンカーメンの黄金のカノポス」(ツタンカーメンの内蔵が保管されていた器)をはじめ、ツタンカーメンのミイラが身にまとっていた黄金の襟飾りや短剣など、日本未公開の展示品を含む122点の遺物や最新の研究結果を惜しげもなく公開。3300年前に存在した古代エジプトの少年王・ツタンカーメンのなぞに迫っている。長さ2m以上の黄金の棺など美術品としても優れた展示物が多く、行列覚悟で“一見の価値アリ”だろう。
次に六本木。こちらは森アーツセンターギャラリーにて9月17日(祝)まで「大英博物館 古代エジプト展」が開催中なのだが、こちらも8月8日(水)に来場者数が10万人を超える人気ぶりとなっている。
同展の見どころは、大英博物館の所蔵品約180点によってひも解かれる、古代エジプトの人々が信じた「死後の世界」。来世への旅路に役立つようにと作られたさまざまな「死者の書」など、貴重な遺物が公開されている。
この「死者の書」は、死者が来世へたどり着けるように作られたいわゆる“ガイドブック”。なんと約37m(!)もある世界最長の死者の書「グリーンフィー ルド・パピルス」などを通じて、古代エジプトの人々の想像していた“死後の世界”について学ぶことができるのが、同展の魅力だろう。
骨太な内容で東京に“エジプトブーム”を巻き起こしている2大展覧会。この夏は東京で3300年前の古代エジプトミステリーに触れてみてはいかがだろう。【東京ウォーカー】
2012年8月18日 東京ウォーカーより引用
東京・上野の森美術館にて開催されている「ツタンカーメン展」。先に開催された大阪会場では会期中に93万人が来場した行列必至のイベントだ。開幕以降、来場者は伸び続け、8月13日から15日までのお盆期間中も3日連続で1万人超えを記録、入場まで最大5時間待ちという盛況っぷり。こうくると、暑いなかの行列は辛いと思ってしまうが、ご安心あれ。同展では、混雑状況により入場整理券を発行。屋外で長時間の待ち列に並ばず、入館までの待ち時間を有意義に過ごせるのだ。
【写真を見る】「チュウヤの人型棺」。あまり見つめると吸い込まれるほどパワーがある!?
お盆シーズン平日初日の8月13日にも、8時25分のオープン直後より瞬く間に長蛇の列が伸び、8時45分より整理券の配布を開始。30分につき450枚配布した整理券は、僅か10分程のペースでさばけて、昼過ぎには最大5時間先の整理券を配布する状況だったそうだ。また、お盆期間中に開館時間が延長されていたが、あまりの人気で(!?)、8月中は9時から18時(最終入場17時)までとその後の延長も発表されている。夏休み中に予定している方は是非ともオープン時間を狙ってみよう!
この展覧会、東京での開催は47年ぶりとなるが、前回の1965年には今なお日本美術展史上最多入場数となる約295万人の来場者数(東京、京都、福岡を合わせた総入場者数)を記録、まさしく“黄金の展覧会”だ。
今回は、元エジプト考古大臣のザヒ・ハワス博士監修のもと「ツタンカーメンの黄金のカノポス」(ツタンカーメンの内蔵が保管されていた器)をはじめ、ツタンカーメンのミイラが身にまとっていた黄金の襟飾りや短剣など、日本未公開の展示品を含む122点の遺物や最新の研究結果を公開している。3300年前に存在した古代エジプトの少年王ツタンカーメンの謎を迫っているので、ミステリー好きも見逃せない!【東京ウォーカー】

インターネットのニュースで現在上野の森美術館で開催されている「エジプト考古学博物館所蔵 ツタンカーメン展」の入場者数が100万人を突破したというニュースが先日見ました。その時は「へぇ、そうなんだ」と流したきりでしたが、先日東京へ出かけた帰りに上野による機会があったので、その時に写真を撮ってきました。

以前に特別展を観覧した時には無かった案内板が新たに設置されていました。確かに上野の森美術館周辺は散策道や広場が入り組んでいるので、初めて来たお客さんたちは迷ってしまうことが多いと思いますので、これがあると便利ですね。

緑が8月中旬に観覧した時はもっと人の出が多かったと記憶していますが、この日も結構な混み具合でした。当然のように入場整理券の配布が実施されていました。