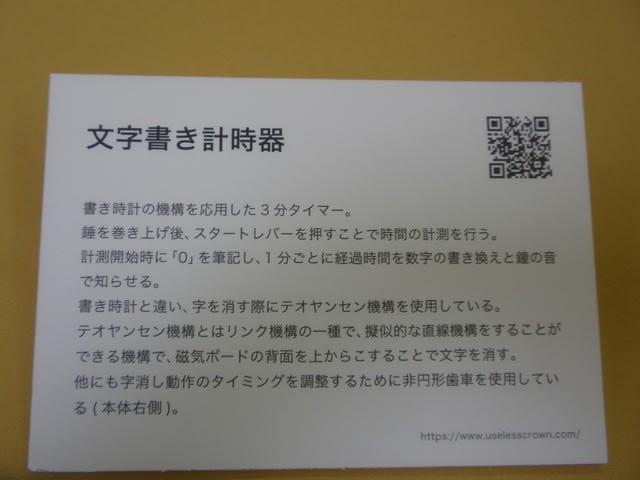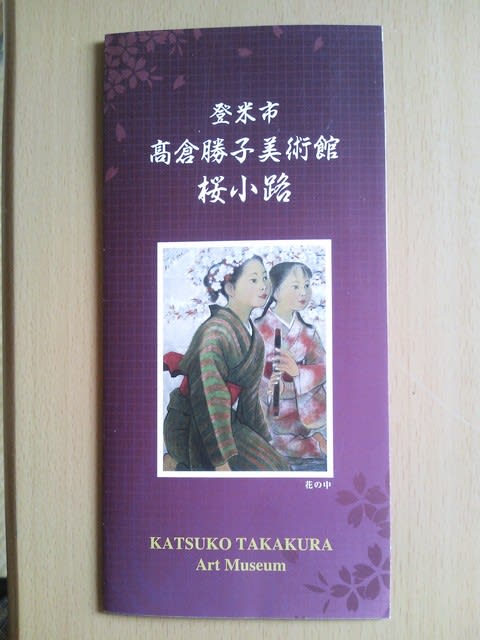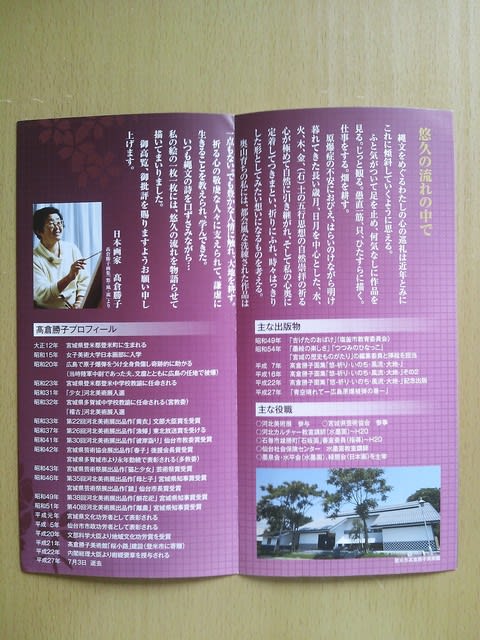「生きて帰ってきた男」(小熊英二著)を読む
前回の「終わらざる夏」に続いて、また戦争関連である。
今回は小説ではなくノンフィクションである。著者が自分の父から聞き出した話をまとめたものである。
副題にある通り「ある日本兵の戦争と戦後」である。
この本は以前に新聞広告に出ていて、いつかは読んでみたいと思っていた。前にも書いた通り自分の父
の生きた時代のことが知りたかったこともあった。
著者の父、謙二さん(1925年生まれ)は「終わらざる夏」の主人公たちのように終戦が近くなってから
召集され、その後シベリア抑留を経験した人であった。
また、謙二さんは北海道佐呂間町に生まれ、召集前は東京で育ち、シベリヤから帰還後は岡山、新潟
などで暮らしたこともあり、東京のほか、地方での生活も経験していた。したがって、一部地域だけ
ではなく広い範囲の見分も含まれている。そのため背景にある日本経済や社会の状態も分かる証言
になっている。
この本を読んでわかるのは、謙二さんの一家は庶民の家庭なので、貧しい生活であり、また戦前は
それがほとんどだったと思う。
第1章の「入営まで」は、小熊家の歴史と19歳で招集されるまでの謙二さんの生い立ちである。
第2章の「収容所へ」、第3章「シベリア」、第4章「民主運動」は戦争からシベリア抑留のこと、
第5章の「流転生活」、第6章「結核療養所」、第7章「高度成長」は戦後の生活と社会の変化
第8章の「戦争の記憶」は、生活が落ち着いて自宅を建築してからの、東京での生活である。
謙二さんも仕事に取り組んでいる時期は、戦争の話などはしなかった。生活の安定とともに、戦争の記憶を
振り返る余裕ができていったという。
「チタ会」という抑留中の収容所の戦友会のようなものにも参加した。
それらの戦友会も高度成長期からはじまり、1990年代には不活発になり、やがて活動中止になったりした。
そのような中、同年兵で亡くなった人のことが気になり、友人の死の様子を親族に知らせることを行い、
やり終えたことで肩の荷を下ろしたような気がしたと言う。
そして第9章「戦後補償裁判」
前章で、戦争の記憶とは一定のふんぎりがつけられたと思ったが、さまざまな偶然から元シベリア抑留者の
朝鮮人皇軍兵士と文通をはじめ、日本政府を相手とした戦後補償裁判に加わることになった。
1982年、アムネスティ・インターナショナルの会員になった。
1988年、「不戦兵士の会」に参加することになった。
1989年、昭和天皇が亡くなり、ベルリンの壁が崩壊した。
1991年、収容所のあったチタを再訪した。
1988年、ソ連抑留者に対して、日本政府が「慰労金」をだす「平和祈念事業」が行われることになった。
このような事業の背景には、戦後の日本政府は戦争被害者に補償を行わない姿勢をとっていたからである。
その代わりに行われたのは、軍人恩給制度の拡充であった。しかし、軍人恩給は軍務が一定期間を超え
ないと受給資格が発生しない。また、恩給は勤務期間や階級で受給額に上下があった。
謙二さんのように敗戦近くに召集された兵士は、そのほとんどが恩給欠格者であった。
そのために、ソ連抑留者の「平和祈念事業特別基金」はこの軍人恩給欠格者を対象に行われた。
では、こうした事業が「見舞い」や「慰労」の形態をとっているのはなぜか。これは日本政府に戦争被害者に
「補償」を行わないという原則があるためのようである。
1994年、原爆被爆者援護法が成立、その趣旨は「補償」ではなく、あくまで医療援助であった。
1995年、元「従軍慰安婦」への「償い事業」が開始された。これは政府ではなく民間拠出の「女性のための
アジア平和国民基金」が「償い金」を支給し、あわせて政府が医療・福祉支援事業を行うという方式だった。
つまり、日本政府がとってきた原則は、戦争被害は「国民がひとしく受忍」すべきもので「補償」は行わない。
強い要求があった場合には、「慰労」「見舞い」「医療援助」ならば行う。ただし、政府の支出ではなく、民間
団体や外郭団体によって設けられた基金の場合には、多少の柔軟性はありうる。
1988年のシベリア抑留者への「慰労」はその後の他国の戦争被害者への対応の原型を作ったとも言える。
元ソ連抑留者による補償要求運動の経緯概説
・抑留者による補償要求運動は戦後早くから存在した。
・しかし、1956年の日ソ共同宣言によって、日本政府はソ連への賠償請求権を放棄していた。
これは、韓国政府や他のアジア諸国政府が一連の国交回復交渉で、日本に対する賠償請求権を放棄した
のと同じである。ただし、韓国政府の日韓基本条約は1965年である。
・そのため抑留者たちは1980年代から、自分たちの労働賃金の支払いを日本政府に求める運動が起きた。
その論拠は、軍人の生活費用と賃金は国が支払う義務があり、捕虜となった場合でも、生活費用と賃金は
出身国が負担するのが国際慣行であるというものだった。
1949年のジュネーブ条約(日本の批准は1953年)においても、捕虜の労賃は、使役国が発行した労働
証明書をもとに捕虜の所属国が支払うことになっていた。
これにより南方戦線での捕虜には、日本政府は戦後に賃金を払っていた。しかしソ連は労働証明書を
発行しておらず、日本政府も賃金を払っていなかった。
・1981年、全抑協の原告62名が、未払い労働賃金のなどの支払いを国に求めて、東京地裁に提訴した。
・しかし、1989年にでた地裁判決は、原告の敗訴であった。判決理由は、原告の大半はジュネーブ条約
締結以前に帰国していたから条約適用外であること、そして「原告等の損害は、国民が等しく受忍すべき
戦争被害」であるといったことだった。
・これに対して、全抑協は1991年にゴルバチョフが来日した際労働証明書の発行を求めその後に実現した。
さらに1993年に来日したエリツィン大統領は「ロシア政府、国民を代表し、このような非人間的な行為を
謝罪する」と述べた。
・全抑協は地裁判決を不服として上告した。
・しかし、1993年には東京高裁が、1997年には最高裁が原告の敗訴を判決した。ただし最高裁は、
原告らが「不満を抱く心情も理解できないものではない」として、補償は「立法府の裁量」とした。
上記運動や裁判と別個の、政権与党との協調によって補償を実現しようとする動き
・1982年、政府と与党の合意によって、総理府総務長官の私的諮問機関「戦後処理問題懇談会」が設立
された。そこでは、シベリア抑留、恩給欠格者、満州その他からの引揚者の在外資産の三点について、
何らかの補償措置を行うことが検討された。
・検討会の答申は、1984年にだされ、シベリア抑留については何らかの形で「慰藉」を行うべきだと提言、
ただし特定対象に対する新たな政策措置は公平性を欠くという原則も述べられていた。
・1986年、自民党はシベリア抑留者に特別給付金を支給する法律案をまとめた。しかし、これは
法律案提出には至らなかった。
・1988年、平和祈念事業特別基金の設置法案が可決され、同年から事業が開始された。
しかし、謙二さんは当初この平和祈念事業に請求を出さなかった。
「こんなものはごまかしだ。今更金なぞいるか、と思った」
ところが、1990年4月、謙二さんはこの慰労金を請求した。その理由は、同じ収容所にいた朝鮮系中国人
の元日本兵に請求資格がないことを知り、彼と分け合おうと考えたからだった。
謙二さんが朝鮮系中国人の元日本兵、呉さんを知ったのは1989年のこと。
呉さんの手記をみて、その人が同じ収容所に後から来た人であることに気づき、手紙を書いた。何度かの
やり取りの後、呉さんが平和祈念事業の対象外とされていることを知り、「この金は彼のような人にこそ
支給されるべきだ」と思い、自分の請求した慰労金から半分を呉さんに送ったのである。
しかし呉さんは、日本国籍がないために対象外とされることに、納得がいかないようだった。謙二さんは
さまざま調べ、難しさを説明する手紙を送った。しかし呉さんは納得せず、1996年呉さんが来日して訴訟を
起こすことになり、謙二さんに共同原告になってくれと誘いが来た。
謙二さんは共同原告となることを承諾した。「日本人の一人として、呉さんには何かしないといけないと思い
引き受けた」「面倒になるとか、まわりの評判に気を遣うとかは、まったく考えなかった。」
1996年9月、東京地裁に訴状が提出された。
第一回公判は1997年1月、第二回公判は5月、原告に意見陳述の機会が与えられた。
謙二さんが意見陳述した。「呉さんは朝鮮族の日本国民として徴兵され、シベリア抑留にあった。私は
シベリア抑留に対する慰労状と慰労金を受け取った、しかし、呉さんは外国人であるとの理由で対象と
なっていない。日本国民であるからと徴兵しシベリア抑留をさせながら、同じ日本国が今となっては外国人
だからダメというのは論理的に成り立ちません。これは明らかな差別であり、国際的に通用しない人権無視
であります。このような問題は国際的に通用する論理で考える必要があります。
第二次大戦中の他の国でも異民族・外国籍の人々が軍人として、その国のために戦いました。その補償
に国籍などの差別をしている国はありません。戦勝国はもちろん、敗戦国においても同様です。これは
近代国家として常識であります。」
2000年2月、東京地裁から請求棄却の判決が出た。その趣旨は、①損害賠償については「国民のひとしく
受忍しなければならなかった戦争被害」だから補償できない。②公式陳謝の要求については、「立法府の
裁量的判断だ」というものだった。
この訴訟はその後に上告されたが、2001年に東京高裁で請求棄却、さらに2002年に最高裁で請求棄却
となって結審した。
2005年、全抑協の最後の取り組み、野党3党が抑留期間に応じた支払い法案を衆参両院に提出、
これは2006年に否決された。
だが、与党側は妥協的法案を提出、平和祈念特別基金を2010年に廃止し、基金の残額を財源として、
抑留者・引揚者・恩給欠格者を対象に「特別慰労品」を配るというもの。この法案は可決された。
2010年、民主党政権の下で「シベリア特措法」が成立した。抑留期間に応じた給付金が支給された。
これを成果として、全抑協は2011年5月に解散した。
「あとがき」より
この本は2つの点で、これまでの「戦争体験記」と一線を画している。
①戦争体験だけでなく、戦前及び戦後の生活史を描いたこと
②同時代の経済、政策、法制などに留意しながら、当時の階層移動、学歴取得、職業選択、産業構造など
の状況を一人の人物を通して描いている。
本書はオーラルヒストリーであり、民衆史、社会史である。
本書は著者の父を対象として、平均的な日本人について、危機的な経験や英雄的な瞬間だけでなく、
日常的な生活も含めて描いている。
それらを総合的に把握し、同時代の社会的文脈の中に位置づけてこそ、立体的な歴史記述になるのでは
ないか。
本書は「記録されなかった多数派」の生活史である。一人の人物という細部から、人間を取り囲んでいる
全体の構造、東アジアの歴史、日本の中の地方、階層、様々な政策、そのような全体をかいまみようと
試みたことである。
この本を読みながら、戦前、戦後の歴史とともに、亡くなった私の父のことも考えてきた。
戦後復員してからの生活は自分の父や兄弟姉妹の生活のために、やみくもに働いてきたようである。
結婚して私たちが生まれてからも、私たちのために働いてくれた。昭和が終わるころには自分の仕事も
定年になり、やはり謙二さんと同じように戦友会や亡くなった方の墓参に赴いていた。
私たちには戦争のことはあまり話はしなかった。話したいこともあっただろうが、実態を知らないもの、その
時々の事情が分からないものには話し難いことがあったと思う。私たちも父の話はあまり聞いてあげようとも
しなかった。
同じようなことで、話をしないままに亡くなった方がたくさんいたであろう。そしてそういう方々は、だんだん
少なくなってきていると思う。
今世の中は、憲法改正などを叫んでいるようだが、そのまえにもう少し考えるべきことがあるのでは
ないだろうか。また同じような苦しみをする人たちが出るのではないだろうか。
過去に生きた人たちの経験にも耳を傾け、もう少し考え方を深めて、新しい方法を考えてほしいものである。
前回の「終わらざる夏」に続いて、また戦争関連である。
今回は小説ではなくノンフィクションである。著者が自分の父から聞き出した話をまとめたものである。
副題にある通り「ある日本兵の戦争と戦後」である。
この本は以前に新聞広告に出ていて、いつかは読んでみたいと思っていた。前にも書いた通り自分の父
の生きた時代のことが知りたかったこともあった。
著者の父、謙二さん(1925年生まれ)は「終わらざる夏」の主人公たちのように終戦が近くなってから
召集され、その後シベリア抑留を経験した人であった。
また、謙二さんは北海道佐呂間町に生まれ、召集前は東京で育ち、シベリヤから帰還後は岡山、新潟
などで暮らしたこともあり、東京のほか、地方での生活も経験していた。したがって、一部地域だけ
ではなく広い範囲の見分も含まれている。そのため背景にある日本経済や社会の状態も分かる証言
になっている。
この本を読んでわかるのは、謙二さんの一家は庶民の家庭なので、貧しい生活であり、また戦前は
それがほとんどだったと思う。
第1章の「入営まで」は、小熊家の歴史と19歳で招集されるまでの謙二さんの生い立ちである。
第2章の「収容所へ」、第3章「シベリア」、第4章「民主運動」は戦争からシベリア抑留のこと、
第5章の「流転生活」、第6章「結核療養所」、第7章「高度成長」は戦後の生活と社会の変化
第8章の「戦争の記憶」は、生活が落ち着いて自宅を建築してからの、東京での生活である。
謙二さんも仕事に取り組んでいる時期は、戦争の話などはしなかった。生活の安定とともに、戦争の記憶を
振り返る余裕ができていったという。
「チタ会」という抑留中の収容所の戦友会のようなものにも参加した。
それらの戦友会も高度成長期からはじまり、1990年代には不活発になり、やがて活動中止になったりした。
そのような中、同年兵で亡くなった人のことが気になり、友人の死の様子を親族に知らせることを行い、
やり終えたことで肩の荷を下ろしたような気がしたと言う。
そして第9章「戦後補償裁判」
前章で、戦争の記憶とは一定のふんぎりがつけられたと思ったが、さまざまな偶然から元シベリア抑留者の
朝鮮人皇軍兵士と文通をはじめ、日本政府を相手とした戦後補償裁判に加わることになった。
1982年、アムネスティ・インターナショナルの会員になった。
1988年、「不戦兵士の会」に参加することになった。
1989年、昭和天皇が亡くなり、ベルリンの壁が崩壊した。
1991年、収容所のあったチタを再訪した。
1988年、ソ連抑留者に対して、日本政府が「慰労金」をだす「平和祈念事業」が行われることになった。
このような事業の背景には、戦後の日本政府は戦争被害者に補償を行わない姿勢をとっていたからである。
その代わりに行われたのは、軍人恩給制度の拡充であった。しかし、軍人恩給は軍務が一定期間を超え
ないと受給資格が発生しない。また、恩給は勤務期間や階級で受給額に上下があった。
謙二さんのように敗戦近くに召集された兵士は、そのほとんどが恩給欠格者であった。
そのために、ソ連抑留者の「平和祈念事業特別基金」はこの軍人恩給欠格者を対象に行われた。
では、こうした事業が「見舞い」や「慰労」の形態をとっているのはなぜか。これは日本政府に戦争被害者に
「補償」を行わないという原則があるためのようである。
1994年、原爆被爆者援護法が成立、その趣旨は「補償」ではなく、あくまで医療援助であった。
1995年、元「従軍慰安婦」への「償い事業」が開始された。これは政府ではなく民間拠出の「女性のための
アジア平和国民基金」が「償い金」を支給し、あわせて政府が医療・福祉支援事業を行うという方式だった。
つまり、日本政府がとってきた原則は、戦争被害は「国民がひとしく受忍」すべきもので「補償」は行わない。
強い要求があった場合には、「慰労」「見舞い」「医療援助」ならば行う。ただし、政府の支出ではなく、民間
団体や外郭団体によって設けられた基金の場合には、多少の柔軟性はありうる。
1988年のシベリア抑留者への「慰労」はその後の他国の戦争被害者への対応の原型を作ったとも言える。
元ソ連抑留者による補償要求運動の経緯概説
・抑留者による補償要求運動は戦後早くから存在した。
・しかし、1956年の日ソ共同宣言によって、日本政府はソ連への賠償請求権を放棄していた。
これは、韓国政府や他のアジア諸国政府が一連の国交回復交渉で、日本に対する賠償請求権を放棄した
のと同じである。ただし、韓国政府の日韓基本条約は1965年である。
・そのため抑留者たちは1980年代から、自分たちの労働賃金の支払いを日本政府に求める運動が起きた。
その論拠は、軍人の生活費用と賃金は国が支払う義務があり、捕虜となった場合でも、生活費用と賃金は
出身国が負担するのが国際慣行であるというものだった。
1949年のジュネーブ条約(日本の批准は1953年)においても、捕虜の労賃は、使役国が発行した労働
証明書をもとに捕虜の所属国が支払うことになっていた。
これにより南方戦線での捕虜には、日本政府は戦後に賃金を払っていた。しかしソ連は労働証明書を
発行しておらず、日本政府も賃金を払っていなかった。
・1981年、全抑協の原告62名が、未払い労働賃金のなどの支払いを国に求めて、東京地裁に提訴した。
・しかし、1989年にでた地裁判決は、原告の敗訴であった。判決理由は、原告の大半はジュネーブ条約
締結以前に帰国していたから条約適用外であること、そして「原告等の損害は、国民が等しく受忍すべき
戦争被害」であるといったことだった。
・これに対して、全抑協は1991年にゴルバチョフが来日した際労働証明書の発行を求めその後に実現した。
さらに1993年に来日したエリツィン大統領は「ロシア政府、国民を代表し、このような非人間的な行為を
謝罪する」と述べた。
・全抑協は地裁判決を不服として上告した。
・しかし、1993年には東京高裁が、1997年には最高裁が原告の敗訴を判決した。ただし最高裁は、
原告らが「不満を抱く心情も理解できないものではない」として、補償は「立法府の裁量」とした。
上記運動や裁判と別個の、政権与党との協調によって補償を実現しようとする動き
・1982年、政府と与党の合意によって、総理府総務長官の私的諮問機関「戦後処理問題懇談会」が設立
された。そこでは、シベリア抑留、恩給欠格者、満州その他からの引揚者の在外資産の三点について、
何らかの補償措置を行うことが検討された。
・検討会の答申は、1984年にだされ、シベリア抑留については何らかの形で「慰藉」を行うべきだと提言、
ただし特定対象に対する新たな政策措置は公平性を欠くという原則も述べられていた。
・1986年、自民党はシベリア抑留者に特別給付金を支給する法律案をまとめた。しかし、これは
法律案提出には至らなかった。
・1988年、平和祈念事業特別基金の設置法案が可決され、同年から事業が開始された。
しかし、謙二さんは当初この平和祈念事業に請求を出さなかった。
「こんなものはごまかしだ。今更金なぞいるか、と思った」
ところが、1990年4月、謙二さんはこの慰労金を請求した。その理由は、同じ収容所にいた朝鮮系中国人
の元日本兵に請求資格がないことを知り、彼と分け合おうと考えたからだった。
謙二さんが朝鮮系中国人の元日本兵、呉さんを知ったのは1989年のこと。
呉さんの手記をみて、その人が同じ収容所に後から来た人であることに気づき、手紙を書いた。何度かの
やり取りの後、呉さんが平和祈念事業の対象外とされていることを知り、「この金は彼のような人にこそ
支給されるべきだ」と思い、自分の請求した慰労金から半分を呉さんに送ったのである。
しかし呉さんは、日本国籍がないために対象外とされることに、納得がいかないようだった。謙二さんは
さまざま調べ、難しさを説明する手紙を送った。しかし呉さんは納得せず、1996年呉さんが来日して訴訟を
起こすことになり、謙二さんに共同原告になってくれと誘いが来た。
謙二さんは共同原告となることを承諾した。「日本人の一人として、呉さんには何かしないといけないと思い
引き受けた」「面倒になるとか、まわりの評判に気を遣うとかは、まったく考えなかった。」
1996年9月、東京地裁に訴状が提出された。
第一回公判は1997年1月、第二回公判は5月、原告に意見陳述の機会が与えられた。
謙二さんが意見陳述した。「呉さんは朝鮮族の日本国民として徴兵され、シベリア抑留にあった。私は
シベリア抑留に対する慰労状と慰労金を受け取った、しかし、呉さんは外国人であるとの理由で対象と
なっていない。日本国民であるからと徴兵しシベリア抑留をさせながら、同じ日本国が今となっては外国人
だからダメというのは論理的に成り立ちません。これは明らかな差別であり、国際的に通用しない人権無視
であります。このような問題は国際的に通用する論理で考える必要があります。
第二次大戦中の他の国でも異民族・外国籍の人々が軍人として、その国のために戦いました。その補償
に国籍などの差別をしている国はありません。戦勝国はもちろん、敗戦国においても同様です。これは
近代国家として常識であります。」
2000年2月、東京地裁から請求棄却の判決が出た。その趣旨は、①損害賠償については「国民のひとしく
受忍しなければならなかった戦争被害」だから補償できない。②公式陳謝の要求については、「立法府の
裁量的判断だ」というものだった。
この訴訟はその後に上告されたが、2001年に東京高裁で請求棄却、さらに2002年に最高裁で請求棄却
となって結審した。
2005年、全抑協の最後の取り組み、野党3党が抑留期間に応じた支払い法案を衆参両院に提出、
これは2006年に否決された。
だが、与党側は妥協的法案を提出、平和祈念特別基金を2010年に廃止し、基金の残額を財源として、
抑留者・引揚者・恩給欠格者を対象に「特別慰労品」を配るというもの。この法案は可決された。
2010年、民主党政権の下で「シベリア特措法」が成立した。抑留期間に応じた給付金が支給された。
これを成果として、全抑協は2011年5月に解散した。
「あとがき」より
この本は2つの点で、これまでの「戦争体験記」と一線を画している。
①戦争体験だけでなく、戦前及び戦後の生活史を描いたこと
②同時代の経済、政策、法制などに留意しながら、当時の階層移動、学歴取得、職業選択、産業構造など
の状況を一人の人物を通して描いている。
本書はオーラルヒストリーであり、民衆史、社会史である。
本書は著者の父を対象として、平均的な日本人について、危機的な経験や英雄的な瞬間だけでなく、
日常的な生活も含めて描いている。
それらを総合的に把握し、同時代の社会的文脈の中に位置づけてこそ、立体的な歴史記述になるのでは
ないか。
本書は「記録されなかった多数派」の生活史である。一人の人物という細部から、人間を取り囲んでいる
全体の構造、東アジアの歴史、日本の中の地方、階層、様々な政策、そのような全体をかいまみようと
試みたことである。
この本を読みながら、戦前、戦後の歴史とともに、亡くなった私の父のことも考えてきた。
戦後復員してからの生活は自分の父や兄弟姉妹の生活のために、やみくもに働いてきたようである。
結婚して私たちが生まれてからも、私たちのために働いてくれた。昭和が終わるころには自分の仕事も
定年になり、やはり謙二さんと同じように戦友会や亡くなった方の墓参に赴いていた。
私たちには戦争のことはあまり話はしなかった。話したいこともあっただろうが、実態を知らないもの、その
時々の事情が分からないものには話し難いことがあったと思う。私たちも父の話はあまり聞いてあげようとも
しなかった。
同じようなことで、話をしないままに亡くなった方がたくさんいたであろう。そしてそういう方々は、だんだん
少なくなってきていると思う。
今世の中は、憲法改正などを叫んでいるようだが、そのまえにもう少し考えるべきことがあるのでは
ないだろうか。また同じような苦しみをする人たちが出るのではないだろうか。
過去に生きた人たちの経験にも耳を傾け、もう少し考え方を深めて、新しい方法を考えてほしいものである。