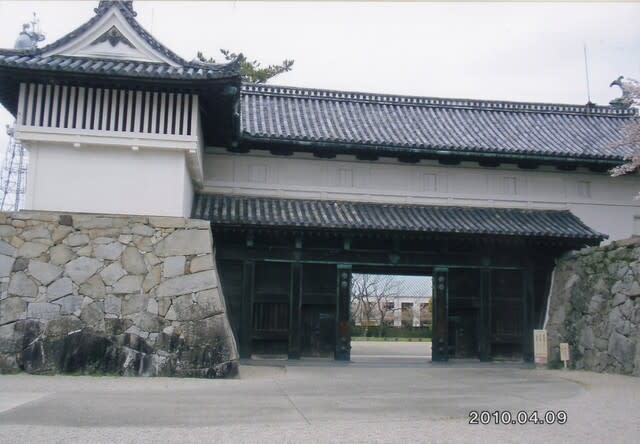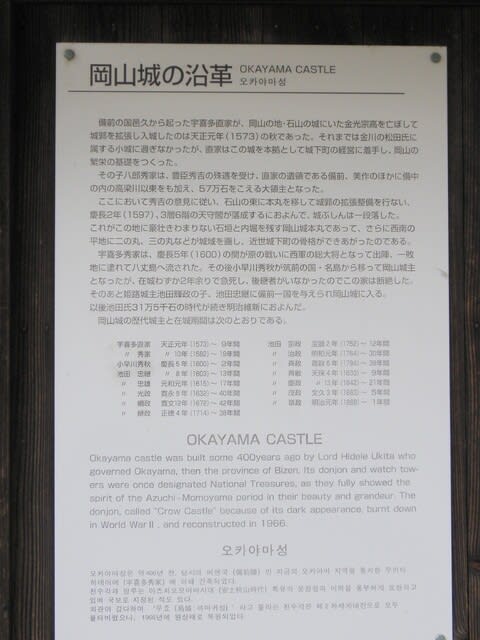乙巳の変(いつしのへん)というのは、昔は「大化の改新」と教わったものである。
私の中・高校生の頃はである。
今手元にある高校時代の「日本史辞典」(旺文社発行)には、
「645年(大化1年)に始まる政治大改革」とある。
私の記憶では、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を殺害し、蝦夷、入鹿の蘇我一族を滅ぼした政変と覚えていた。
確かに、646年に改新の詔が発せられ諸政刷新にのりだしたとある。これが「大化の改新」であった。
私の息子の「日本史用語集」(山川出版社発行)には、「乙巳の変(いつしのへん)」というのが出ている。
それが、蘇我氏を滅ぼした政変のことであった。
「大化の改新」もでており、「蘇我氏打倒に始まる一連の政治改革。氏姓制度の弊を打破し、天皇中心の中央集権国家建設を
目標とした」とある。
急に私が古代史の話を書き始めたのは、以前から歴史には興味がありいろんな本やブログなどを見ていたからでもあるが、
昨今のコロナ禍で、集中して読書する気が無くなっていたからでもある。
毎日、自粛と3密回避やコロナ感染者の数やワクチンの効果や弊害など、合わせてオリンピック、パラリンピックと
落ち着くところがないからである。さらにコロナを忘れたような政治の動きである。もうたくさんだ!
それにしても、日本人は忘れやすいというか、過去の経験を結局活かせないのではないか。
先の戦争の時のような、大本営発表のような報道や戦力の小出しの投入、責任感のないリーダーと精神力の強要、
もう我慢ができない。
さらにこの後には、無駄にかかった費用の回収があるだろう。税金の増大だ。
私にはいままでの方策はすべて選挙へ向かっての、というか政権維持へ向かっての魂胆があったようにしか見えない。
楽観的観測で、そのうちよくなると思っていたから、こんな5回もの緊急事態宣言となったし、子供にまで拡大する
感染症になってしまっていると思う。
私にはこれをどうしようともできないし、総裁選にも関与できないのであるから、選挙で望みをつなぐしかないではないか。
早く選挙をやって人心一新、人と政策を変えて、明るい世の中にしてほしい。
さらにゆっくり読書のできる環境を取り戻したい。