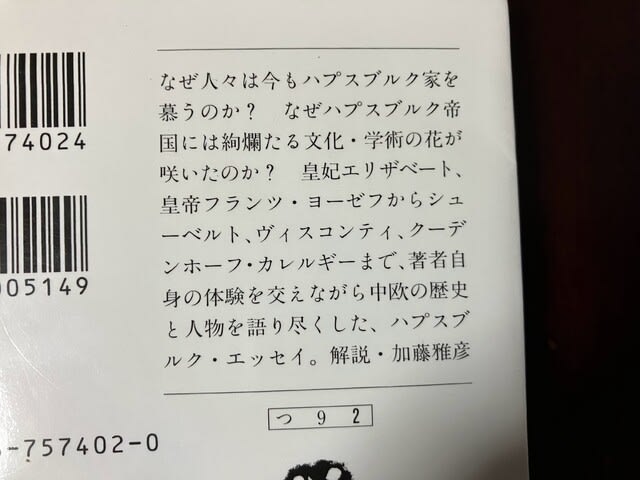映画「スペシャルズ!政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話」を再び観た、2回目だ。以前一度観てよかったのでもう一度観たくなった。2019年製作、フランス、監督エリック・トレダノ、オリビエ・ナカシュ、原題Hors normes。原題はグーグル翻訳で「並外れた」とでた。邦題に「実話」とあるので、実際にあったことなのだろう。

自閉症の子供を預かる無許可の施設「正義の声」を運営するブリュノ(バンサン・カッセル)と自閉症児の就職支援をする(と映画の中では言っていたと思うが)仲間のマリク(レダ・カティブ)。この2人は、国が運営する児童施設や病院、ケア施設などから見放された、あるいは受け入れ拒否された重度の自閉症児を引き受け、自立支援をしていた。その「正義の声」が無許可でずさんな児童の取扱いをしていると国の検査が入り、存続の危機になるが・・・

この映画を観ていると自閉症児をケアすることの難しさがよくわかる。通常の病院・施設であれば暴れたり手に負えない自閉症児は鎮静剤を注射して病室に閉じ込めるようなことをして済ませる。これではいつまで経っても自立は無理だ。この「正義の声」ではなるべく自閉症児に寄り添い、外に連れ出し、自然や動物に触れ、比較的軽度な人には電車に1人で乗せたり、会社にたのんで働かせたりしているが、実際には簡単ではない、電車に乗せれば被害妄想から非常停車ボタンを何回も押したり、会社で働けばやさしくしてくれる女性社員の背中に顔を埋めたりして、問題を起こす。自分自身を傷つけるようなことをする子供もいる。

親や施設などからも手に負えないと見放された自閉症児に愛情を持って接するには、高度な使命感がなければできないことだろう。頭が下がる思いである。この困難な仕事をしている人たちの中には、自閉症ではないが、世の中から見放されて、自分の居場所が見つけられないでいた人たちもいることが映画の中でちょっとだけ触れられている。そうなのかもしれない。自分たちが見放された存在だったからこそ、自分たちを人間として受け入れてくれ、自閉症児の支援をする仕事を与えてもらい、それを意気に感じて頑張って手伝う。立派な行為だ。主人公の2人がどうしてこの仕事をすることになったのかの事情が描かれていればさらによかったと思う。
見る価値のある映画だと思う。